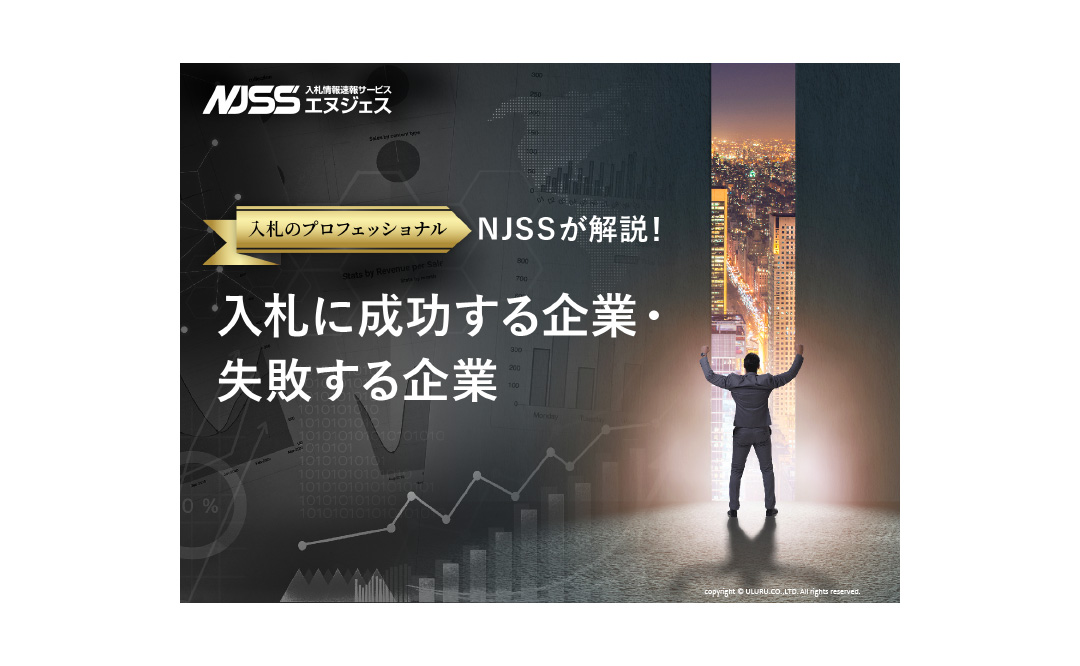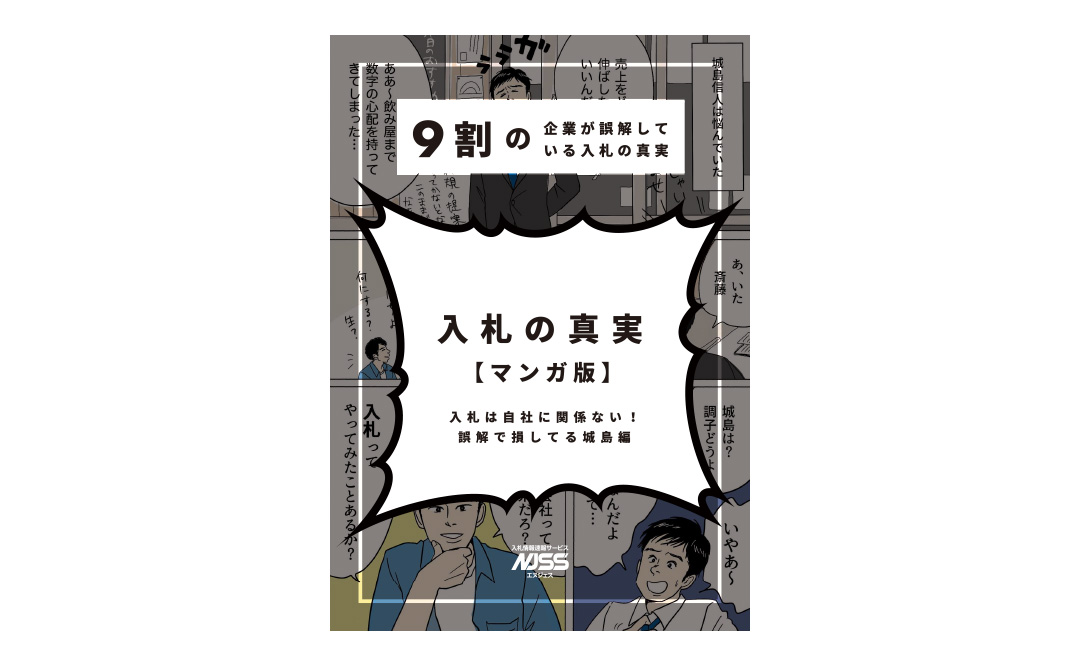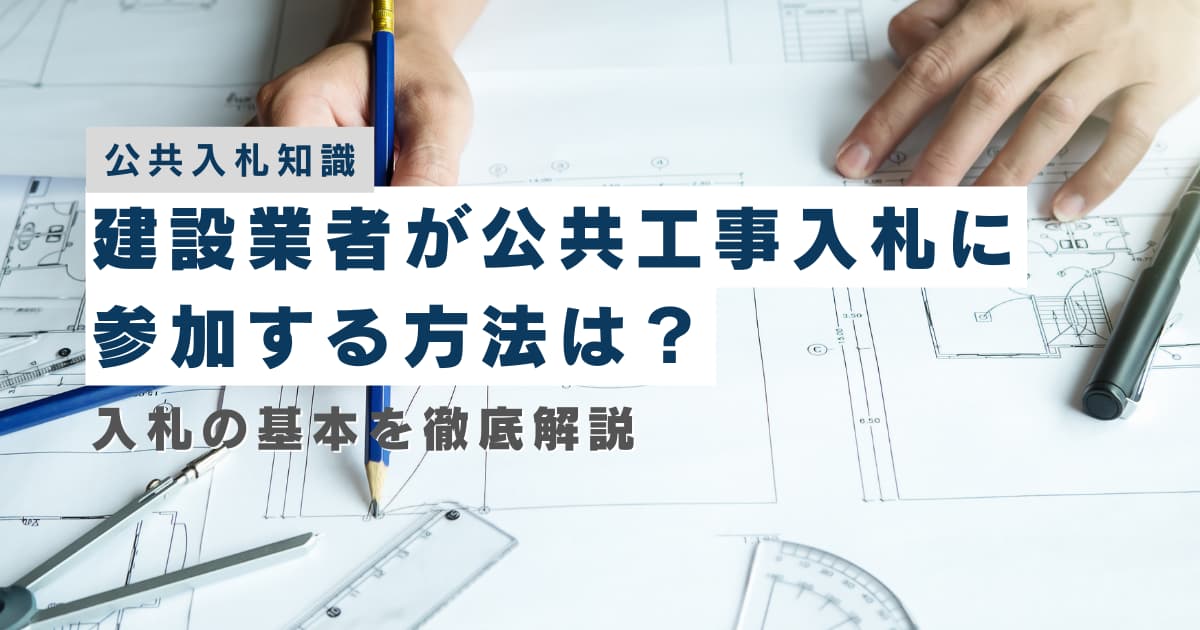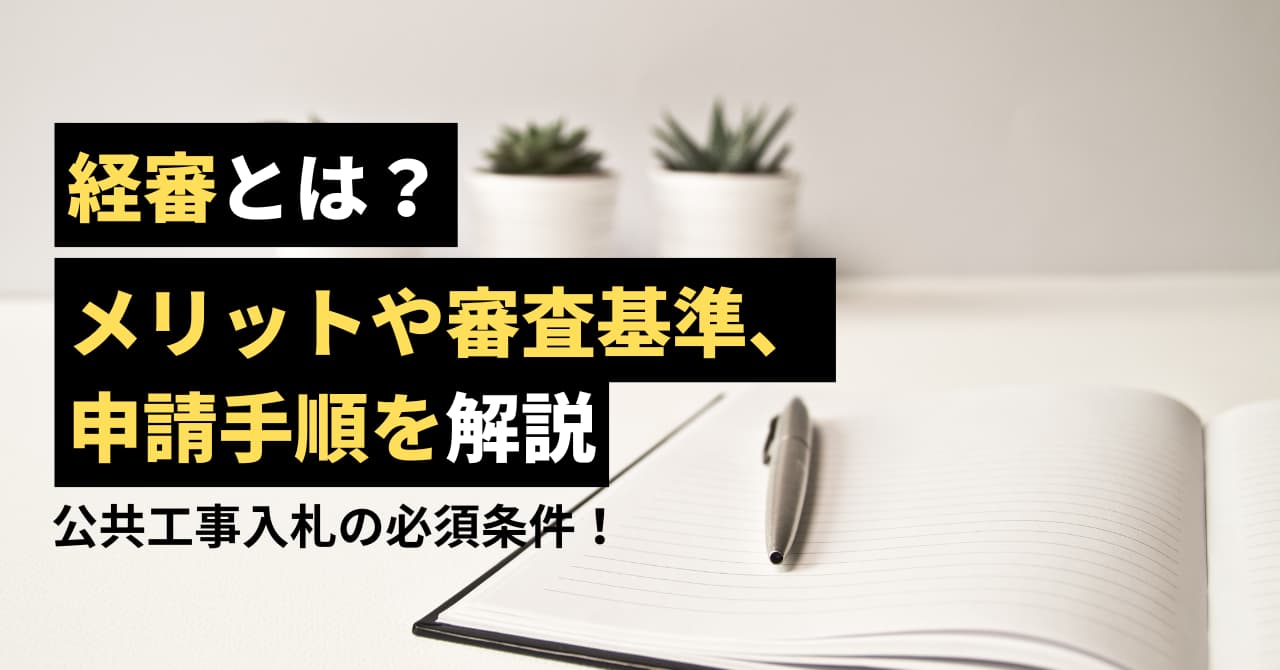公共工事は民間工事と比べて「利益が出にくい」と言われることもあります。
これから公共工事に参入しようとする企業にとっては、利益率は採算性を正しく見極めるための重要なポイントになります。とくに、積算基準による価格の標準化や競争入札方式など、公共調達特有の仕組みは利益率に直接影響します
本記事では、建設業全体の一般的な利益率から、公共工事が低くなりやすい理由、実際の現場で利益を圧迫する要因、そして利益率を確保するための対策を解説します。
公共工事の利益率の目安
公共工事の利益率を理解するには、まず建設業全体の利益率の水準を把握することが重要です。
一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)が毎年公表する「建設業の経営分析」では、建設業の利益率に関する基礎的な指標が示されています。
建設業全体の一般的な利益率
同調査によると、平成26年から令和5年にかけて建設業全体の利益率(売上高総利益率)は20~25%程度となっています。
ただし、この値は同調査の対象が中小企業を中心としたものであり、別の統計調査ではこれよりも低い結果となっている場合もあります。例えば、財務省「法人企業統計調査」では、平成26年から令和5年にかけての売上高総利益率が15%~20%程度となっています。
なお、他業種の売上高総利益率について、この財務省の調査では、製造業で20%強、農林水産業で20%~30%、サービス業で45%~50%とされています。
こうした傾向について、CIICの分析では建設業が労働集約型の産業であるため、工業製品のように大量生産によるスケールメリットの追求が困難である点を挙げています。
工事種別による利益率の傾向
同資料では、土木工事や建築工事は、設備工事や職別工事と比べ、利益率が相対的に低い水準にあることが示されています。
とくに建築分野では、売上総利益率や自己資本経常利益率が他分野より低位となる傾向があります。
利益率の種類と計算方法
利益率を検討するうえで重要なのが、「どの利益率を基準に判断するか」です。
単に「利益率」といっても、指標の用途・目的によっていくつかの計算方法があります。
売上総利益率(粗利率)
売上総利益率(粗利率)は、工事の直接的な採算性を判断するための基本指標です。
・売上総利益率(粗利率)=売上総利益÷ 売上高×100
※売上総利益=売上高-原価(直接工事原価)
売上高に対して売上から原価を引いた「利益」の割合を確認することができます。
工事ごとに算出しやすく、「この工事は採算が取れるのか」を最も明確に示す指標です。
営業利益率
営業利益率は、工事原価に加えて一般管理費(会社の経費)まで含めた、事業運営全体の収益性を示す指標です。
・営業利益率=営業利益÷売上高×100
※営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費(販管費)
販管費には、人件費、事務所費、車両費、営業経費などの間接費が含まれます。
そのため営業利益率は、企業としての競争力を測るうえで重要ですが、工事単位での判断には用いにくい側面があります。
経常利益率
経常利益率 は、営業利益に営業外収益・費用(受取利息・支払利息など)を含めた企業全体の利益を示します
・経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高
※経常利益 = 営業利益 ± 営業外損益
公共工事の採算判断で直接使うことは少ないものの、会社の財務基盤や資金繰りを把握するためには欠かせません。
公共工事が民間工事より利益率が低いとされる理由
公共工事は、民間工事と比較して利益率が低くなりやすいと言われます。
公共工事が民間工事と比較して利益率が低いことを示す調査は見当たりません。しかし、主に以下の理由から、公共工事が民間工事より利益率が低くなりやすいと言われていると考えられます。
入札方式による価格競争が強く、粗利率が上げにくい
公共工事の請負先は、一般競争入札や指名競争入札といった「入札方式」で決定されることが基本です。
複数の事業者が同条件で価格競争を行うため、自然と「落札を狙うほど低価格化が進む」構造になります。
ただし近年は、“安かろう悪かろう”を防ぐための制度が整備されています。
公共工事の品質確保の促進に関する法律により、公共工事の品質は価格及び品質が総合的に優れた内容の契約によることが明確化されました。
また「価格と品質が総合的に優れた調達」を可能にするため総合評価落札方式が活用され、技術提案などの非価格要素も評価する取組みが行われています。
積算基準により単価・歩掛・経費率が標準化されている
公共工事は、国土交通省や自治体が定める積算基準に基づき人件費(労務単価)、材料単価などを積算して予定価格とし、この金額を上限に価格競争が行われます。
民間工事であれば難易度等に応じて単価交渉したりする余地がありますが、公共工事では自由度が限定的です。
そのため、積算基準で想定される利益率に収まりやすく、高い利益を狙う価格設定がしにくい構造になっています。
発注者の予算執行ルール
積算単価の標準化に加え、公共工事の予算執行に関するルールも一因と考えられます。
公共工事は国民・住民の税金を財源とするため、その予算の執行には「適正さ」が求められます。そのため、設定した予定価格の扱いは厳格で、1円でも超過すれば落札することはできません。
また、増額を伴う設計変更や追加協議についても、民間工事のように柔軟に認められるわけではなく、必要最小限に留められる傾向があります。
その結果、工事の難易度や企業の経費構造を反映した値上げが難しく、価格上昇が抑制される仕組みが強く働きます。
公共工事で利益率を圧迫する具体的な要因
「公共工事は利益率が低い」と言われる背景について制度的な背景を整理しましたが、契約締結後の運用や現場での対応によっても利益率が圧迫される場合があります。
契約後の労務費・資材費の上昇
公共工事は、契約後に設計変更が限定的で、増額協議も必要最小限に運用される傾向があります。
このため、契約締結後に労務費や資材価格が上昇した場合、企業側が単価をそのまま吸収せざるを得ないケースが生じます。
鋼材・木材価格の急変、燃料費の増加などは短期間で変動する可能性があり、契約時の積算には反映しきれないことがあります。
公共工事では契約額の増額が制度的に難しい場合もあり、結果として粗利率が圧迫される場合があります。
書類・検査対応など、見積に載せにくい事務負担
公共工事では、書類作成や検査対応が非常に多く、事務工数がかかりやすいという特徴があります。
代表的なものとして、
- 施工体制台帳・施工体系図
- 工程管理・出来形管理・品質管理記録
- 中間検査・完成検査の対応
- 協議調書・打合せ記録の作成
などが挙げられます。
これらは、労務費や材料費のように明確に数量化して積算に反映しにくく、実際の現場工数が見積よりも大きくなるケースがあります。
特に総合評価落札方式では、提案書作成や技術資料作成といった「入札段階の工数」も増加しやすく、利益率を引き下げる要因となります。
公共工事で利益率を確保するための実務対策
公共工事は制度的な制約から利益率を確保しにくい場面が考えられる一方で、企業側の運用次第で採算を改善できる余地もあります。
本章では、実務で特に効果が高いとされる利益率改善策を整理します。
見積段階での数量拾い出し精度を高める
数量の拾い出しは、公共工事の原価管理で最も重要な工程です。
積算基準により単価は大きく変動しませんが、数量(=施工量)は企業によって差が生まれやすいポイントです。
そのため、入札参加時に設計図書・仕様書・特記仕様書の読み込みを徹底すること等が重要です。
設計書・図面の不整合を早期に発見し、契約前に照会・協議する
設計書の不備や図面間の不整合が契約後に判明すると、追加施工や手戻りが発生するリスクがあります。
公共工事では増額協議が容易ではないため、契約後の発覚はそのまま企業の負担になる可能性が高い点に注意が必要です。
そのため、施工方法内の曖昧な点、図面と数量総括表の差異、現場条件と設計条件のミスマッチなどは、契約前や入札時に整理し、必要に応じて発注者へ照会を行うことが重要です。
工程管理を徹底し、変更・追加工事を最小化する
公共工事では、工程遅延がコスト増加の主要因になります。
遅延による人工増、仮設期間の延長、外注費の変動などが粗利率を圧迫します。
対策としては、更新リスクの予見と対策(雨天・地中障害物・近隣協議)、進捗管理会議の定期実施などが挙げられます。
工程の乱れは、追加費用を発注者へ請求しにくい公共工事において、最も大きな採算リスクといえます。
労務管理・資材調達のタイミングを最適化する
労務費や資材費は契約後も変動しやすく、利益率に直結します。
対策としては、 繁忙期を避けた施工計画を策定する、資材について複数の仕入先を確保する、早期発注により仕入価格を確定する、などが有効です。
類似案件の落札相場を把握し、適正な見積根拠を作る
公共工事では、落札相場を把握することが価格競争における重要な情報となります。特に、類似工種、類似規模、同一発注者の落札情報は、適正な見積根拠をつくるうえで有用です。
NJSS(入札情報速報サービス)などの入札情報データベースを活用することで、効率的に市場価格を把握し、実行予算の妥当性を検証できます。
まとめ
公共工事の利益率は、民間工事に比べて低くなりやすいと言われることがあります。
これを裏付ける調査は見当たりませんが、公共調達制度の仕組みには利益率を引き下げる方向に作用するものがあります。
例えば、入札方式による価格競争、積算基準による単価・歩掛・経費率の標準化、さらには予算執行などが挙げられます。
また、契約後の運用面でも、労務費や資材費の市況変動、書類・検査対応に伴う事務負担などが、粗利率や営業利益率を圧迫する要因となります。
公共工事で安定した収益を確保するためには、見積段階の数量精度向上、設計書の不整合の早期発見、工程管理の徹底など、企業側の内部管理も極めて重要です。
一方で、こうした制度環境を踏まえつつ公共工事に参入する企業にとっては、市場の落札相場や発注動向を正確に把握することが重要になります。
こうした入札情報のリサーチにおすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。これまでのように発注者ごとに分かれた入札システムにアクセスする手間を削減できます。
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上