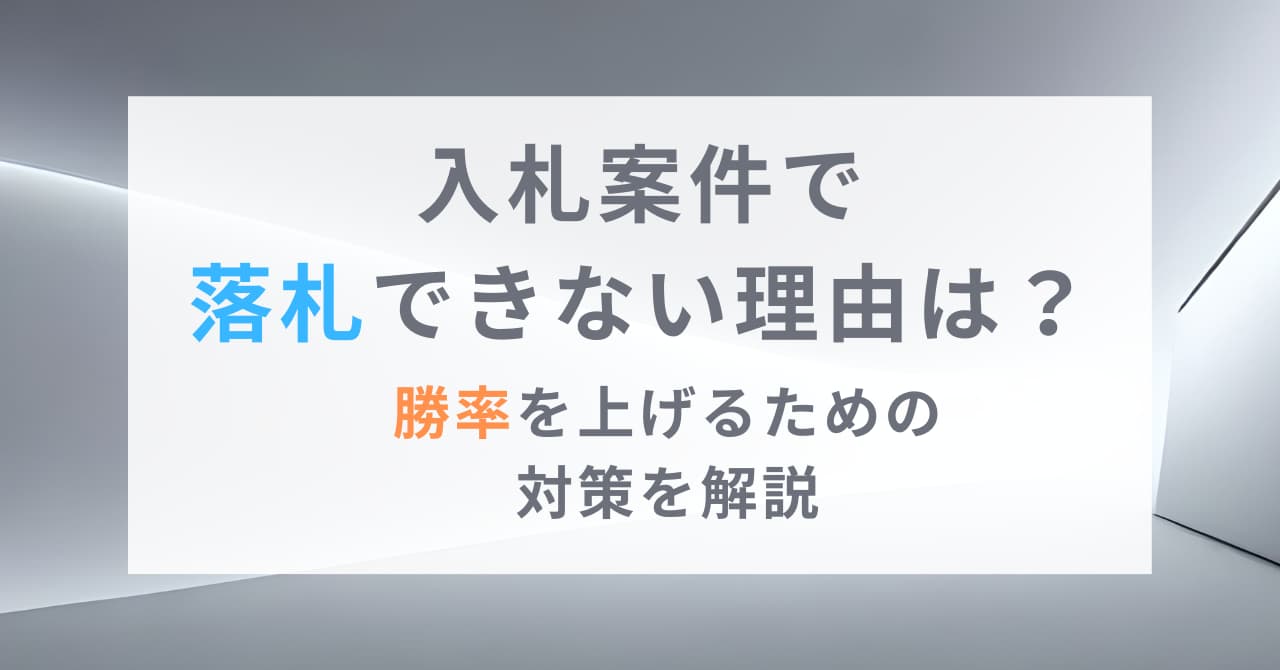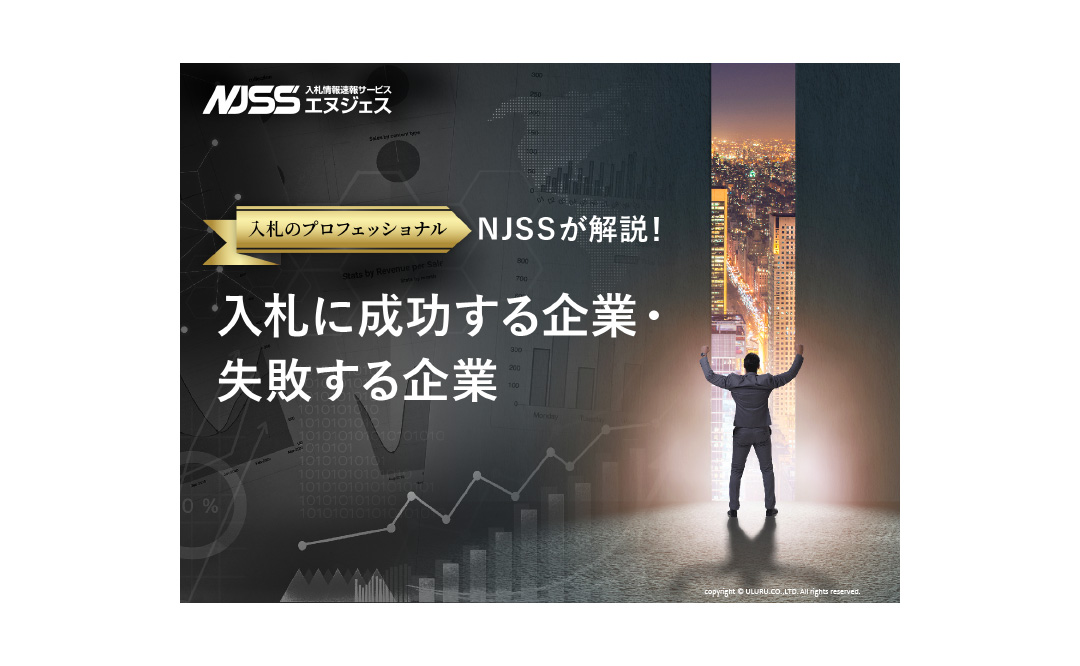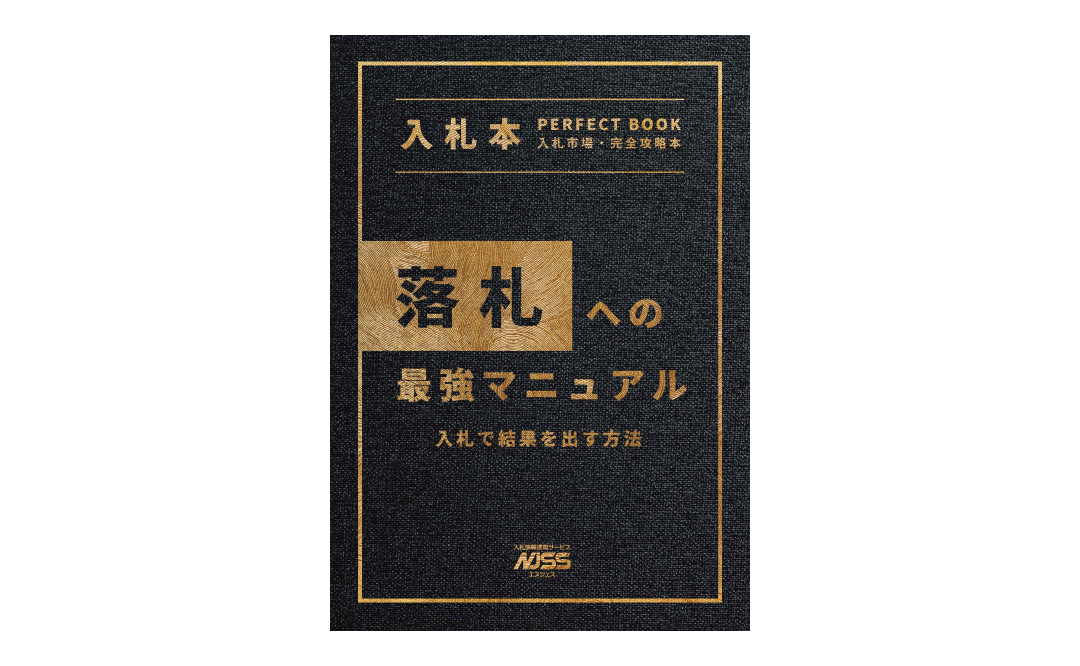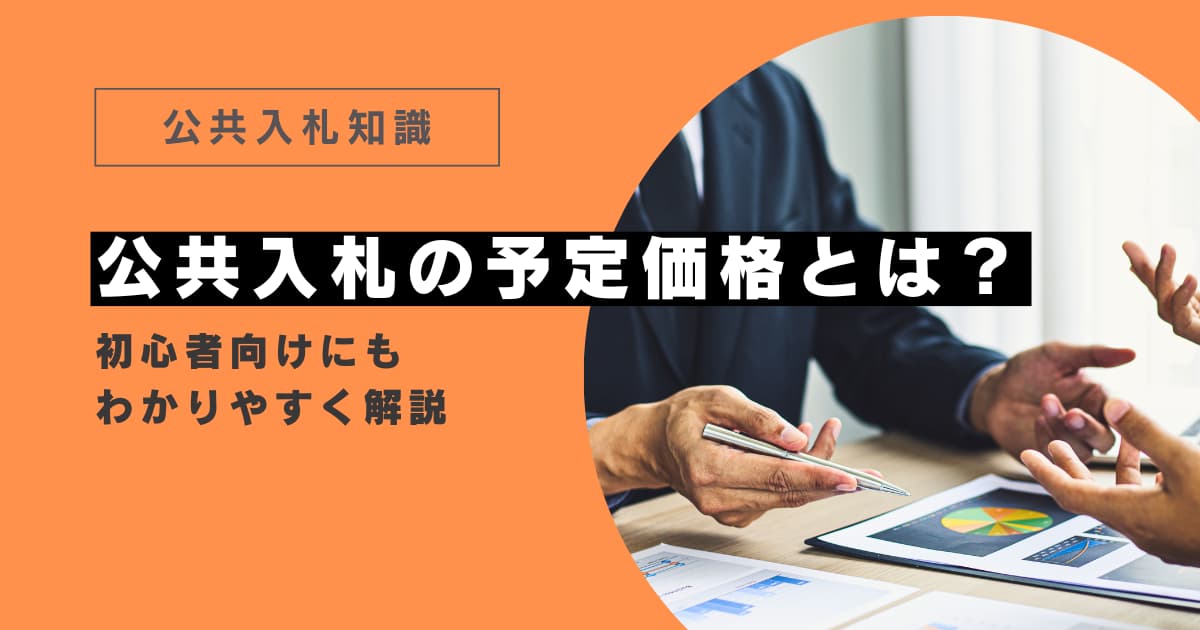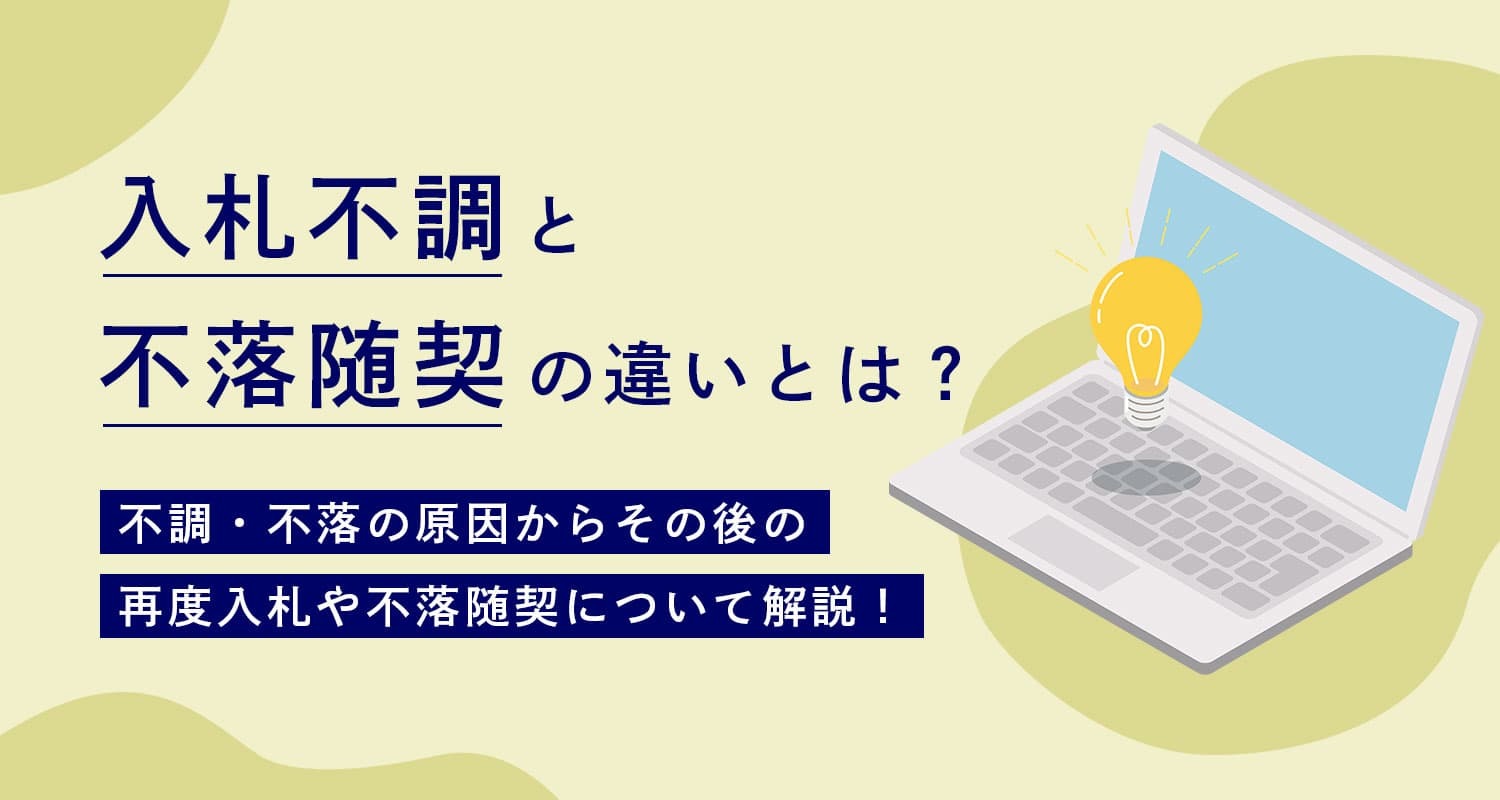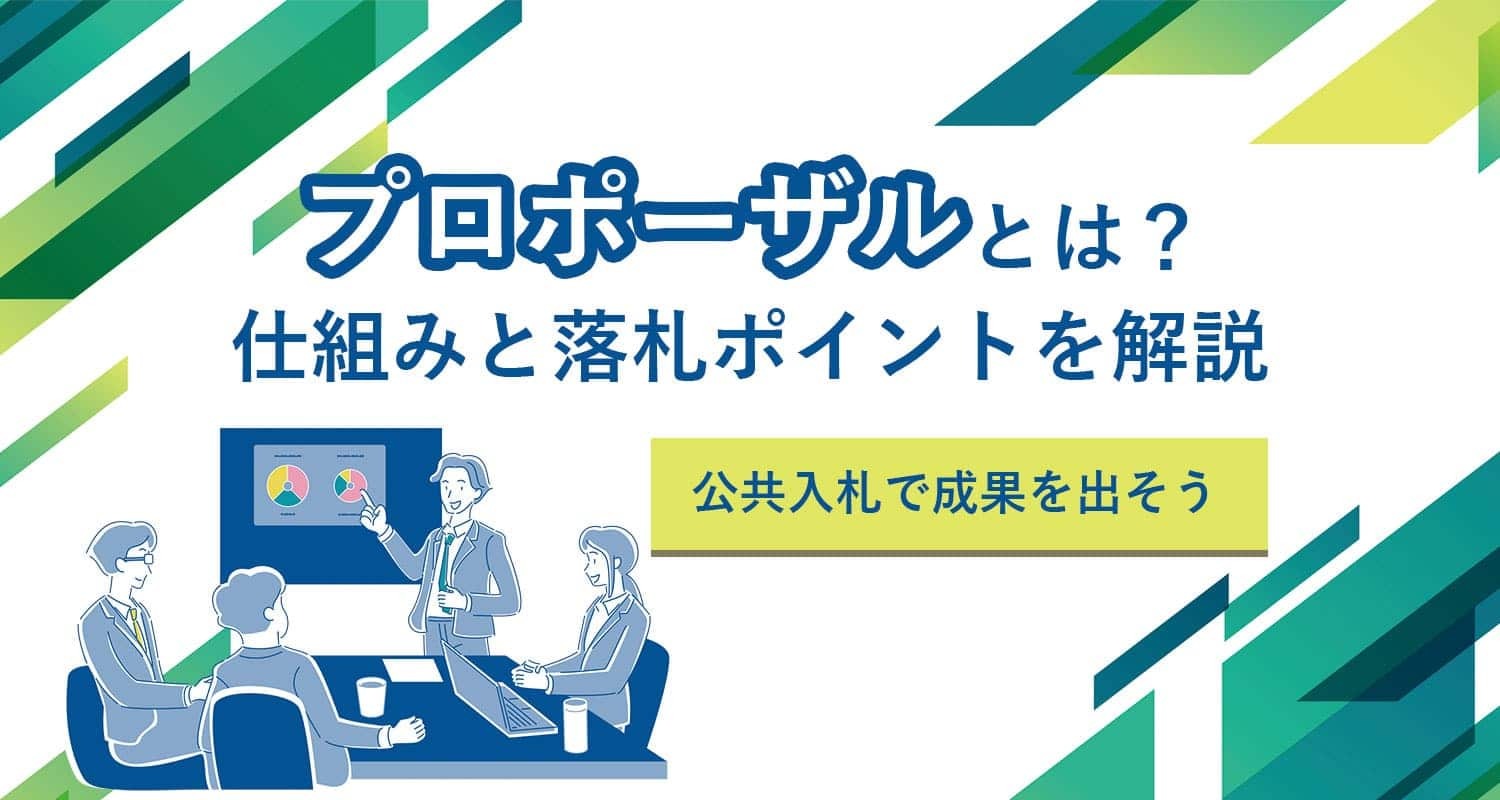「入札案件に参加しても、なかなか落札できない──。」
そう感じている中小企業の担当者は少なくありません。入札では価格が大きな要素となる一方で、単に安く見積もれば良いというものではなく、発注者の積算や評価の仕組みを理解していなければ、落札につながりません。
実際には、落札できない原因は見積り金額だけでなく、格付け、提案内容、情報収集の不足など、複数の要因が絡み合っています。
この記事では、入札案件で落札できない主な理由を整理したうえで、見積り戦略や提案書作成の工夫、落札できなかった後の分析方法を具体的に解説します。
落札率を高めたい方は、ぜひ一度自社の入札プロセスを見直すヒントとしてご活用ください。
入札案件を落札できない主な原因は
入札案件を落札できない原因は単に「入札価格が高いから」とは限りません。入札の仕組みや競争環境を十分に把握できていないことも考えられます。
ここでは、受注者側と発注者側、それぞれの視点から主な要因を整理します。
受注者側の要因
入札価格(見積金額)が高すぎる
最も基本的な要因は、見積金額が競合より高いことです。
ただし「安ければ良い」というわけではなく、発注者の予定価格(上限)と、採算を維持できる自社コストとのバランスが重要です。
予定価格の算出には、国や自治体が定める積算基準や労務単価が用いられています。それを理解せずに見積りを作成すると、過大・過小いずれにもずれが生じます。
類似案件の傾向を把握していない
過去の入札結果を分析していないと、適正な価格帯をつかめません。
発注機関や地域によって、同種業務でも落札率(予定価格に対する落札価格の割合)が異なるため、相場感を知らずに金額を設定すると、競争力を欠く見積りになります。
特に、同一発注者による過去案件の落札価格を追うことは、最も効果的な改善策です。
格付けが低い
建設工事や物品・役務の入札では、参加資格の格付けによって参加できる案件の範囲が決まります。
経営事項審査(経審)や入札参加資格申請審査で評価が低いと、そもそも高額案件・大規模案件に参加できず、入札参加機会自体が限られてしまいます。つまり、入札参加機会自体が少ないことで、案件獲得につながっていないことも考えられます。
技術職員数や財務基盤を見直し、定期的な格付け改善を図ることが必要です。
提案書の精度不足
プロポーザル方式や総合評価落札方式などでは、単に価格だけでなく、技術提案書や実施計画書の内容も評価対象になります。
形式的な要件を充足させることはもちろん、その上で発注背景を踏まえた上で自社ならではの適切な提案をしなければ、他社との差別化ができず、評価点が伸びません。
実績・体制・独自性を具体的に示し、発注者が「この事業者なら任せられる」と思える説得力を持たせることが大切です。
発注者側の要因
一方で、落札できない背景には、発注者側の設定や環境も影響します。
予定価格が実勢価格と乖離している
資材費・人件費等の実勢価格の上昇が反映されていない場合、予定価格自体が低すぎることがあります。
この場合、適正な見積を提出しても、上限を超えて失格となることがあります。
地域・実績要件の設定
一部の案件では、地元業者や特定の実績を持つ事業者に限定して公募する場合があります。
該当しない場合は、入札資格を満たしていても参加が難しくなります。
公示期間・納期の短さ
公示から入札日までの期間が短い案件では、十分な積算や提案準備ができず、結果として不十分な見積り・提案となるケースもあります。
ただし、公示期間が短期間の案件は他社にとっても参入を困難にする要素でもあります。そのため、情報収集を逃さず行うことで、有利に働かせることもできます。
入札案件を落札するための見積り戦略
入札で継続的に成果を上げるためには、単に価格を下げることではなく、根拠のある適正な見積りを行うことが不可欠です。
短期的に受注を狙って根拠のない低価格で応札してしまうと、利益を確保できず、結果的に次の案件への体力を失うことにつながります。
公共調達における競争は、「安ければ良い」という単純なものではありません。発注者が求めているのは、妥当なコストの範囲で確実に業務を遂行できる事業者です。
そのためには、発注者の積算構造を理解し、自社の強みや実績を踏まえて、論理的に説明できる見積金額を提示することが求められます。
こうした「適正かつ戦略的な見積り」を実現するためには、以下の点を押さえることが重要です。
発注者の積算方法を理解する
入札の予定価格は、発注者が算出した「基準となるコスト」に基づいています。
例えば、建設工事に係る入札の場合、予定価格の内訳は、労務単価・材料単価・歩掛・共通仮設費・一般管理費などで構成され、国や自治体ごとに積算基準が定められています。
また、物品・役務に係る入札の場合、複数の事業者から徴取した見積書の金額や、類似案件の落札価格等を参考に決定している場合もあります。
このような発注者の積算構造を理解していないと、自社の見積り金額がどの水準にあるのかを正確に把握できません。
特に建設工事では、国土交通省や総務省が公表する積算基準書や公共工事設計労務単価を参照することで、予定価格の仕組みを推測できます。
こうした理解をもとに見積りを行うことで、「過大でも過小でもない、競争力のある金額」を設定することが可能になります。
過去案件を分析して落札価格の相場感を把握する
見積り戦略の基礎は、過去の落札結果を分析することです。
同一発注者・同種業務でも、年度や地域によって落札率(予定価格に対する落札価格の割合)は異なります。
具体的には、過去の入札データを確認し、落札率(予定価格に対する落札価格の割合)、応札者数、応札業者の傾向(大手か中小か)などを把握することが重要です。こうした情報収集を通じて、「○○○万円台で入札すれば、おそらく落札できる」などといった、実際の相場感を掴むことができます。
感覚や経験に頼るより、データを根拠にした見積りを行うことで、入札の再現性と精度が格段に高まります。
利益率とリスクのバランスを取る
総合評価落札方式等では、過去の受注実績・成績が評点に反映される場合もあるため採算度外視で受注を優先する考えもできるでしょう。
しかしながら、落札を優先して過度に価格を下げると、利益が残らず、事業継続に支障をきたすおそれがあり、かえって財務状況の悪化を招く懸念があります。
最低限確保すべき利益率(限界利益ライン)を明確にし、「落札しても赤字になる入札」は避ける判断力が重要です。
入札(プロポーザル)の提案書で評価を落とさない工夫
入札の中には、価格だけでなく技術力や提案内容も評価対象となる案件があります。
特に、総合評価落札方式や公募型プロポーザル方式では、提案書の内容が結果を左右します。
見積り金額が競争力のある水準であっても、提案の完成度が低ければ評価点が伸びず、結果として落札を逃すことも少なくありません。
ここでは、発注者の評価構造を理解し、提案書の質を高めるための具体的なポイントを整理します。
評価項目を正確に把握する
まず重要なのは、評価項目と配点を把握することです。
評価基準は募集要領や審査基準書に明記されているため、これらを読み込みます。
多くのプロポーザルや総合評価では、次のような観点で審査が行われます。
- 業務遂行能力(体制・経験・技術力)
- 提案内容の実現可能性・独自性
- コストの妥当性・経済性
- 契約履行に対する信頼性(過去の実績・法令遵守)
案件や発注者によっては、要領に配点が記載されている場合があります。
配点が分かる場合は、類似案件での競合他社の参加状況を鑑みながら「自社の提案では何点取れそうか」をシミュレーションしてみることも有効です。
例えば、仕様に対して提案内容自体に強みがある場合は見積額をやや強気で作成し、反対に他社と比較して提案内容で劣る点が考えられる場合は、見積額を引き下げ価格での加点を狙う等の対応を検討することが採点のシミュレーションを通じて可能となります。
また、評価項目を把握する過程で「発注者が何を重視しているか」を読み取ることも重要です。
たとえば、「課題把握力」や「地域貢献」などの観点が加点対象であれば、単なる仕様の理解ではなく、発注者の目的や背景を行政計画等から調査して、その内容を踏まえた提案を意識することが有効です。
提案書の書き方を工夫する
提案書は、内容そのものよりも伝わりやすさ・説得力が評価を左右します。
発注者が示す形式を満たすことはもちろん、いかに良い提案でも、提案書の構成が曖昧だったり文章が冗長だったりすれば、評価者の印象に残りません。
効果的な提案書を作るための基本ポイントは次の3つです。
結論先行で書く
冒頭で提案の要旨(目的・方法・成果)を明示し、全体像を短く伝えます。審査担当者は短い時間で何件もの審査を行います。そのため、提案の全体像を端的に伝えることが有効です。
数値・根拠を示す
自社が実施する場合のメリットを数値・根拠とともに示すことが重要です。
昨今、行政が事業を立案する際にはEBPM(Evidence-Based Policy Making・証拠に基づく政策立案)の考え方が求められています。事業の効果として「○○を行います」といったアウトプットのみでの訴求うでは十分ではありません。
そのため、「○○により作業時間を△%削減」「年間コストを○万円圧縮」など具体的な効果を示すことで、より高い評価を得られる可能性があります。
発注者の意図を読み取る姿勢を持つ
提案書作成で最も重要なのは、「発注者の視点で考える」という姿勢です。
「自社の強みをアピールする」「自社サービスを買ってもらう」が目的ではなく、「発注者の課題を解決できること」を具体的に示すのが提案の本質です。
発注者の意図を把握するには、
- 募集要領・仕様書の文言から「狙い」を読み取る
- 同一部局・同分野での過去案件を調べ、傾向を分析する
といった下調べが欠かせません。
落札できなかった入札案件の分析方法
入札で落札できなかった場合は、結果を振り返り原因を明確にすることが重要です。
分析を行わず次に進むと、同じ失敗を繰り返すことになります。
自社の見積額と他社の応札額・落札価格を比較する
まずは、自社の見積額と落札価格の差を確認しましょう。
公告や入札結果で落札率や応札者数を把握し、自社の価格が高すぎたのか、競争が激しかったのか、あるいはそもそも特定の他社に有利な仕様であったのか等を判断します。
競合の構成・優位性を分析する
次に、落札企業の構成や強みを調べます。
価格以外が評価される方式の案件で地域密着型企業や実績豊富な事業者が多い場合、単なる価格だけでなく実績・信頼性が評価されている可能性があります。
物品・役務の入札の場合、仕様自体が特定サービスを提供する他社にとって有利な条件でなかったかも検討します。
仕様のうち、どの要素が他社に有利に働いたか、反対に自社にとってどういった仕様であれば優位性が確保できるのかを明らかにしておくと、次回以降の参加判断に役立ちます。
提案書の完成度・作成工程を検証する
プロポーザル方式では、提案書の内容や完成度も検証が必要です。
要件の理解不足や説得力の欠如があれば、次回は構成や根拠の示し方を改善します。
また、社内での作成工程も振り返りましょう。担当者任せで情報共有が不足していたり、提出直前に慌てて仕上げた場合は、品質が安定しない原因になります。
情報収集体制を見直す
入札情報の収集スピードや網羅性も、落札率に大きく関係します。
公示期間が短い案件では、情報を見落としたり準備不足のまま参加するケースも少なくありません。
複数の発注機関のサイトを個別に確認している場合は、一元的に検索できる仕組みを導入することで見落としを防げます。
たとえば、全国の入札情報を横断的に検索できるNJSS(入札情報速報サービス)のようなサービスを活用すれば、短期間で関連案件を把握し、準備に充てる時間を確保できます。
まとめ
入札で落札できない原因は、単に価格の問題だけではありません。
発注者の積算構造を理解せずに見積りを行ったり、過去案件の傾向を把握していなかったりすることで、自社の見積りが相場からずれてしまうことも多くあります。
また、総合評価やプロポーザル方式では、価格に加えて提案書の内容・完成度が評価を左右します。
発注者の目的や課題を正しく理解し、論理的かつ実現性の高い提案を行うことが、落札への近道です。
さらに、落札できなかった案件の分析を通じて、自社の強みや改善点を客観的に見直すことも重要です。
価格・提案・競合・情報収集という4つの観点から振り返ることで、次の入札に確実に活かせます。
こうした入札情報の収集・分析に役立つのが NJSS(入札情報速報サービス) です。
NJSSでは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を一括検索できます。
複数システムを個別に確認する手間を省き、8日間の無料トライアルも利用可能です。入札活動の効率化と精度向上に、ぜひ活用してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上