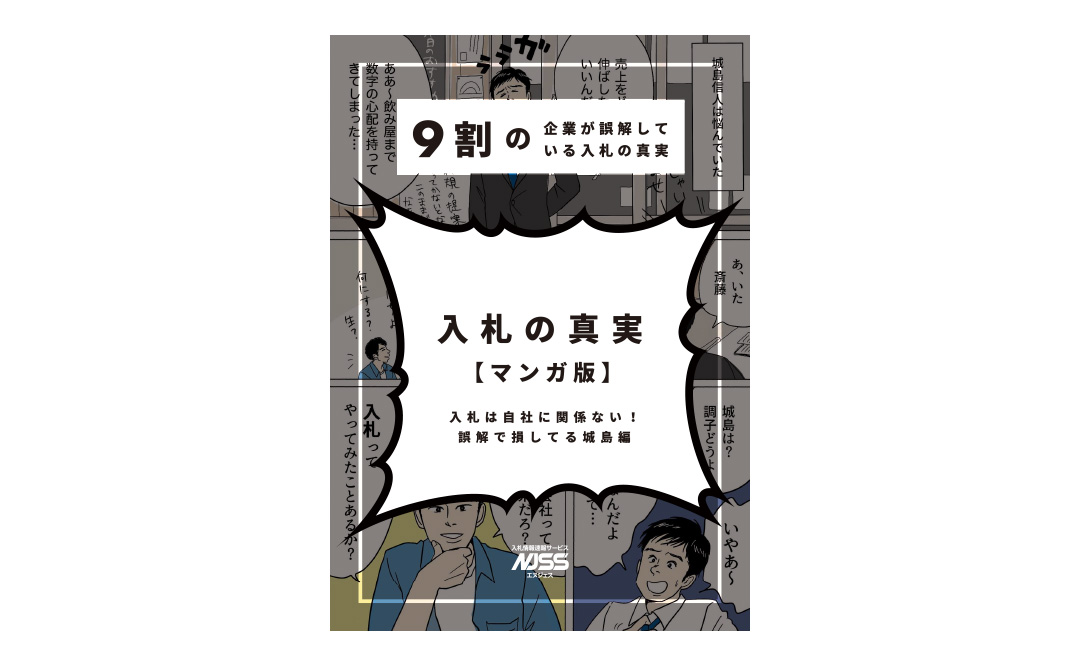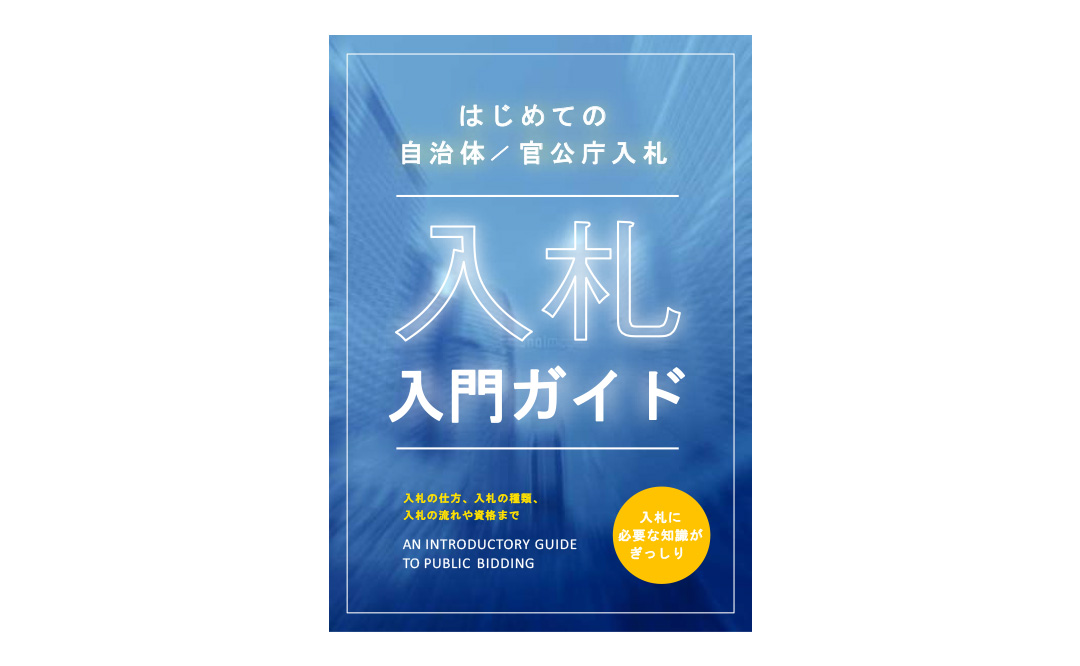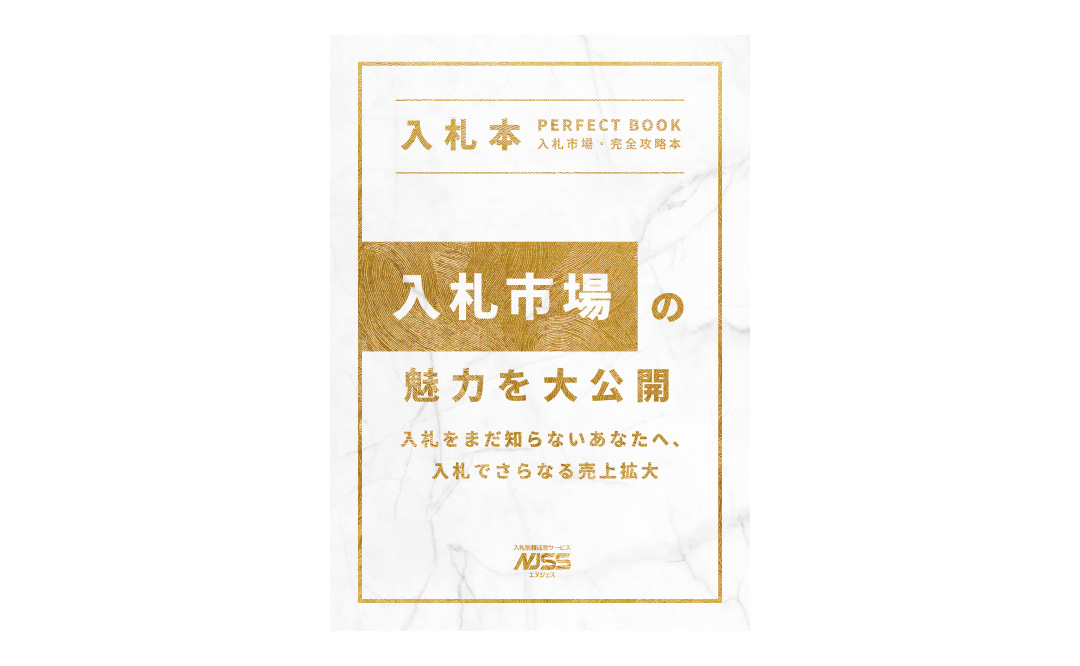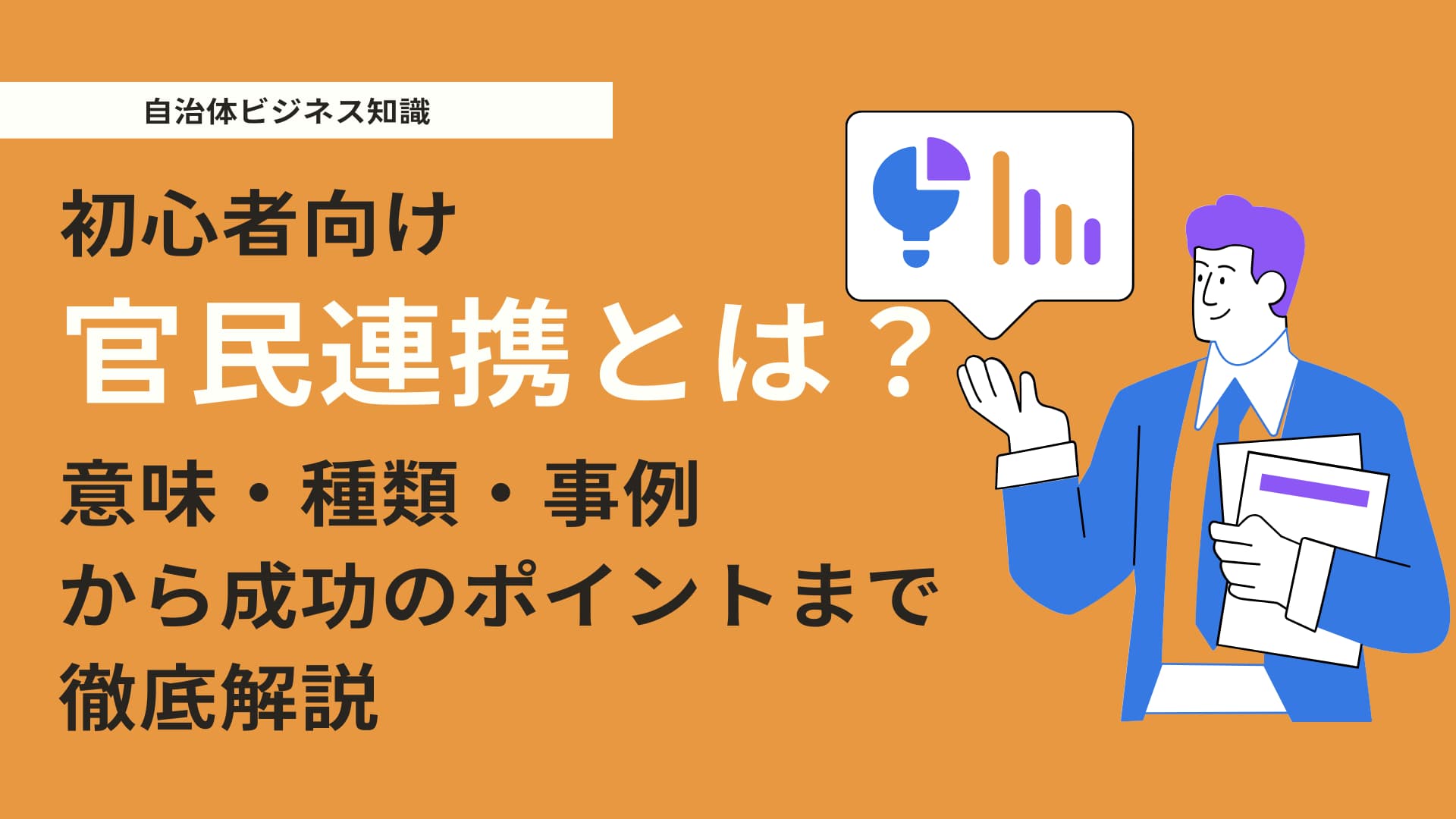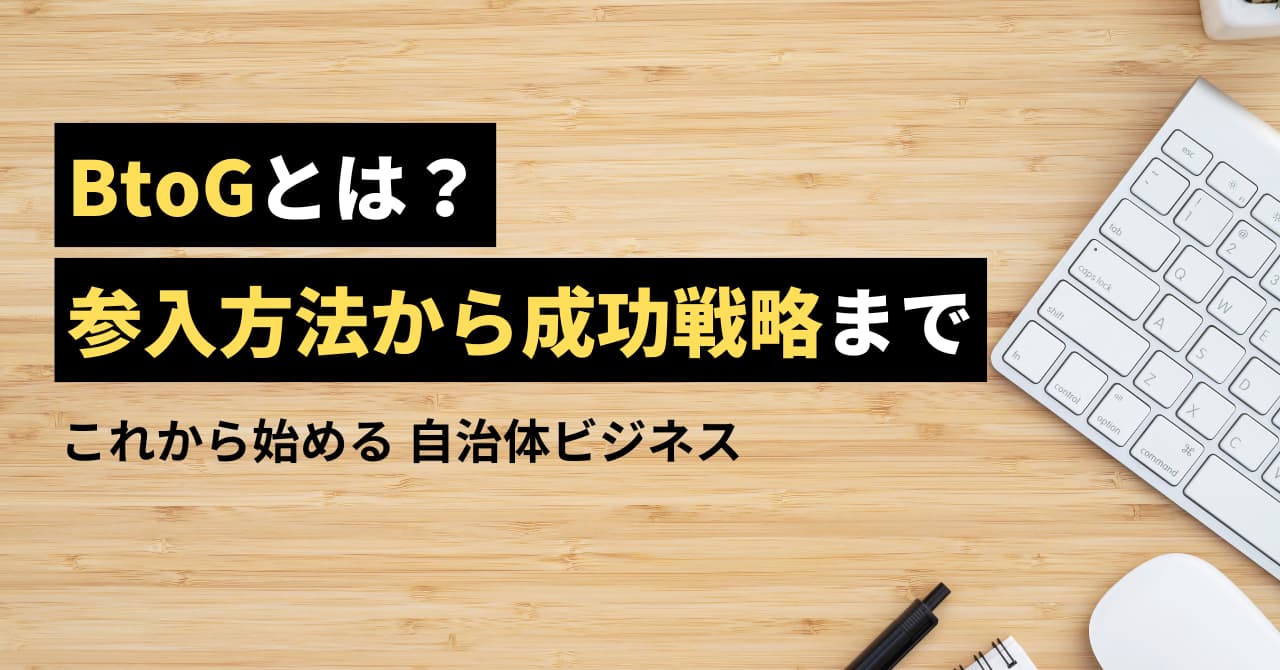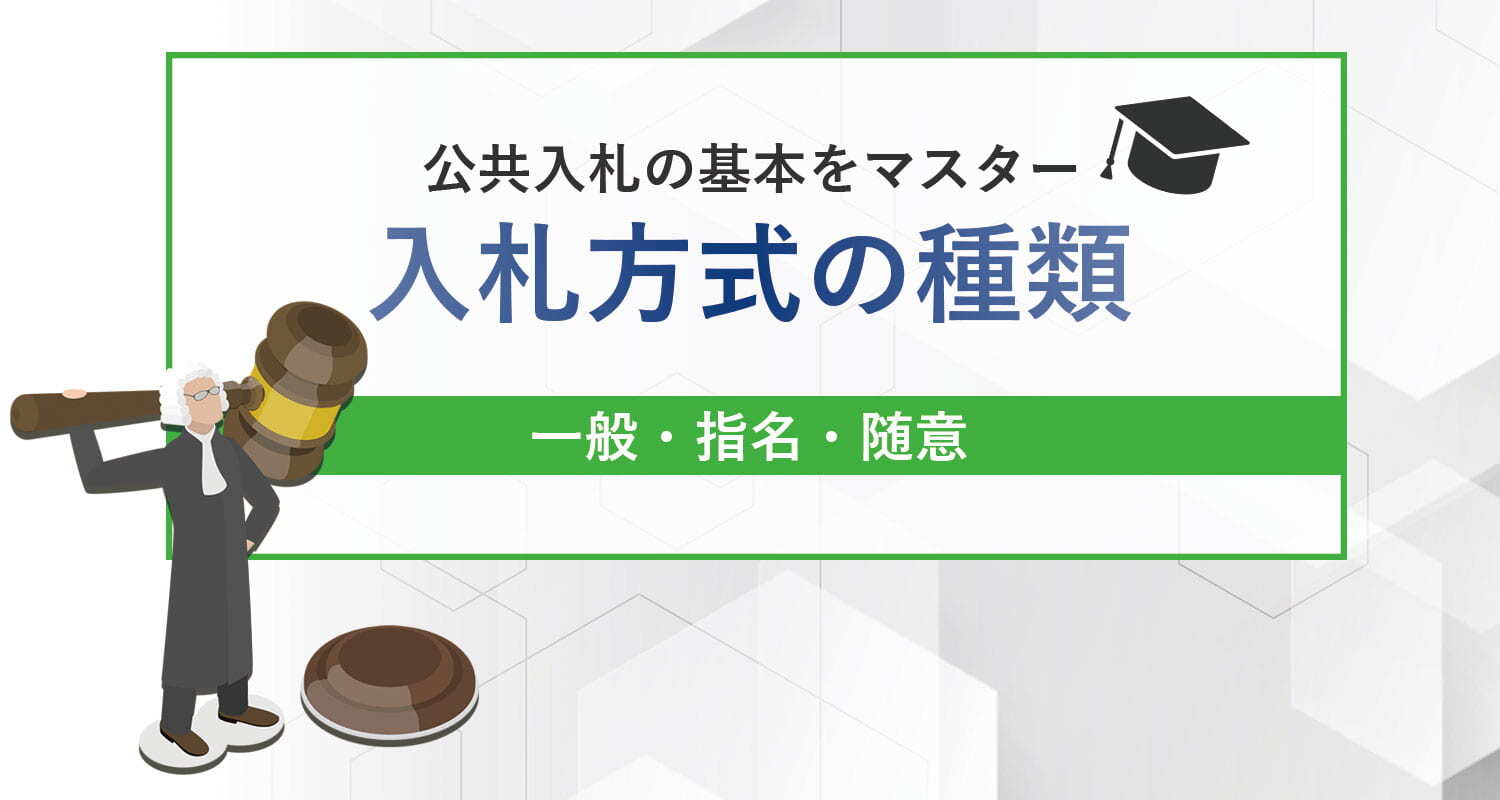- 官公庁営業は民間と異なり「入札制度」が基本
- 行政のスケジュールと多様な入札方式の理解が重要
- 組織・政策理解と効率的な情報収集が成功の鍵
官公庁営業とは、国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人など、公的な機関に対して自社の製品やサービスを提案し、契約獲得を目指す営業活動を指します。
省庁・地方自治体といった官公庁の案件は毎年発注されるものも多く、また支払遅延のリスクがない等様々なメリットがあることから、官公庁専門の担当者を充てて営業活動を行う企業もあります。
しかし「官公庁営業」といっても、どのようにアプローチすれば良いのかと戸惑う方も少なくないでしょう。民間企業への営業とは異なるルールやプロセスが存在するため、その特性を理解せずに臨むことは、まったく成果が出ないといった事態にもなりかねません。
本記事では、官公庁営業の基本的な仕組みから、民間営業との決定的な違い、さらには案件獲得に成功するための具体的なコツを解説します。
行政の調達システムを理解し、貴社の製品やサービスを官公庁に効果的に提案するための実践的な知識理解して、営業活動の参考にしてみてください。
もくじ
官公庁営業とは?
官公庁営業とは、国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人など、公的な機関に対して自社の製品やサービスを提案し、契約獲得を目指す営業活動全般を指します。
官公庁営業の定義
官公庁営業は、文字通り「官」つまり行政機関を対象とした営業活動です。
民間企業への営業では、製品・サービスの魅力や価格交渉、担当者との関係構築などが中心となりますが、官公庁営業においては、公共性・公平性・透明性を踏まえたアプローチが重要です。
基本的な案件獲得方法:入札制度
官公庁から事業を受注しようとする場合、民間企業のように個別の交渉や随意契約で簡単に契約に至ることはありません。
官公庁が何かを購入したり、事業を委託する場合は「入札」を行うことが原則です。
したがって、官公庁からの受注を目指す企業は、原則として「入札」に参加し、最も有利な条件を提示した受注者として選定される必要があります。
この入札制度への対応が、官公庁営業の根幹をなす活動となります。
官公庁職員の役割とコンプライアンス
官公庁の職員は「全体の奉仕者」として、特定の企業や個人に不当な利益を与えないよう、厳格なコンプライアンス上の制約を受けています。
そのため、民間営業では有効とされるような接待や贈答などは、官公庁営業においては厳禁です。
営業活動を行う際には、これらの公務員倫理やコンプライアンスに関する規定を深く理解し、適正な範囲内での情報提供や提案活動に徹する必要があります。公平性を重んじる行政の特性を尊重した営業姿勢が求められます
官公庁営業の基本:行政スケジュールの理解と入札方式
官公庁から案件を獲得するには、行政特有のスケジュール感と、多岐にわたる入札方式を深く理解することが重要です。
これらは、案件獲得の機会を見極め、適切な戦略を立てる上での基礎となります。
年度予算と調達スケジュール
官公庁における製品やサービスの調達は、年度ごとに編成される予算に基づいて実施されます。各省庁や地方自治体は、ある年度の予算を前年度の夏頃から編成作業を始め、年度末に議会での議決を経て成立し新年度4月から予算の執行(発注)を行います。
そのため、例えば通年で実施されるような継続的な事業の入札は、予算が確定し、事業が本格化する年度の始め(多くは4月~5月)に集中する傾向があります。
この行政スケジュールを把握することで、企業は自社の製品・サービスが求められる時期を予測し、準備を進めることが可能になります。
多様な契約方式の理解
官公庁の調達においては、税金を効率的かつ公正に利用するため、原則として価格競争による入札が行われます。入札方式は大きく以下の種類に大別されます。
一般競争入札
最も一般的な方式で、参加資格を満たす全ての企業が自由に参加できます。
指名競争入札
発注機関が、あらかじめ選定した特定の企業グループを指名し、その中で競争させる方式です。実績や信頼性が重視される案件で用いられることがあります。
随意契約
特殊な事情がある場合に限り、競争入札によらず特定の事業者と直接契約を結ぶ方式です。原則として避けるべきとされていますが、緊急時や専門性が極めて高い場合や、価格が低額な場合などに適用されます。
これらの価格競争を基本とした入札方式に加え、価格以外の要素も加味して最適な事業者を選定するために、以下の方式も採用されています。
総合評価落札方式
価格だけでなく、企業の技術力、実績、信頼性、提案内容などを総合的に評価し、最も優れた提案を行った企業を落札者とする方式です。公共性の高い大規模な工事や、専門的なサービス調達で多く用いられます。
公募型プロポーザル方式
契約内容が複雑・専門性が高い場合などに、事業者から技術的な解決策や企画提案を公募し、最も優れた事業者を選定する方式です。単なる価格だけでなく、提案の質や実現可能性が重視されます。
したがって、官公庁から受注を獲得するには、これらの多岐にわたる入札方式を理解し、官公庁に対して販売する商品・サービスがどのような形態で発注されることが多いのかを確認しておくことが重要です。
官公庁営業と民間営業との違い
官公庁営業と民間営業は、製品やサービスを提供するという点では共通しています。しかし、そのプロセス、重視される原則、そして求められる姿勢において根本的な違いがあります。
これらの違いを理解することは、官公庁との関係を構築しながら受注を獲得する上で重要です。
調達プロセスの計画性
民間企業における営業は、顧客のニーズや市場の動向に柔軟に対応し、比較的短期的な意思決定で契約に至るケースが多く見られます。
一方で、官公庁の調達は、編成された年度予算に基づいて、ある程度計画的に入札が実施されます。この予算編成は、単なる財政状況だけでなく、社会情勢の変化や首長(市長、知事など)の公約が反映された行政計画に基づいて行われます。
そのため、官公庁営業では、年度予算の動向や行政計画を事前に把握し、長期的な視点での提案や準備が求められる点が、民間営業との大きな違いです。
公平性の徹底と裁量の排除
民間営業では、営業担当者と顧客との間に形成された信頼関係や個人的な繋がりが、受注に結びつく重要な要素となる場合があります。
しかし、官公庁営業においては、このような個人的な関係性は契約に直結しません。官公庁の入札は法律に基づき手続の方法が定められています。
「コンプライアンス」の違いと順守
民間営業では、取引先との円滑な関係構築のために、接待や贈答品などが一定の範囲で慣習として行われることがあります。
しかし、民間では一般的な慣習として行われることであっても、官公庁営業においてはコンプライアンスの観点から行うべきではありません。
官公庁職員は「全体の奉仕者」であり、特定の企業から利益供与を受けることは、贈収賄などの汚職につながる可能性があるため、極めて厳格な倫理規定と法律が適用されます。
そのため、官公庁営業では、あくまでも製品やサービスの質、そして適正なプロセスを通じてのみ契約を獲得するという、極めてクリーンな営業姿勢が求められます。
官公庁営業で成功するためのコツ
官公庁営業を成功させるためには、民間営業とは異なる独自の「コツ」が存在します。
行政の特性を深く理解し、戦略的にアプローチすることで、案件獲得の可能性を大きく高めることができます。
行政組織と政策の深い理解
行政機関は、民間企業とは異なり、法律や規則に基づいて厳格なルールで運営されています。
そのため、営業を行う側も、官公庁がどのような法規や内部規定に基づいて動いているのかを知っておくことが重要です。
さらに、行政の調達活動は、単に物品やサービスを購入するだけでなく、社会が抱える様々な課題を解決するための政策を具体的に実行する手段として行われますので、行政機関が掲げる政策目標と予算の紐付きを理解することが重要です。
例えば、公募型プロポーザルに参加する場合、自社サービスのアピールのみを行うのではなく、発注者の政策動向を分析したうえで、発注者のニーズ・住民のニーズを捉え、社会課題の解決に資するような提案をすることが有効です。
効率的な入札情報の収集
官公庁から案件を獲得する基本は入札への参加です。
そのため、自社が参入したい分野や、強みを活かせる可能性のある入札情報を漏れなく、かつ効率的に収集することが成功の第一歩となります。
国や地方自治体の公式サイト、電子調達システムなど、情報源は多岐にわたり、発注機関ごとにシステム・ページが存在します。そのため、個別にチェックするのは非常に手間がかかります。
必要に応じて、NJSS(入札情報速報サービス)などサービスも活用して、効率的に入札情報を収集する体制を構築することが重要です。
政策・予算動向を踏まえた営業活動
単に公募されている入札案件に対応するだけでなく、行政の政策や予算の動向を先読みし、それに合致する事業を自ら提案するという能動的なアプローチも非常に有効です。
行政が今後どのような課題に取り組もうとしているのか、どのような分野に予算が重点的に投じられる見込みがあるのかを分析し、自社の技術やノウハウで解決できる具体的なソリューションを提案するのです。
このような提案は、時に公募型プロポーザル方式のきっかけとなったり、行政機関が新たな事業を検討する上での参考になったりする可能性があります。
こうした、行政予算から行政の動向を把握するのにおすすめなのが「GoSTEP」です。
省庁・自治体の予算書、行政事業レビューの情報を収集しており、入札で発注される前の「上流工程」からの営業活動を支援します。
行政のニーズを行政側が明確にする前に、企業側から具体的な解決策を提示することで、他社に先駆けて案件獲得の道を切り開くことができるでしょう。
まとめ
官公庁営業は、民間企業への営業活動とは異なる独自の特性を持つ分野です。成功のためには、その違いを深く理解し、適切な戦略を講じることが不可欠です。
官公庁案件を獲得する方法は、基本的に入札に参加して落札を目指す方法と、行政の政策や予算の動向を先読みし、自社から事業を提案していく方法の二つに大別されます。
いずれの方法を選択するにしても、実際にどのような事業が発注されているのか、どのようなニーズが存在するのかといった情報を正確に把握し、常に最新の情報を収集することが極めて有効です。
このような情報収集において、NJSSやGoSTEPのようなサービスを活用すれば、全国の省庁・自治体の予算情報・入札情報を効率的にチェックし、自社に最適な案件を迅速に見つけ出すことが可能です。
官公庁営業の特性を理解したうえで情報収集のツールを戦略的に活用することで、より効率的・効果的な官公庁営業を行うことができるはずです。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上