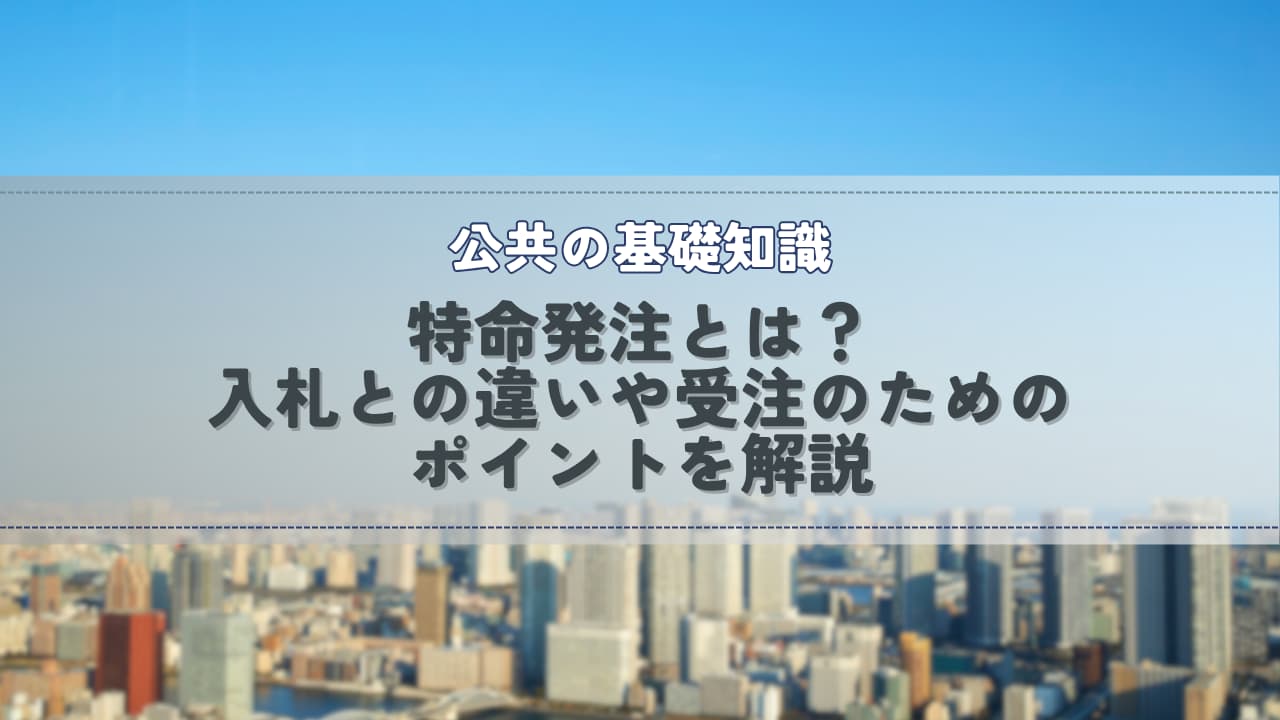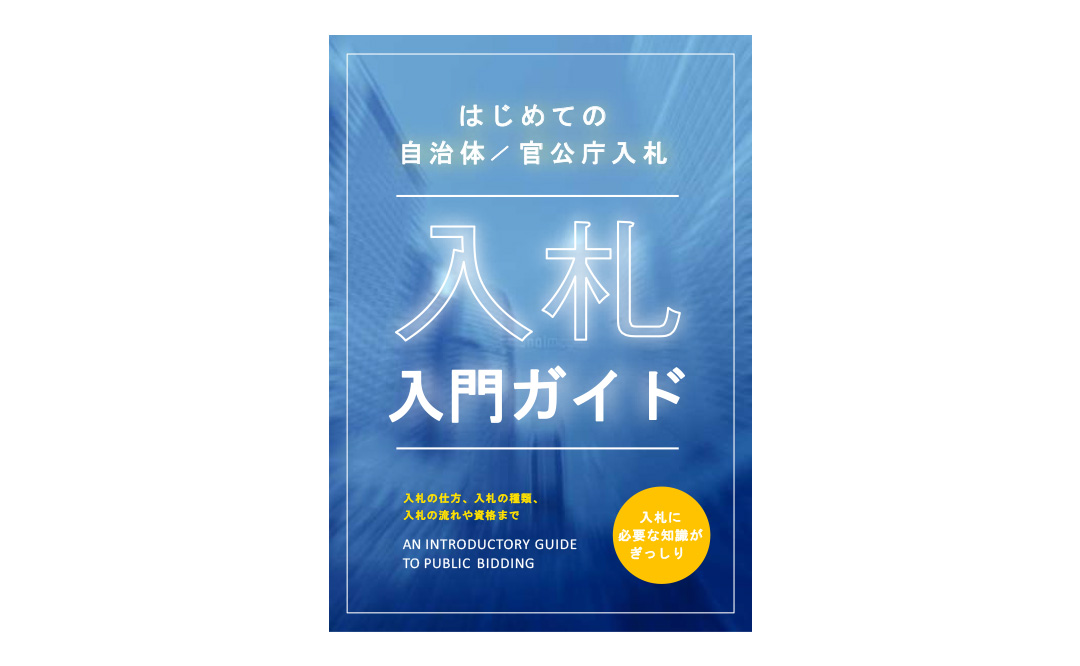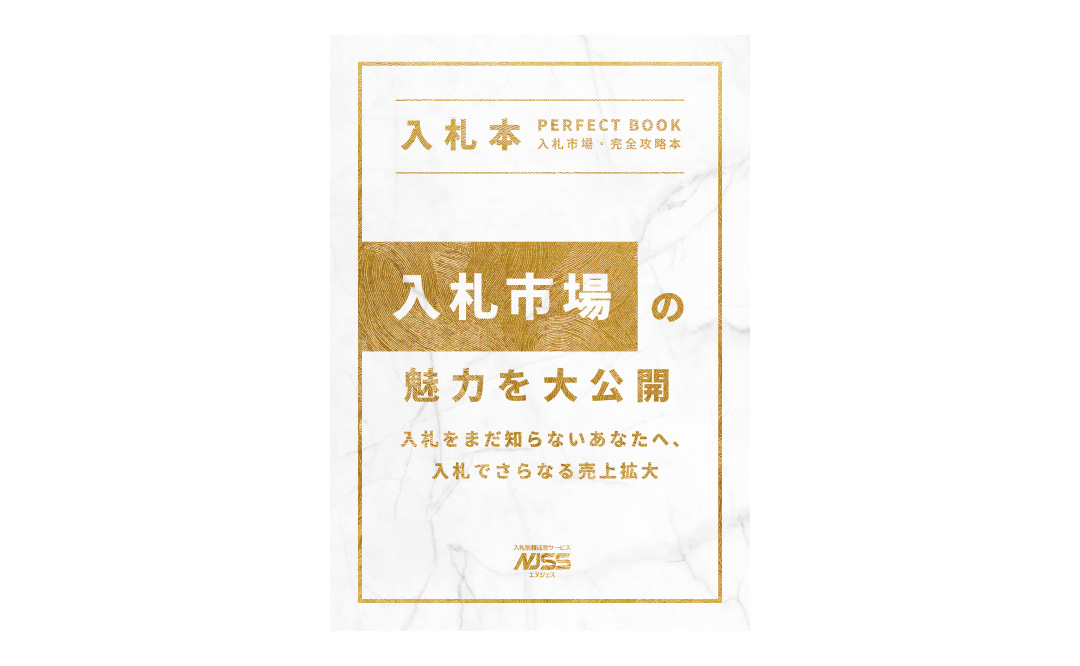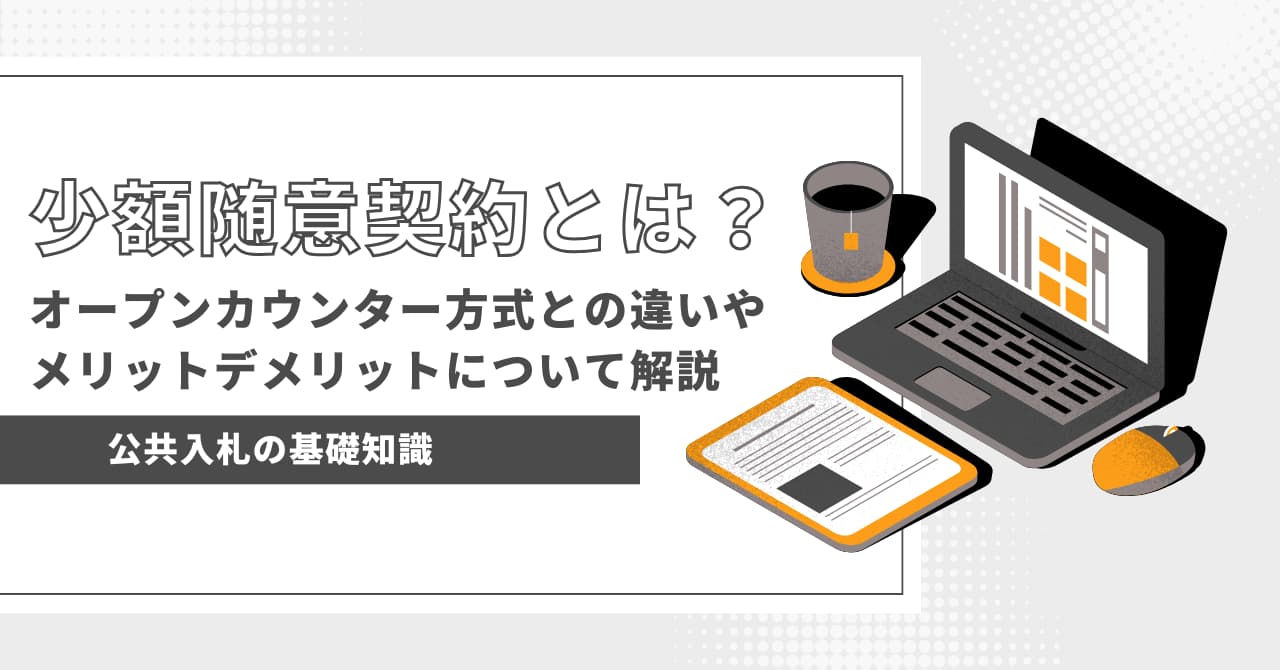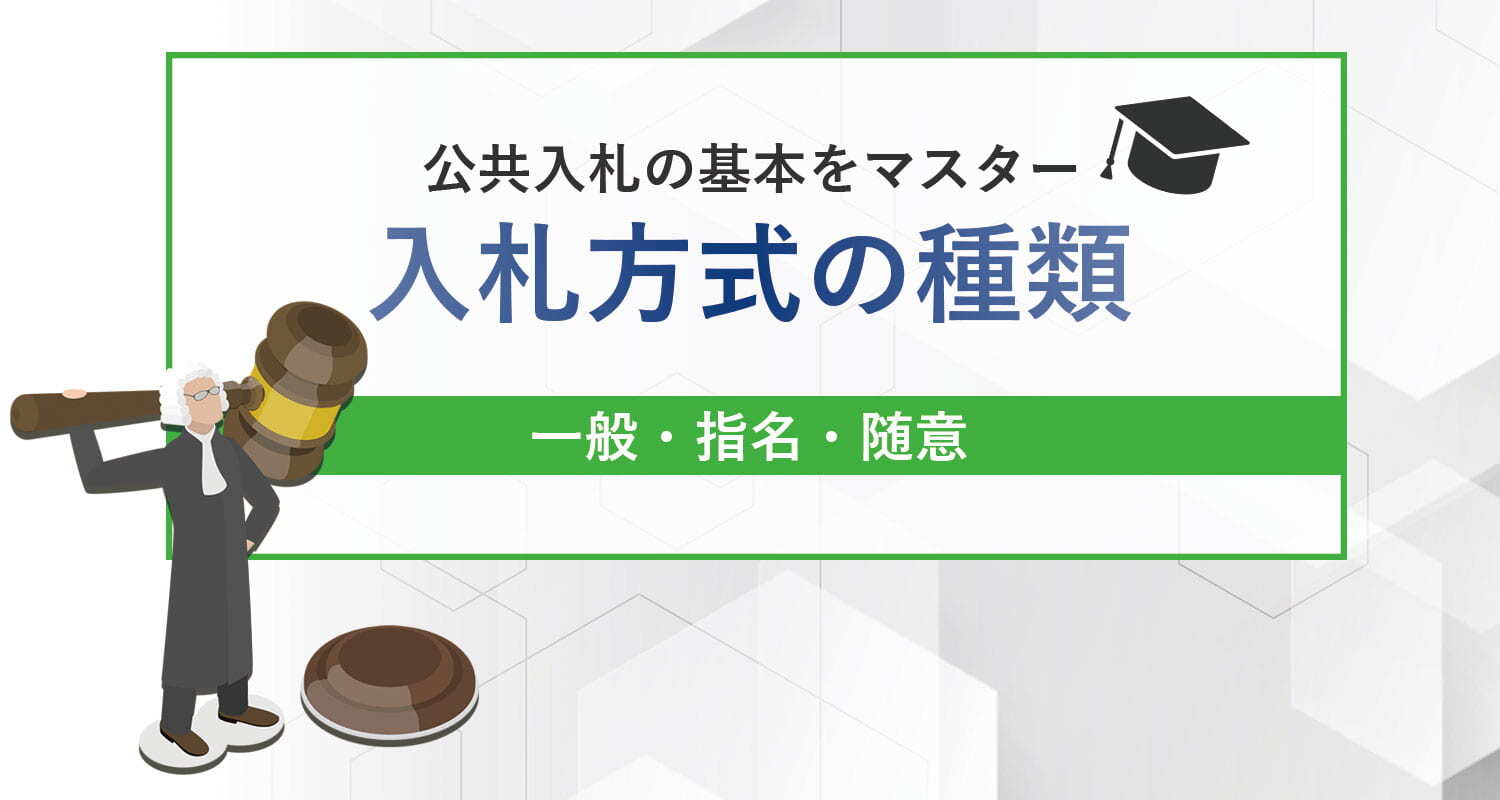- 特命発注(特命随意契約)は特定の相手を指名して契約する例外的な方式
- 契約の性質や目的から競争入札が適さない場合に行われる
- 選定の合理的根拠の明確化と、厳格な内部手続きによって透明性が確保される
特命発注は、府省庁や地方自治体が行う契約方式のひとつで、契約の目的や性質から競争入札が成立せず、相手方を特定の一者に絞って契約する場合に用いられる随意契約です。いわゆる「特命随意契約」と呼ばれるもので、特殊性・緊急性の高い案件や、他の事業者では代替がきかないサービス・製品を調達する際に採用されます。
この記事では、特命発注の基本的な仕組みや法的根拠、入札方式との違い、調達の流れを解説します。さらに、事業者が官公庁から特命発注を受注するために取り組むべきポイントも紹介し、競争性のある入札案件とあわせた営業戦略のヒントを提供します。
もくじ
特命発注とは?
特命発注とは、国の省庁や地方自治体が行う契約方式の一つである「随意契約」のうち、契約の目的物や役務の性質から競争に適さず、取引相手が一者に特定される場合に実施される契約を指します。
特命発注という呼び方は会計法や地方自治法に規定された呼び方ではなく、主に建設工事関係で使われることが多い俗称です。特命発注は、「特命随意契約」とも呼ばれます。
特命発注などの随意契約は発注者が「特定の相手先を指名して発注する」性質があるため、実施する場合は相応の理由が必要とされています。
例えば、緊急性や高度な専門性が求められる案件、または代替性のない技術・製品・役務を調達する場合です。発注者が導入済みの特定システムの保守契約を継続するケースや、特許権を有するメーカーのみが提供できる装置の調達などが典型例です。
このように、特命発注は例外的な契約方式ではありますが、適正に運用されれば公共サービスの継続性や品質確保に寄与する重要な手段です。
特命発注として調達を行う理由
国の省庁や地方自治体の調達は、公平性・透明性・効率性の観点から一般競争入札によることが原則です。
しかし、一入札の実施には所定の期間を確保したうえで手続きを実施する必要があります。災害復旧等の緊急時や、当該案件の調達先が1者に限定される場合においても、期間をかけて一般競争入札手続きを実施することはかえって非効率になってしまいます。
こうした場合を想定して、国及び地方自治体の契約方式には、特命発注などの随意契約が用意されています。
特命発注が用いられるのは、法令で定める随意契約の要件に該当する場合です。
国の契約では会計法および予算決算及び会計令(予決令)、地方公共団体の契約では地方自治法施行令に随意契約の根拠と要件が規定されています。
とくに実務で重要なのが、「契約の性質又は目的が競争を許さない(一般競争入札に適さない)」場合という要件です。
国の法的根拠
国の省庁が随意契約により契約できる場合は、会計法第29条の3第4項に規定されています。
会計法 第二十九条の三
④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
地方公共団体の法的根拠
地方公共団体が随意契約により契約できる場合は、地方自治法167条の2に規定されています。
このうち、「特命発注」を規定しているのは、同条第1項第6号です。
地方自治法施行令
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
なぜ「競争を許さない」事由が生じるのか
契約の性質や目的が競争を許さない事由として典型的なのは、まず代替がきかない技術や権利が関係するケースです。
たとえば、特定の特許や専有技術、ソースコードを保有する事業者のみが履行可能な業務では、競争入札を行っても実質的に一者しか応札できない状況になります。
また、既存設備やシステムとの適合性や継続性を確保する必要がある場合も、供給者を限定せざるを得ません。既設システムの保守契約や同一メーカー部材の追加調達などは、品質や安全性を担保するために同一事業者への発注が合理的です。
特命発注と入札との違い
特命発注は、複数社が同条件で競えることを前提とする入札と異なり、そもそも競争の前提が成り立たない案件を対象とします。既設システムの保守や特許・専有技術に基づく製品・役務など、代替が困難な場合に限って、発注者が特定の相手方と直接契約します。
競争性・透明性の確保手段も異なります。入札は公告等により広く参加機会を与え、価格や技術提案で比較します。
一方の特命発注は競争を伴わないため、理由書の作成、見積徴取による価格妥当性の確認、承認手続の厳格化、随意契約案件の公表といった内部統制で透明性を担保します。
競争が働きにくい分、これらの手続きを適正に運用することが不可欠です。
手続の流れも対照的です。入札は公告・応札・開札・落札者決定という公開性の高いプロセスで進みますが、特命発注は発注者と事業者間で直接やり取りを行う非競争的プロセスが中心です。
したがって発注者には、契約価格と相手方選定の合理的根拠を明確化する説明責任が求められます。
特命発注の流れ
特命発注は、競争入札の場合と比較して契約に至るまで手続きに違いがあります。
以下に一般的な流れを解説します。
参考見積書の徴取
随意契約に先立ち、発注機関から参考見積書の提出を依頼されることがあります。
発注者は調達を随意契約で実施するに先立ち、当該調達の予定価格を決定しなければなりません。予定価格は、調達(購入)価格の上限額と考えておくと良いでしょう。
発注者が予定価格を算定する方法は様々ですが、一つの手法として、事業者から市場調査を目的とした参考見積書を徴取して当該見積額を参考に決定する方法があります。
こうしたことから、参考見積書の提出を依頼される場合があるのです。
また、特命発注を想定した参考見積書の依頼時には、仕様書案のほか事業者側の実施体制・実績等に関する参考資料の提出を依頼される場合があります。
見積書のほか、各種資料を参考に随意契約の相手方として必要な要件を満たしているか確認をするためです。
そのため、参考見積書の提出依頼には、前向きに対応することがおすすめです。
発注者による契約方式の決定・事業者選定
発注者側の手続きですが、契約方式を随意契約で実施すること、調達の予定価格、契約の相手方となる事業者について、発注者の規定に基づく方法で決裁手続きを行います。
特命発注の場合は、法令にある「競争入札に付することが不利と認められるとき」になぜ該当するのか、契約の相手方事業者がなぜ当該事業者に限定されるのか等について理由を記載した文書とともに決裁を受けることになります。
見積書徴取
発注者で契約方式等の意思決定(決裁)がされると、契約に向けた手続きに移ります。
まず、発注者から正式な見積書の提出依頼があります。依頼時には、業務仕様書なども併せて示されます。
この見積書の提出は、一般競争入札でいう「入札書の提出」に相当します。提出した見積額が発注者の定めた予定価格の範囲内であれば、基本的見積額が契約額になります。
特に特命発注の場合、他社との競争がありませんので、発注者も当該見積額の妥当性を丁寧に確認することが求められています。そのため、詳細な見積内訳の提出が求められることを想定しておくとスムーズです。
また、見積書を提出後、発注者から価格交渉される場合もあります。出精値引きの程度については、必要な工数等を鑑みて対応を検討しましょう。
なお、価格交渉を経て初回の見積額から大幅に値引きすることは、見積額そのものに対する信ぴょう性が疑われることに繋がりかねません。
競争が働かないからといって不誠実な見積額を提示することは避け、誠実な対応をすることで継続的な取引につなげることが有効です。
契約
提出した見積書の見積額が予定価格の範囲内であり、見積内容についても妥当と判断された場合は契約書の締結に移行します。
特命発注により官公庁案件を受注する方法
特命発注は競争を伴わない契約方式です。そのため、一般競争入札での受注のように「入札公告をくまなくチェックして積極的に入札参加する」といった方法は行えません。
特命発注の相手方として選定される、以下のような取り組みが重要です。
入札参加資格を取得する
特命発注は随意契約であるため、入札参加に必要な入札参加資格の取得は必須ではないものの、全省庁統一資格や各自治体の入札参加資格を保有していると、発注者側の内部手続が円滑になります。
資格審査で確認される財務基盤・納税状況・業務実績を整えておくことで、「随意契約の相手方としての妥当性」を裏づけが得られ、結果として参考見積の打診や仕様協議に進みやすくなります。
サービスの独自性を確立する(知財・技術・ノウハウ・地域特化)
特命発注の根拠は、多くの場合代替困難性です。
特許・著作権・商標・営業秘密の保護状況、独自設備、有資格者の配置、地域限定の供給網などを整理し、第三者が確認できる形で公開しておくことが有効です。
例えば、既設システムの保守・拡張であれば、互換性証明(準拠規格・インターフェース仕様・試験結果)や切替時のリスク評価(停止時間・移行コスト)を併せて示すと、特命理由の説得力が高まります。
客観的な実績を蓄積する(性能・品質・継続性)
発注担当者が特命発注の相手方として選定する際、他の事業者ではなく当該事業者ではなければ調達目的が達成できない理由を説明することが求められます。
その際に有効なのは、定量データで比較できる材料があることです。
性能、品質、実績などのデータを日ごろから収集・整理しておくことで、発注者から求められたときに必要な資料を提供することができます。
情報発信を継続する
特命発注理由に直結する事項(互換性、知財、セキュリティ、可用性、地域即応など)を記載したホワイトペーパー、技術ブログ、導入事例等をホームページ等で公開し、検索で到達できる形にしておくと、発注機関の担当者が決裁の添付資料として利用することが可能になります。
また、予め情報をオープンにしておくことで、問い合わせから契約までの時間短縮に寄与します。
まとめ
特命発注(特命随意契約)は、競争が成立しない合理的な理由がある場合に選択される契約方式です。
入札とは前提が異なりますが、受注者側に求められる本質は共通しています。一般競争入札や指名競争入札とは違い価格優位性を直接比較されることはありませんが、発注者が求める業務を履行できる体制を確保していることが必要な点は同様に重要です。
併せて、入札参加資格の整備、独自性(知財・技術・互換性・地域即応)の可視化、稟議で使える実績等の数値化、継続的な情報発信と関係構築が、受注可能性を高めます。
さらに留意すべきは、特命発注は原則として公示されない点です。
そのため、案件を待つのではなく、実績の蓄積・独自性の構築・発注者との関係構築を平時から進めておくことが成果につながります。
一方で、国の省庁や地方自治体の案件を安定的に獲得するには、特命以外の公示案件(一般競争入札・指名競争入札・公募型プロポーザル等)への参入が不可欠です。
公示案件での実績が増えるほど、将来の特命の説得力(継続性・互換性・品質評価)も高まります。
こうした公示案件のリサーチにおすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。
NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。これまでのように発注者ごとに分かれた入札システムにアクセスする手間を削減できます。
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上