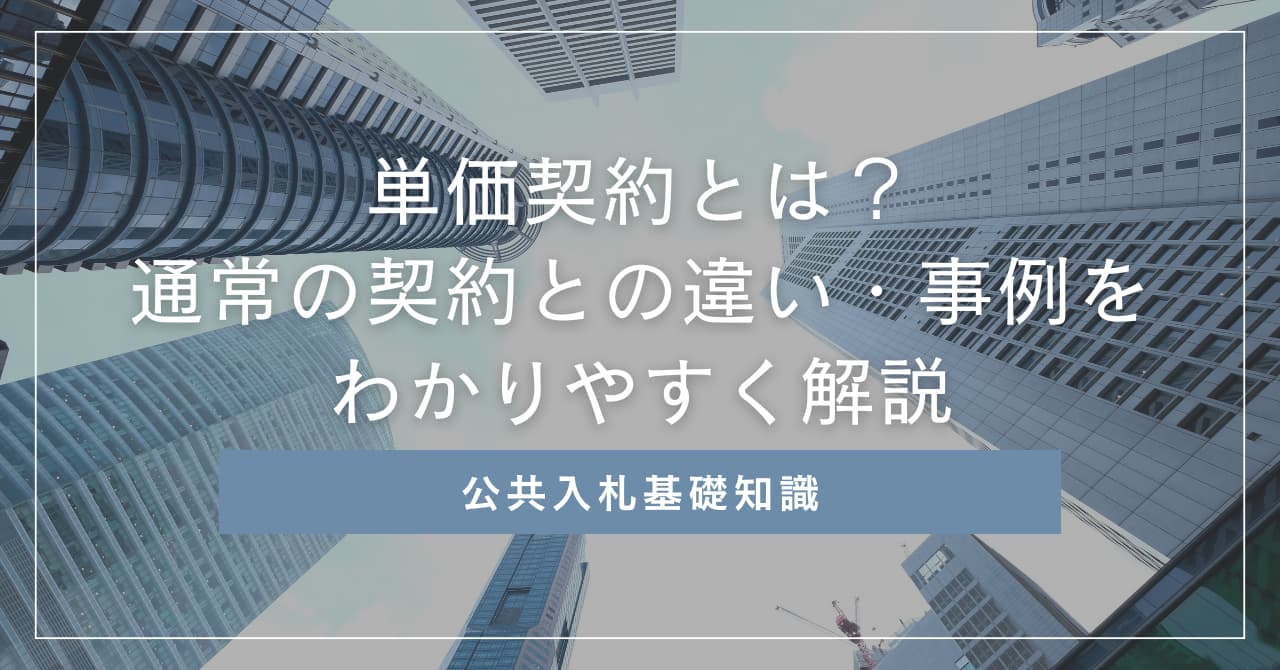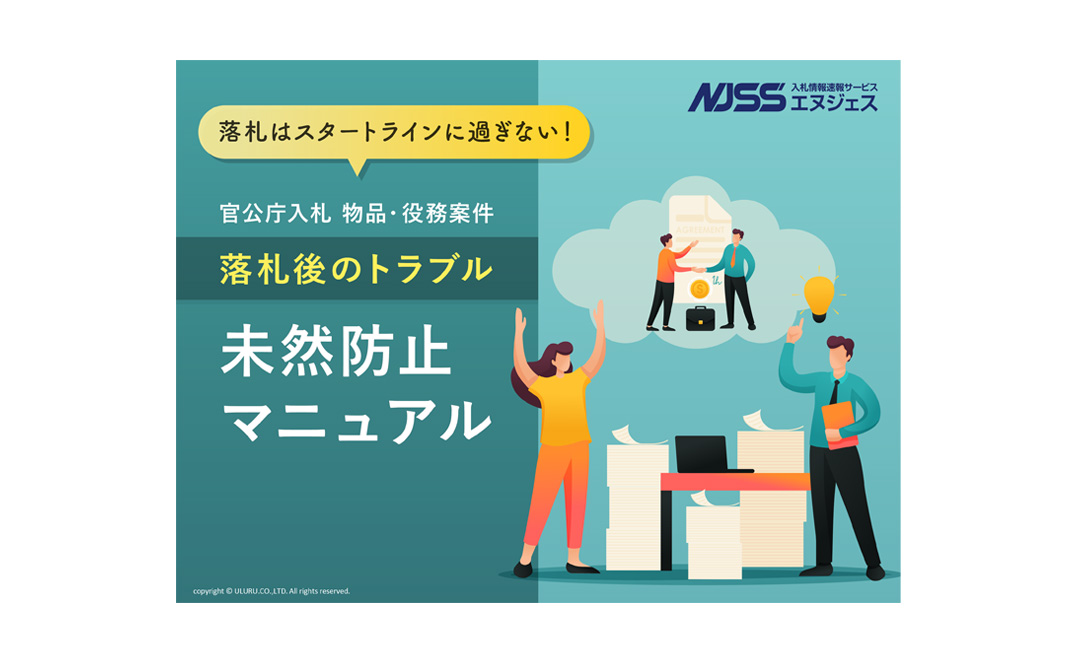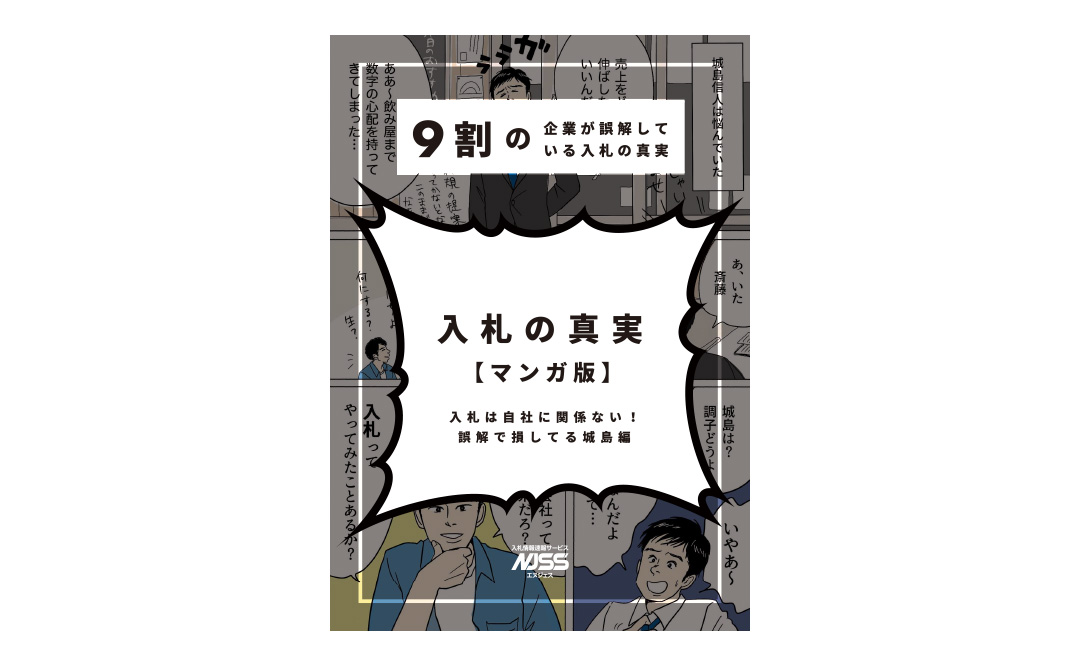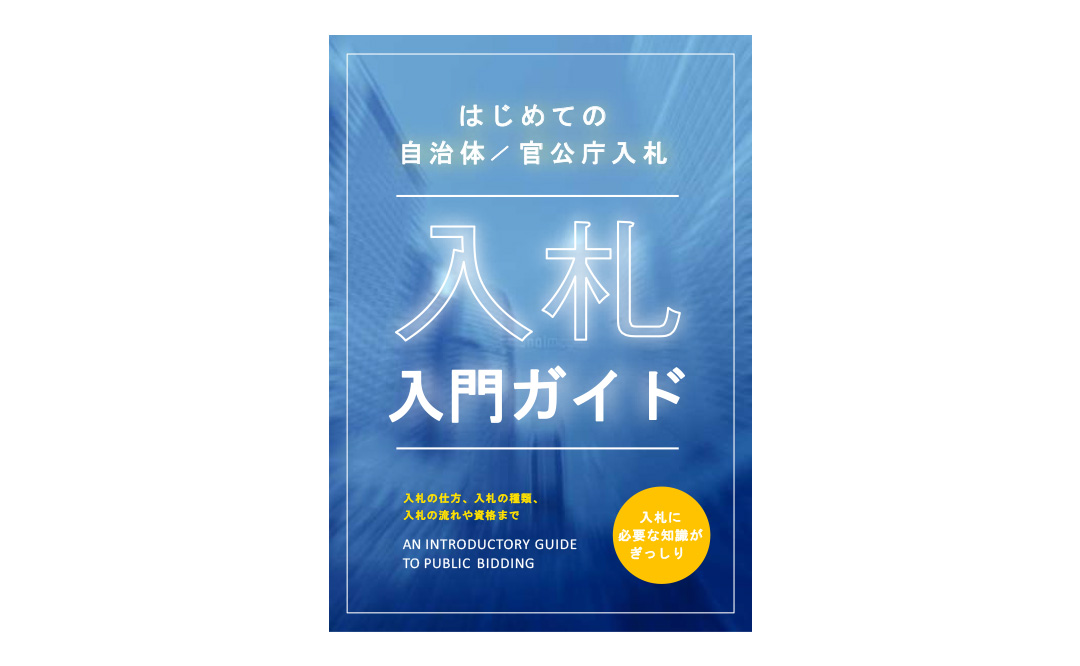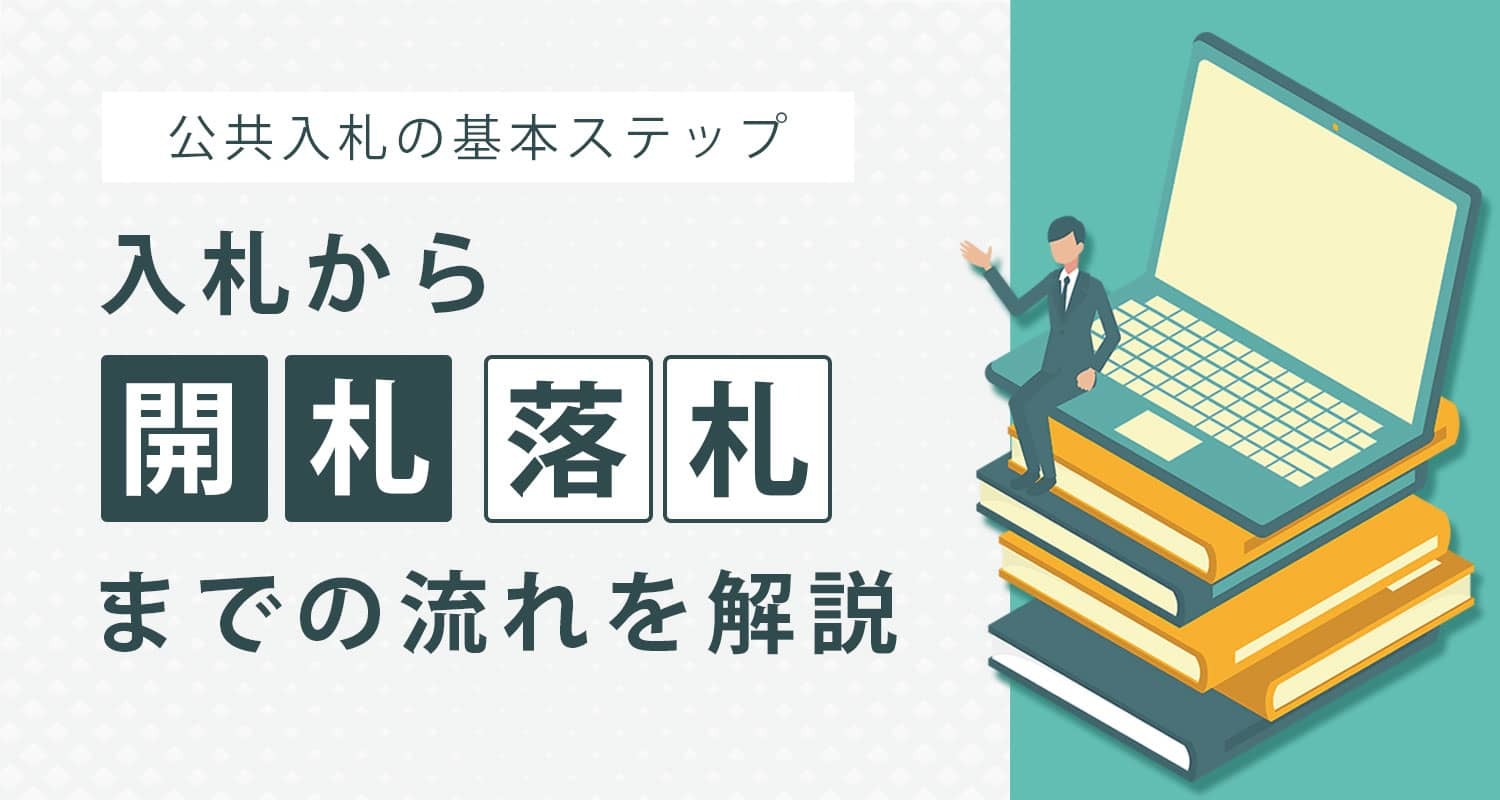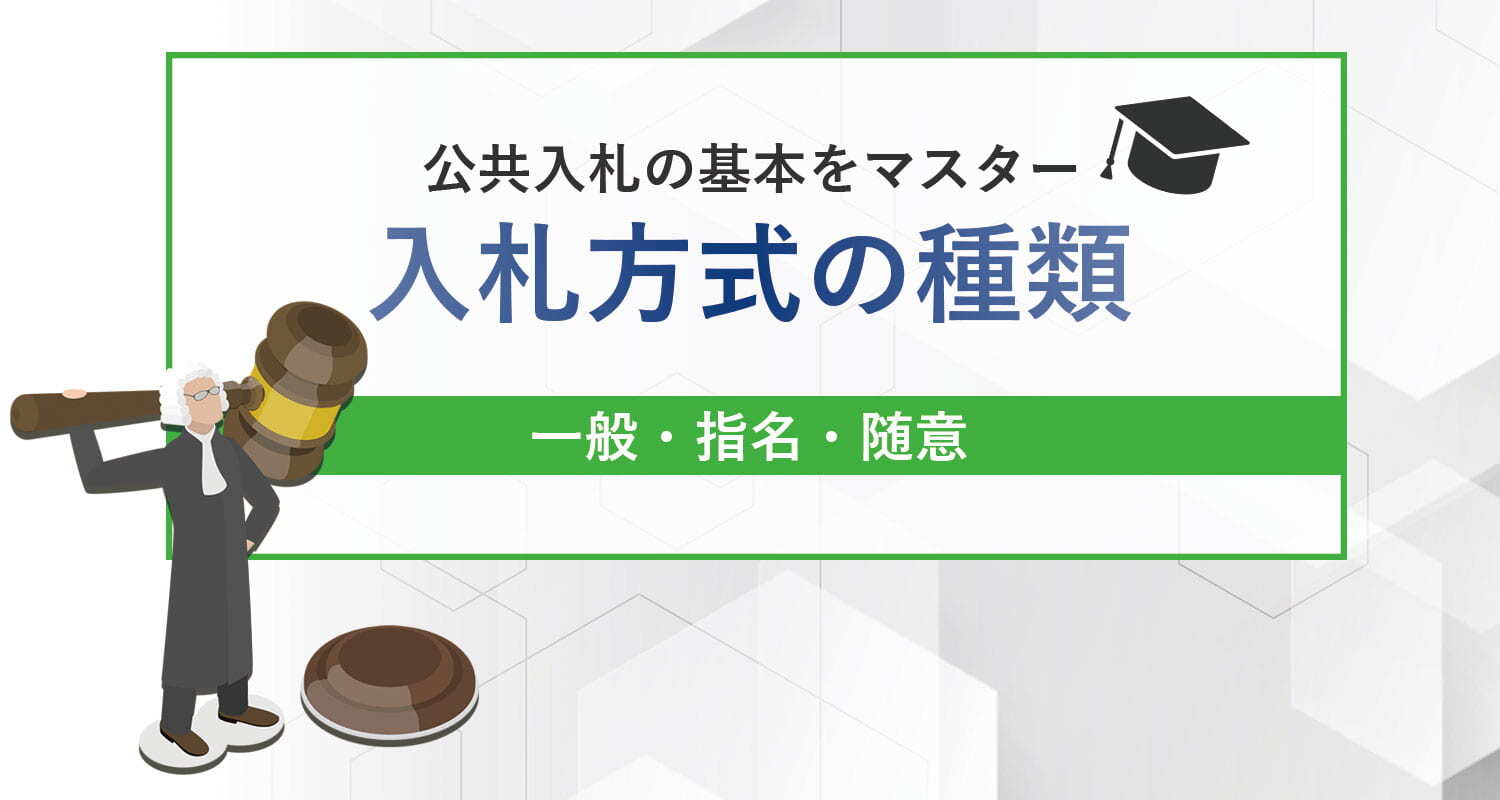- 単価契約とは業務量や調達数量が未確定な場合に、単価と契約条件のみを取り決める契約方式
- 総価契約が契約時点で総額を固定するのに対し、単価契約は柔軟性が高い
- 道路補修、除雪、燃料調達など、発生量が変動しやすい業務に広く活用される
単価契約は、契約締結時に業務量や調達数量を確定できない場合に活用される契約方式です。あらかじめ単価と契約条件だけを取り決めておき、発注の都度確定する数量に応じて精算する仕組みのため、道路補修や除雪、燃料調達など、発生量が変動しやすい業務で広く利用されています。
この記事では、単価契約の基本的な仕組み、総価契約との違い、法的根拠や効力、具体的に活用される案件の例、業務の流れ、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
単価契約とは
単価契約とは、業務の数量が確定できない場合に「単価」だけをあらかじめ取り決める契約方式です。
例えば、道路・河川・公園の維持管理業務、検査試薬や消耗品の調達など、年度内に発生する作業量や発注数量を正確に見積もれない場合に用いられます。
この契約方式では、契約時点で定めるのは「単価」と契約条件のみであり、実際の発注量は案件ごとに発注者から都度指示されます。発注のたびに数量や金額が確定し、その積み上げで契約金額の総額が決まります。
そのため、契約締結時に金額が確定する総価契約と比べ、柔軟性が高いのが特徴です。
単価契約は、年度中に業務量が変動する可能性が高い調達に適しています。発注者にとっては実際に必要な数量に応じて柔軟に業務を依頼でき、予測困難性を理由に過大な数量を発注すること避けることができます。
このように、単価契約は変動性の高い調達に適応するための仕組みとして、官公庁や自治体で幅広く活用されています。
単価契約と総価契約の違い
契約時点で確定する要素
単価契約では、品目や作業区分ごとの単価、適用条件、契約期間、上限額(または予定数量の上限)をあらかじめ取り決めます。一方で数量と総額は未確定のままです。
これに対して総価契約は、仕様・数量・納期・対価(総額)を契約締結時に確定します。設計変更など特段の事情がない限り、金額は原則として動きません。
金額確定と支払のタイミング
単価契約では、発注の都度「数量×単価」で金額が確定し、検収後に請求します。月次や四半期でまとめて請求する運用もよく見られます。
総価契約は、締結時に総額が決まっており、出来高払・部分払・一括払など契約で定めた支払条件に沿って精算します。
運用面の違い(発注・検収・変更)
単価契約は必要なとき、または定期的に必要な分だけを発注が出る契約形態です。
受注者は個々の指示に基づいて作業・納品し、作業報告や写真、計量票などで出来高を確認して検収を受けます。数量が増減しても、上限額や期間を超えない限り契約変更は不要です。
総価契約は、原契約の範囲で履行し、仕様や数量を動かす場合は原則として変更契約の手続きを伴います。検収は工事完成、物品の一括納入、役務完了といった区切りで行われます
単価契約の法的根拠・効力
国の根拠(予算決算及び会計令第80条)
単価契約は、国の会計ルールである予算決算及び会計令(予決令)第80条に基づきます。
同条は、予定価格は原則「総額」で定める一方、継続して行う給付で数量の事前確定が難しい場合には「単価」で定めることができる旨を定めています。
つまり、年間の発生量が読みにくい調達について、単価ベースの契約が許容されています。
地方公共団体の運用(各自治体の財務規則・要領)
地方公共団体では、各自治体の財務規則や契約事務取扱要領などで、単価契約の定義や手続きを具体化しています。
一般に、あらかじめ単価と有効期間・上限額(または上限数量)を定め、実績数量×単価で精算する方式として整理されており、公告・見積・検収の運用もあわせて規定されています。
債権債務が発生するタイミング
単価契約は、契約を結んだ時点では債権債務が発生しません。
発注者が発注書・注文書等で都度発注を行い、その数量が確定した段階で、初めて債権債務が発生します。
実務上は、発注単位で作業実績や納品の検収を行い、検収済み分について請求する運用となります。
なお、上限額・上限数量を超える場合や期間を延長する場合は、契約変更の手続きが必要になります。
単価契約が利用されることがある案件の例
建設工事
道路管理(舗装修繕、道路施設〔照明・標識・防護柵等〕修繕、雑草刈払い、除雪、側溝清掃 など)
道路は天候・交通量・季節要因で損傷や発生量が変動します。たとえば凍結や豪雨後は補修箇所が一時的に増え、冬季は降雪量に応じて出動回数が大きく変わります。
作業発生の都度、数量×単価で精算できる単価契約であれば、過不足のない支出と迅速な手配が可能です。
河川管理(堆積土砂等処分、水質事故対策工)
出水状況や事故発生は予測が難しく、必要な土砂処分量や緊急対応の工数が一定しません。
単価契約により、発生量や対応規模に応じて速やかに発注でき、余剰の見込み発注を避けられます。
公園管理(植栽・樹木剪定、除雪、雑草刈払い)
植物の生育や気象条件により作業頻度が変動します。
剪定本数や刈取り面積、除雪出動回数は季節差が大きく、年度当初に総量を確定しにくいため、実績数量に応じて精算する単価契約が適しています。
物品・委託
燃料(灯油など)
需要は外気温や稼働状況に左右され、月ごとの使用量が変動します。価格も市況に連動するため、数量は都度の発注で確定し、単価ベースで精算する方が実務に合致します。
複合機利用・コピー用紙
印刷枚数や用紙消費は業務量で上下し、その事情は各課で異なります。事前に総量を見積もると過不足が生じやすく、クリック単価(枚単価)や用紙単価での精算が効率的です。
必要分だけを都度発注できるため、在庫リスクや無駄な支出を抑制できます。
各種検査業務委託
検体数・対象件数は依頼状況や施策の進捗により変動します。件数に応じた単価設定をしておけば、繁忙期・閑散期の振れに柔軟に対応でき、固定総額契約よりも実態に沿った支払いが可能です。
検査用試薬等
有効期限や保管条件の制約があり、まとめ買いによる廃棄リスクが生じます。都度必要量を発注し、単価で精算することで、品質維持とコスト最適化を両立できます。
単価契約による業務の流れ
単価契約の実務は、案件の性質に応じて入札または随意契約で相手方が決まり、その後は個別の発注ごとに数量と金額が確定していきます。ここでは、一連の流れを整理します。
入札・随意契約等
はじめに、発注者は所定の手続により相手方を選定します。
入札の場合は公告・応札・開札を経て落札者が決まり、随意契約の場合は要件に基づく相手方選定と見積協議が行われます。
受注者は、仕様の範囲、適用単価、上限額(または上限数量)、契約期間、検収方法などの条件を確認し、疑義があれば質疑・協議の段階で解消しておきます。
契約締結
契約書(または注文契約の基本合意)で、単価・適用条件・期間・上限額(数量)・検収基準・支払条件・変更手続などを確定します。
単価契約は、この段階では総額が決まりません。のちの個別発注で数量が確定し、その都度「数量×単価」により金額が決まるのが前提です。
発注連絡の受信
契約締結後、必要なタイミングで発注者から案件ごとの発注書・注文書・出動依頼等が届きます。ここで数量、作業場所・日時、納期、必要資機材などの具体条件が示されます。
受注者は、契約条件への適合、手配可能性、価格算定の根拠(数量×単価、割増・加算の有無)を確認し、必要に応じて発注者と条件をすり合わせます。
納品(履行・作業完了)
発注内容に沿って作業・納品を行い、契約で定められた検収資料(作業報告書、写真、計量票、出動記録、受入検査票等)を整えます。
検収は発注単位で行われるのが一般的で、数量・品質・期日が満たされているかが確認されます。
請求
検収完了分について、発注単位または月次・四半期の取りまとめで請求書を発行します。請求及び支払時期は契約書で定められていることが一般的です。
請求金額は基本的に「確定数量×契約単価」で算定し、割増・減額、交通費等の扱いが契約に定められている場合は、その規定に従って整理します。
添付資料(検収書、納品書、内訳書など)は、契約書や発注者の財務規則・要領等に合わせて準備します。
単価契約のメリット・デメリット
単価契約のメリット
単価契約は、年度単位で契約期間が設定されるケースが多く、発注の都度に個別契約を結び直す必要がありません。結果として、同一年度内に継続的な発注が見込まれ、発注者の運用や品質基準に合わせた体制づくりが進めやすくなります。
やり取りの蓄積により、段取りや検収要件の理解が深まり、関係構築にもつながります。
また、発注は小口・反復取引が中心となるため、初期投資が大きくない業務から参入しやすいのが特徴です。中小事業者でも、限られたリソースで対応範囲を拡大しやすく、実績を段階的に積み上げられます。
需要変動に応じて出動・納入量を調整できるため、過剰な在庫や遊休人員のリスクを抑えつつ運用できます。
単価契約のデメリット
一方で、発注量は年度内で変動するため、売上総額の見通しを立てにくい点は避けられません。
収益計画を組む際は、過去の需要実績や季節要因、上限額・上限数量の消化ペースを踏まえ、複数シナリオで試算しておくことが求められます。
また、汎用品や一般的な作業区分では、入札で単価の競争が激しくなりがちです。
さらに、実務では発注書の内容確認、作業・納入実績の記録、検収書類の整備、請求書の作成・突合といった事務負担が総価契約と比較して大きいです。
テンプレート化やシステム化により、証憑の精度と処理速度を確保する体制づくりが重要です。
まとめ
単価契約は、数量の確定が難しい調達に適した契約方式で、あらかじめ「単価」と条件を定め、個別の発注ごとに数量と金額を確定して精算します。
総価契約との違いは、契約時点で総額を固定しない点と、発注・検収・請求を発注単位で積み上げる運用にあります。
実務面では、継続発注や関係構築のメリットがある一方、売上予測の難しさや価格競争、事務負担増といったデメリットへの備えが欠かせません。
単価契約であっても契約の相手方の選定は、総価契約と同様に一般競争入札・指名競争入札・随意契約のいずれかによって行われます。そのため、単価契約の案件獲得を目指す場合は、発注機関ごとに分散する公告を効率よく収集し、条件に合う案件をタイムリーに把握する体制づくりが有効です。
こうした入札情報のリサーチにおすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。これまでのように発注者ごとに分かれた入札システムにアクセスする手間を削減できます。
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上