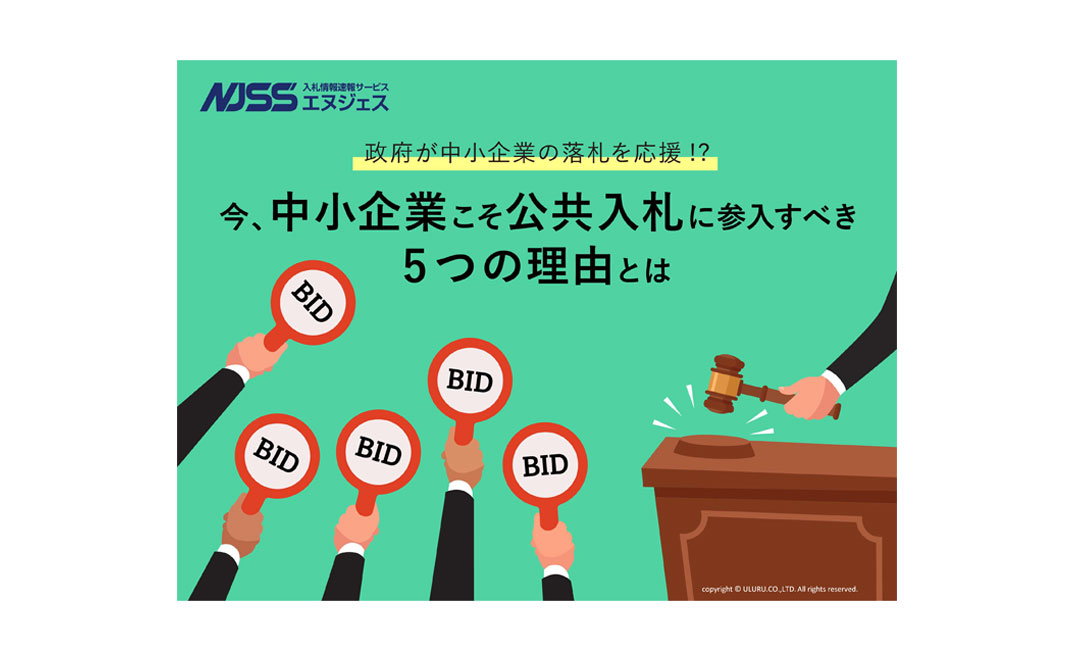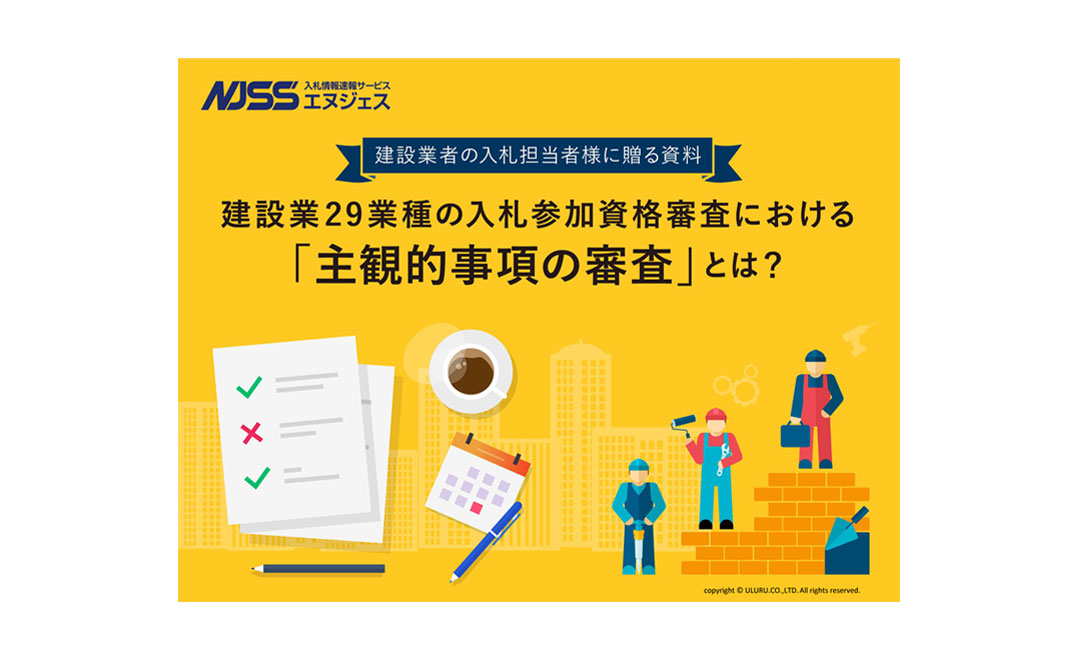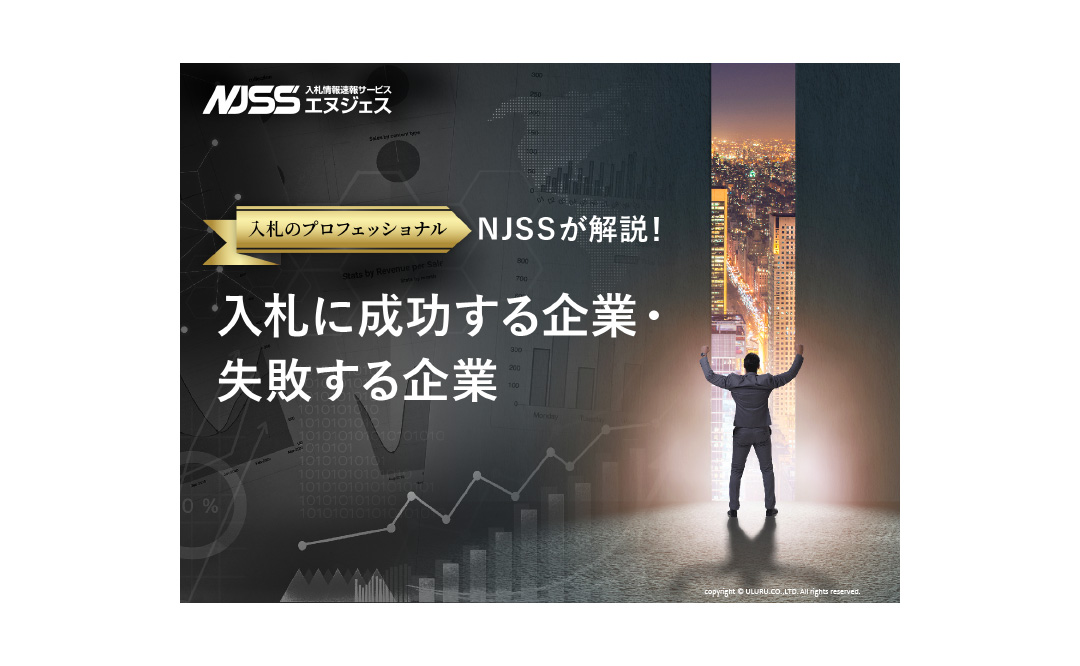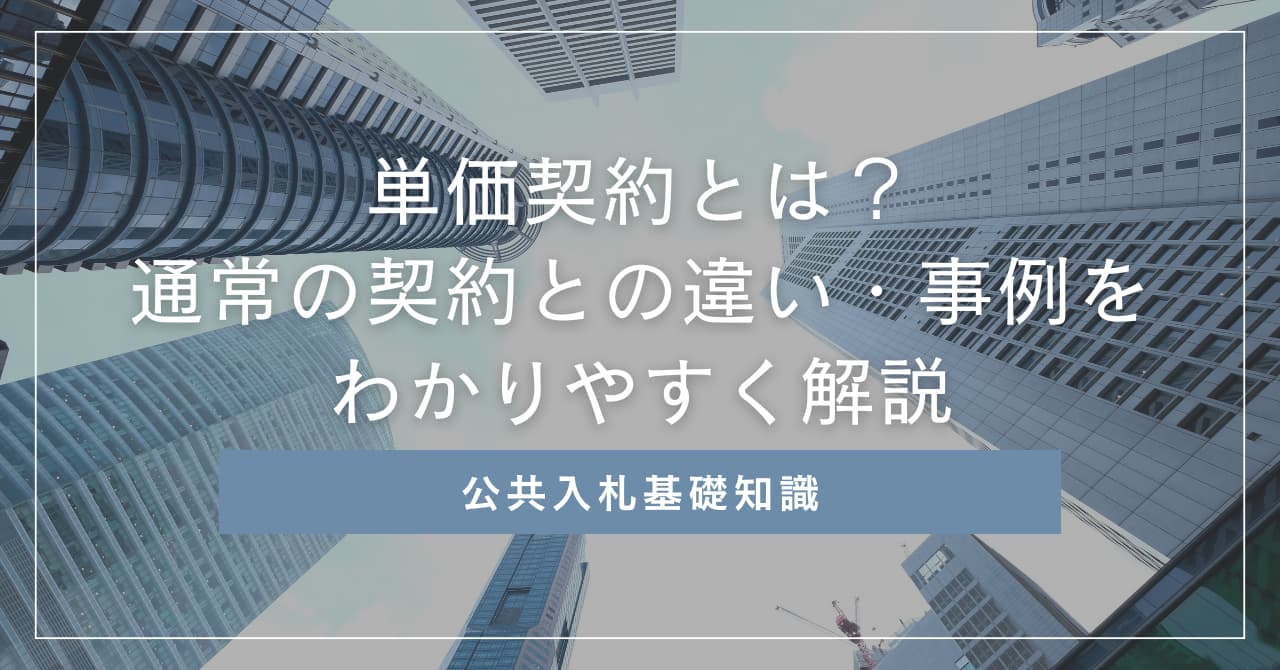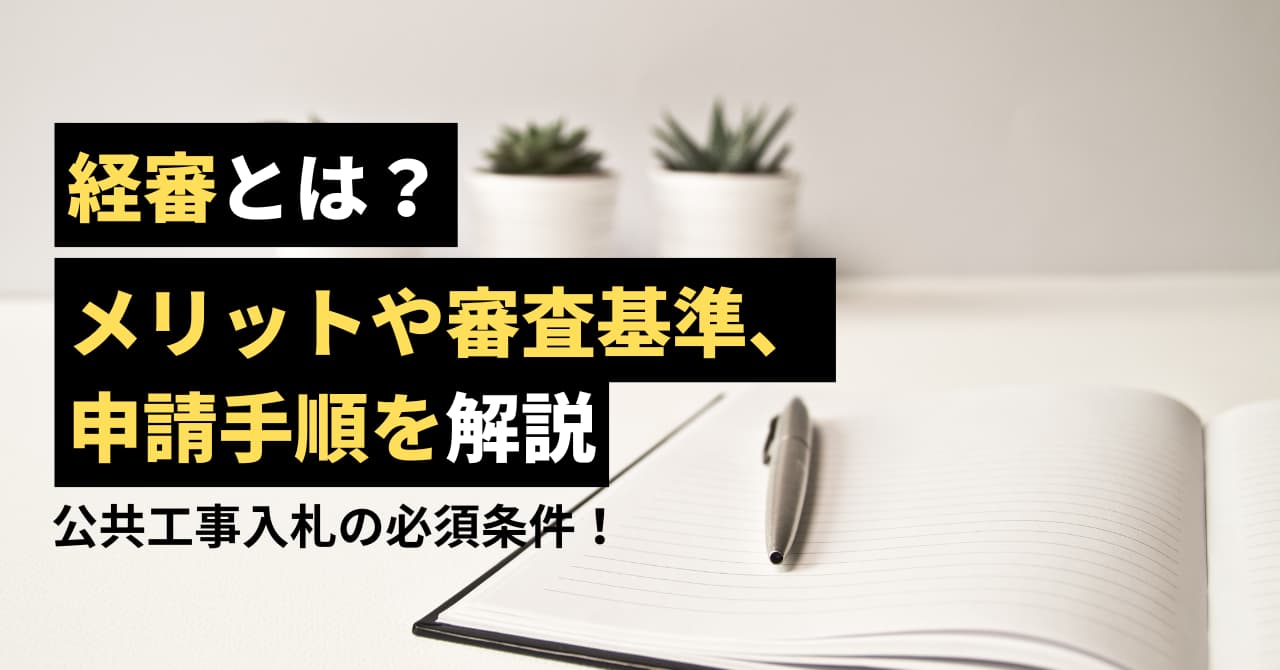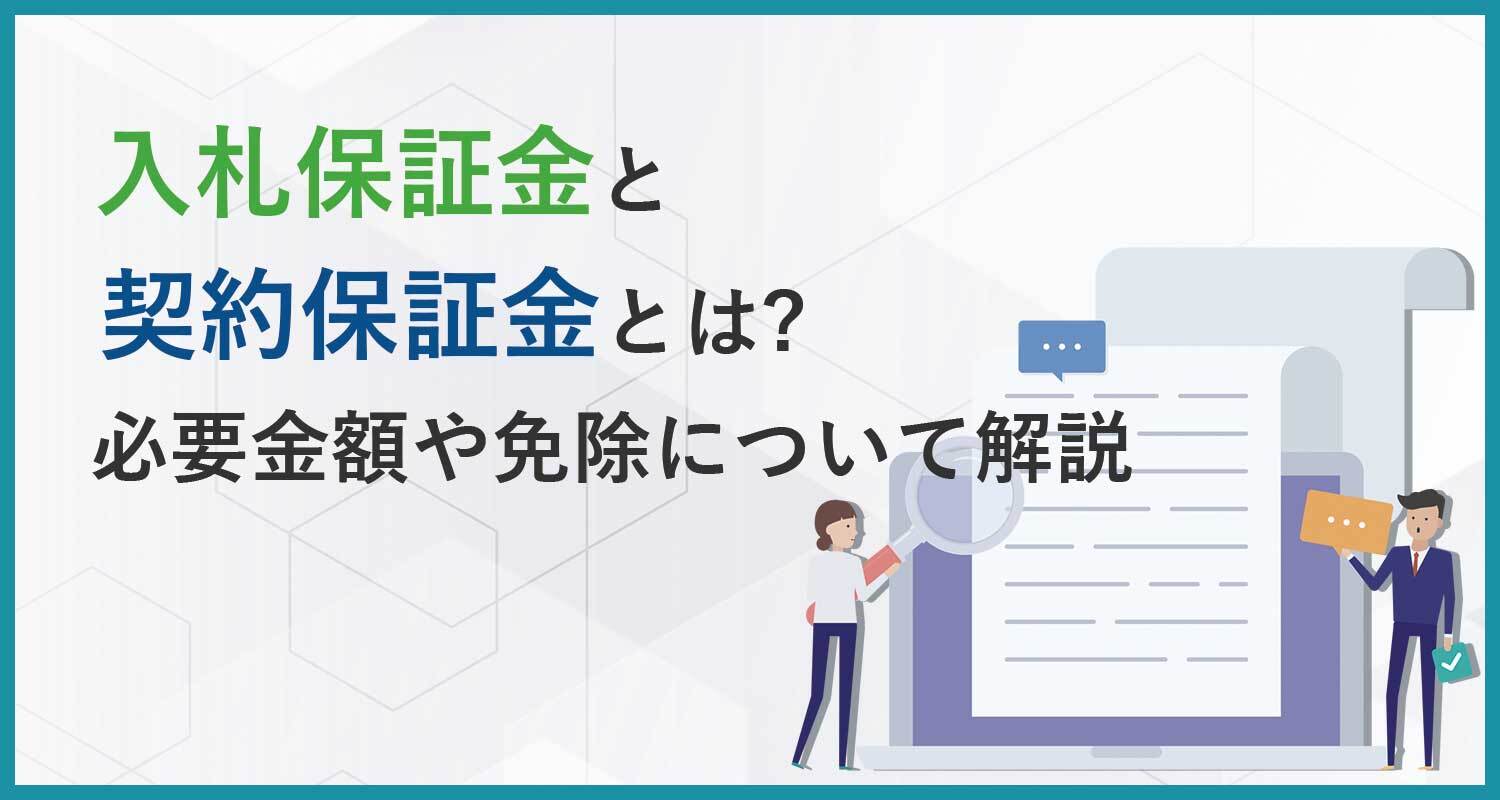- 労務単価とは、公共工事の設計金額を算出する際に用いられる、作業員1人あたり1日分の標準的な人件費相当額
- 国土交通省が毎年調査に基づき公表し、職種ごと・地域ごとに細かく設定される
- 発注者が定める予定価格の積算根拠となるため、受注者側も最新の単価を正しく把握することが不可欠
「労務単価」とは、国土交通省が毎年公表する公共工事設計労務単価のことです。公共工事の積算で、作業員1人あたりの1日分の標準的な人件費を示す基準であり、発注者の予定価格や受注者の見積額を算出する際の重要な指標となります。
この記事では、労務単価の仕組みや決まり方、改定の背景、そして見積り・積算における活用方法をわかりやすく解説します。ぜひ、採算性の高い入札・契約を実現するための参考にしてください。
もくじ
労務単価とは
「労務単価」とは、公共工事で設計金額を算出する際に用いられる作業員1人あたり1日分(8時間当たり)の人件費相当額をいいます。正式には「公共工事設計労務単価」と呼ばれ、国土交通省が毎年度「公共事業労務費調査」の結果をもとに公表しています。
この労務単価は、建設業で働く技能労働者の市場実勢賃金を基礎として算出された標準的な単価です。公共工事における予定価格や設計金額を積算する際の基準となるもので、実際の給与額や企業が支払う賃金そのものではありません。
単価には、基本給相当額(個人負担の法定福利費を含む)、諸手当、臨時の給与(賞与等)、実物給与(食事等)が含まれます。
一方で、事業主負担の法定福利費、労務管理費、安全管理費、時間外割増賃金などは含まれません。
したがって、労務単価は日給制の労働者が受け取る日当よりも広い概念です。また、労務単価には事業主負担の法定福利費等が含まれませんので、事業主が労働者一人を雇用するためには必要な経費とも異なります。
労務単価は職種ごとに設定されており、たとえば「土工」「型枠工」「電工」「とび工」など、それぞれ異なる単価が適用されます。地域による差もあり、都道府県単位で公表されるほか、離島などでは地域補正(係数)が設けられています。
このように、労務単価は全国一律ではなく、地域と職種の組み合わせによって細かく設定された「実勢を反映した基準値」です。毎年の改定を通じて、賃金動向や人手不足の影響が反映されるため、建設業者が公共工事の積算・見積りを行う際には、最新の労務単価を把握しておくことが不可欠です。
なぜ労務単価を理解することが重要なのか
労務単価は、建設業者が公共工事を受注するうえで、積算・見積り・契約すべての段階に影響を及ぼす基礎的な指標です。
この単価の意味や改定動向を正しく理解していないと、見積り金額の妥当性を判断できず、採算管理にも支障を来します。
入札・積算の基礎となる共通基準だから
国や自治体が工事費を積算する際、設計金額のうち「労務費」の部分は、最新の公共工事設計労務単価をもとに算出されます。
そのため、同じ業務仕様でも労務単価が上昇すれば、予定価格も上昇することになります。
したがって、仕様から発注者が定めた予定価格を想定する場合、労務単価を把握していることが必須と言えます。
また、労務単価の改定には、技能者の処遇改善や人材確保などの政策的背景があります。
単なるコスト上昇ではなく、「建設現場の持続可能性を守るための調整」でもあるため、
その意味を理解することは、今後の業界動向を読み取るうえでも重要です。
最新単価を把握しないと採算リスクを招くから
労務単価を把握していない場合、その改定方向によって異なるリスクが生じます。
例えば、単価が上昇している局面では、発注者の予定価格も上昇傾向にあるため、旧単価を前提に見積もると予定価格よりも低く見積もりすぎて利益を取り損ねるおそれがあります。
一方、単価が下落している場合には、発注者の予定価格も下がるため、古い高単価を基に見積もると、他社より入札価格が高くなり競争上不利になる可能性があります。
いずれの場合も、最新の単価動向を把握していないことが、
適正な入札価格の設定を難しくし、採算や落札確率に影響を与える要因となります。
労務単価の決まり方と制度の仕組み
公共工事設計労務単価は、国土交通省が毎年実施する「公共事業労務費調査」の結果に基づいて算出されます。
この調査では、全国の建設現場で実際に支払われている賃金(市場実勢賃金)を把握し、
その平均的な水準をもとに、各職種・地域ごとの標準的な単価を設定します。
公共事業労務費調査とは
この調査は、毎年9〜11月頃に実施され、翌年3月に結果が反映された労務単価が公表されます。
調査対象は、土木・建築・設備など幅広い工種に従事する技能労働者で、事業者から提出された賃金実態(基本給・諸手当・賞与など)をもとに統計的に分析されます。
労務単価はこのデータに社会保険料などの法定福利費(事業主負担分)を加算した日額換算で示されます。
労務単価に含まれる費用・含まれない費用
労務単価には、作業員本人の賃金のほか、通勤手当や手当、事業主が負担する社会保険料などが含まれます。
これにより、技能労働者を1日雇用する際の実質的な人件費が反映されます。
一方で、現場管理費、一般管理費、時間外割増賃金などは含まれていません。
これらは別途「共通仮設費」や「現場経費」として積算される項目です。
したがって、労務単価はあくまで「直接工事費の中の労務費部分」に対応する単価であり、企業経営全体の人件費とは異なる概念です。
職種と地域による違い
労務単価は、技能や職務内容によって大きく異なります。たとえば、「土工」「型枠工」「電工」「配管工」「左官工」など、工種ごとに設定された単価が存在し、作業の難易度や熟練度に応じて水準が変わります。
また、単価は都道府県単位で公表され、地域の賃金水準や物価を反映しています。
地方と都市部では人件費の差があるため、同じ職種でも地域によって単価が異なります。
離島や特定の遠隔地においては、追加的な「地域補正係数」が適用される場合もあります。
労務単価の改定動向
公共工事設計労務単価は毎年、公共事業労務費調査の結果をもとに改定されます。
令和7年(2025年3月適用)改定版では、全国全職種の加重平均値で24,852円(令和6年3月比+6.0%)、主要12職種(公共工事において広く一般的に従事されている職種)では同23,237円(令和6年3月比+5.6%)となりました。
労務単価の全国全職種平均値は平成25年度の改定から13年連続で引き上げとなっています。
平成25年度改定時に単価算出手法が変更され、労働者本人が負担する法定福利費も算入されることになり、以降一貫して労務単価は上昇を続けています。
労務単価の使い方(積算・見積りでの活用)
公共工事の入札参加時に見積りを行う際、まず確認すべきなのが労務単価です。
国や自治体が定める予定価格は、最新の「公共工事設計労務単価」と標準歩掛をもとに積算されています。
したがって、受注者側も該当する都道府県・職種の最新版を活用し、設計書の前提と整合性を取りつつ自社の実勢人件費と比較して見積額を調整・決定していくことが欠かせません。
また、労務単価はあくまで基準値であり、実際の現場では歩掛や作業量に差が生じる場合があります。
過去の施工実績と比較し、自社の作業効率を踏まえて見積りを行うことが、採算を守るうえで重要です。
特に下請企業を抱える場合、最新単価が反映されていないと、現場の賃金格差や人手不足の原因となります。
元請・下請間で最新の単価情報を共有し、適正な取引単価を設定する意識が求められます。
労務単価に関するよくある誤解
労務単価は積算の基礎となる重要な数値ですが、その性質や運用を正しく理解していないまま扱われることも少なくありません。
こうした誤認は、見積り精度の低下や赤字受注など、実務上のリスクを招く原因となります。
ここでは、現場で特に多く見られる3つの誤解を整理します。
労務単価は「支払給与」ではない
最も多い誤解は、「労務単価=作業員への給与額」と考えてしまうことです。
実際の労務単価は、国土交通省が調査・公表する「積算上の標準的な単価」であり、企業が従業員や外注作業員に支払う実際の賃金そのものを示すものではありません。
したがって、設計書に記載された単価を「給与として支払うべき金額」と誤解すると、実際の労務費と積算上の金額の差を見誤り、採算性の低下を招くおそれがあります。
適用すべき労務単価の誤り
労務単価は毎年改定され、2月に公表・3月から適用されます。
古い単価のまま見積りを行う、あるいはどの案件にどの年度単価が適用されるかを誤るケースが多く見られます。
改定を正しく把握していないと、最新の実勢賃金との差が広がり、赤字受注や不当な低入札の原因となるため注意が必要です。
特に年度末から年度初めにかけては、旧単価を前提とした設計書や公告が残っていることがあります。
そのため、入札公告日・設計書の作成年月日を必ず確認し、どの年度の単価が適用されるのかを見極めることが重要です。
地域・職種の適用ミス
労務単価は全国一律ではなく、都道府県ごと・職種ごとに異なります。
同じ「土工」「電工」でも地域によって数千円単位の差があるため、現場所在地の単価を誤ると、見積額が過大または過小になるおそれがあります。
まとめ
労務単価は、公共工事における積算の基礎となる数値であり、
発注者と受注者の双方が「適正な人件費を確保するための共通の指標」として活用しています。
その一方で、労務単価は実際の給与ではなく、毎年の改定・地域差・職種差があるため、
これらを正しく理解しないまま見積りを行うと、採算の崩れや低入札の原因になりかねません。
また、入札に臨む際は労務単価の確認だけでなく、
類似案件の入札価格・落札価格を参考に、適正な見積額を設定することも重要です。
過去の傾向を把握することで、無理のない価格設定と競争力の両立が可能になります。
こうした入札情報のリサーチにおすすめなのが NJSS(入札情報速報サービス) です。
NJSSでは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を一括検索できます。
複数の入札システムを個別に確認する手間を省けるうえ、
8日間の無料トライアルも実施されていますので、ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上