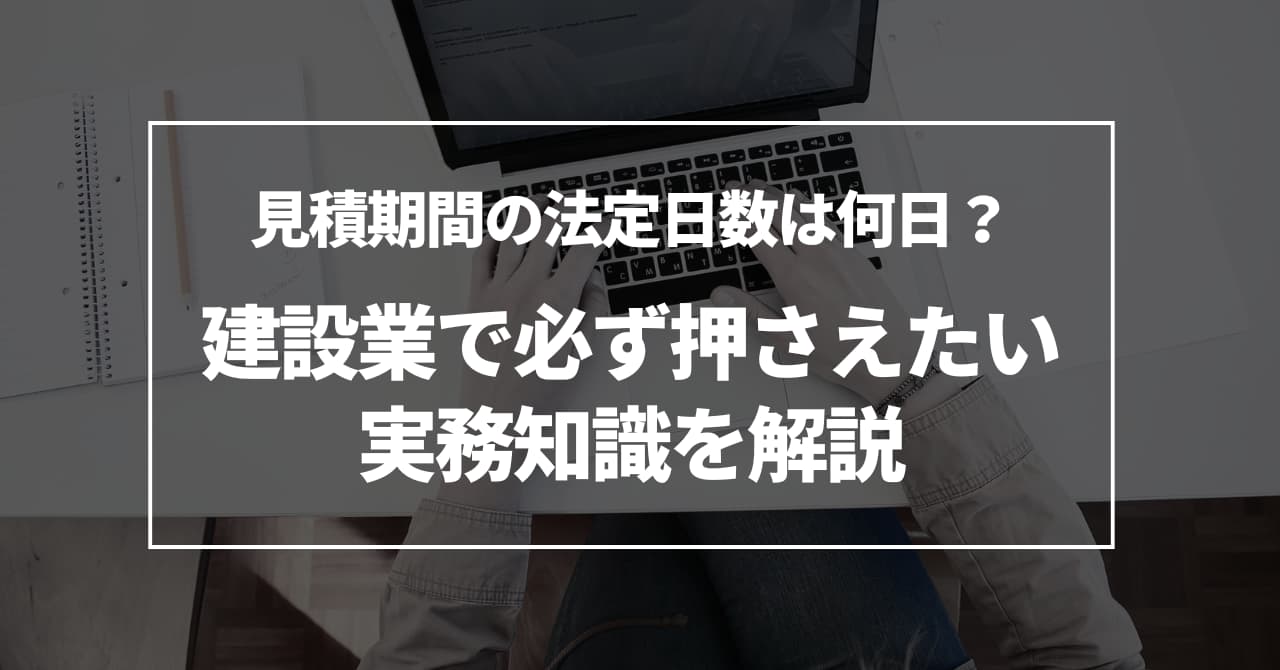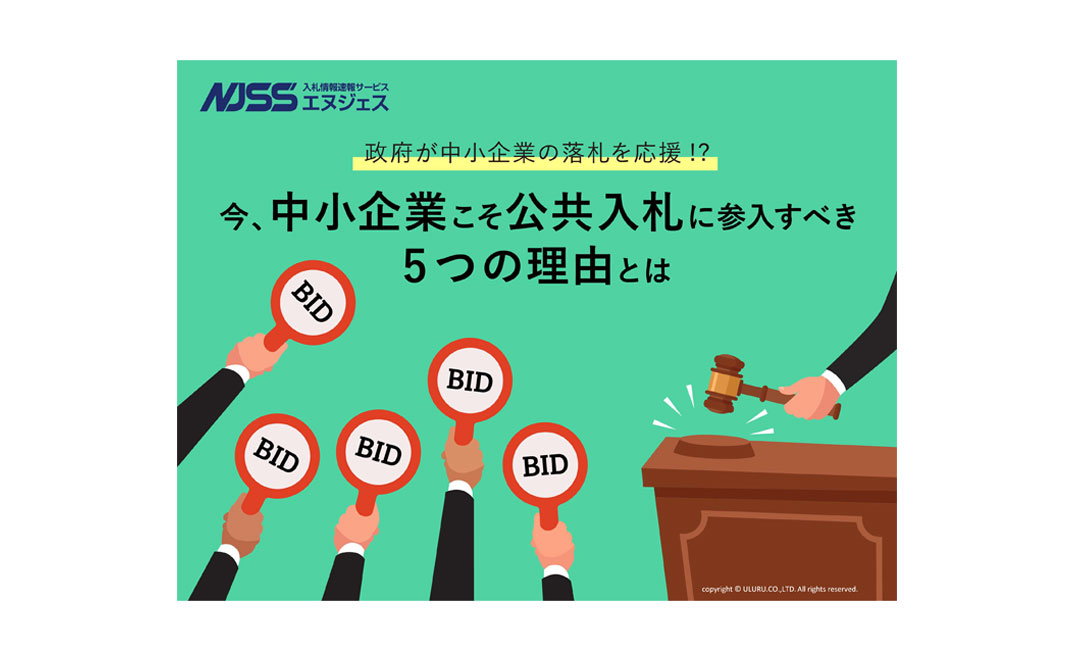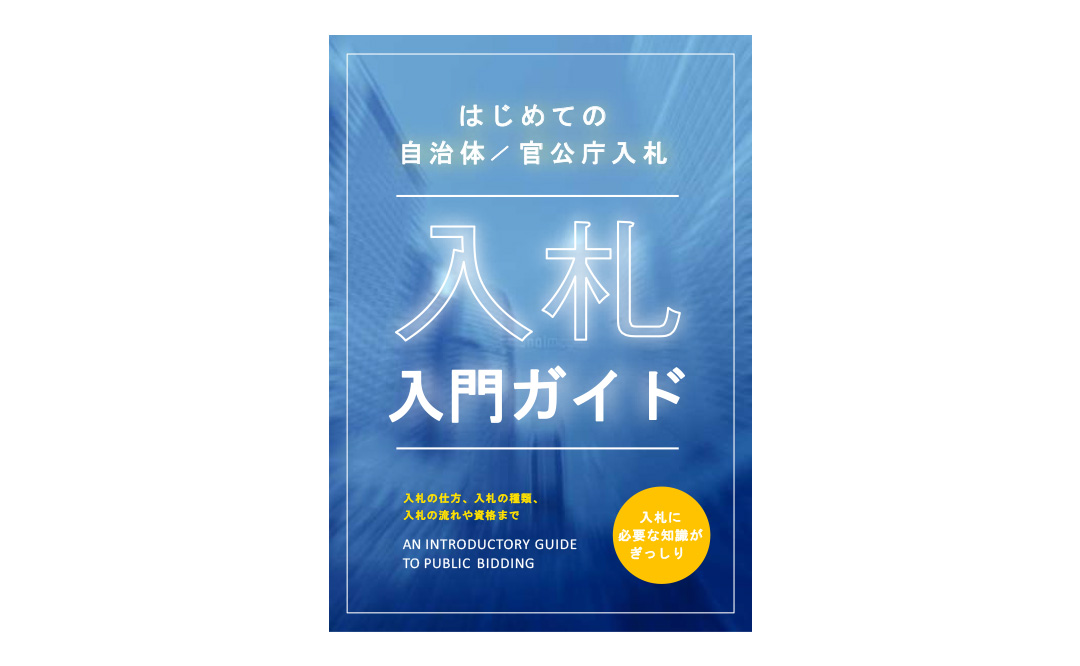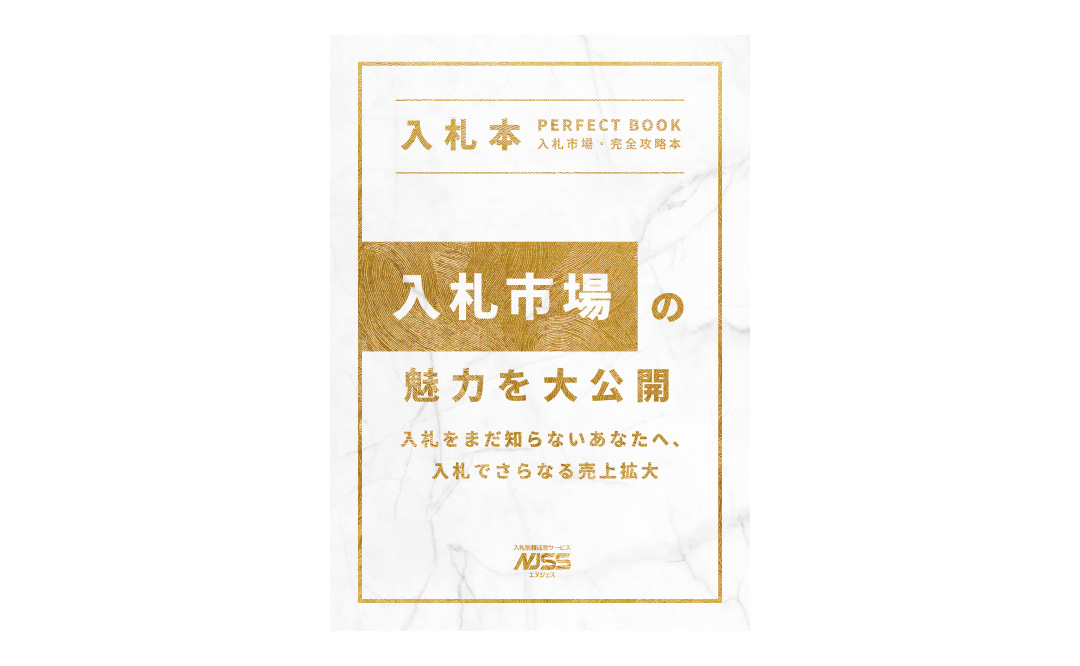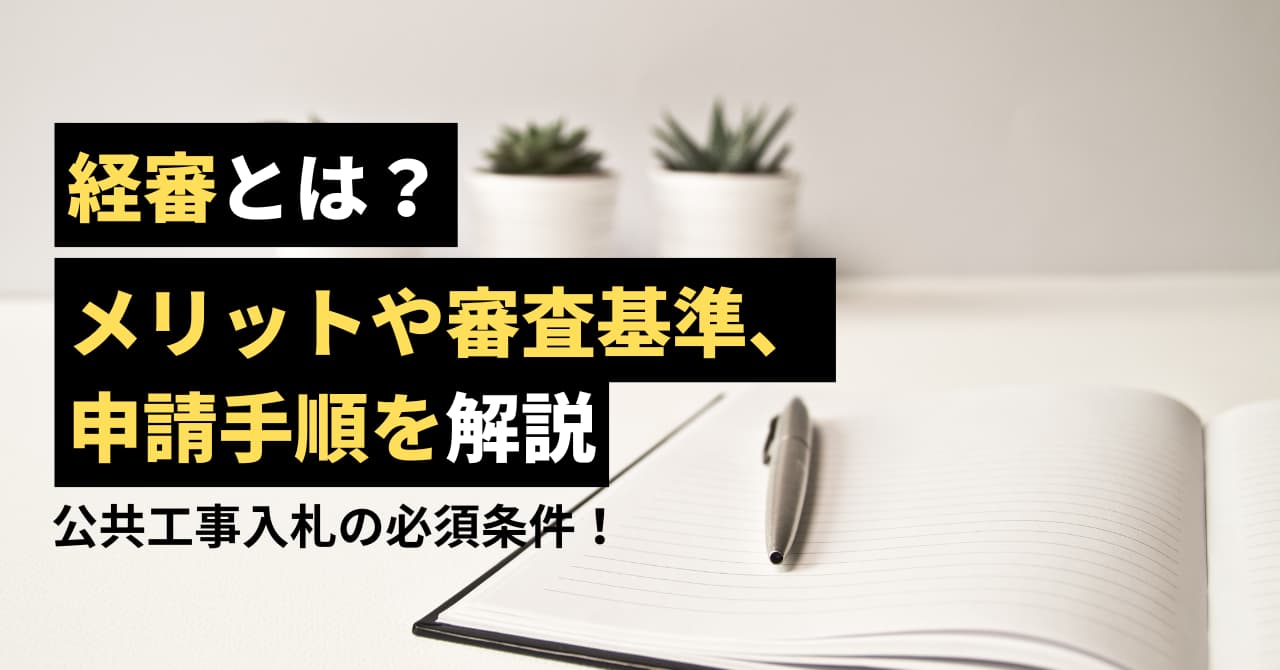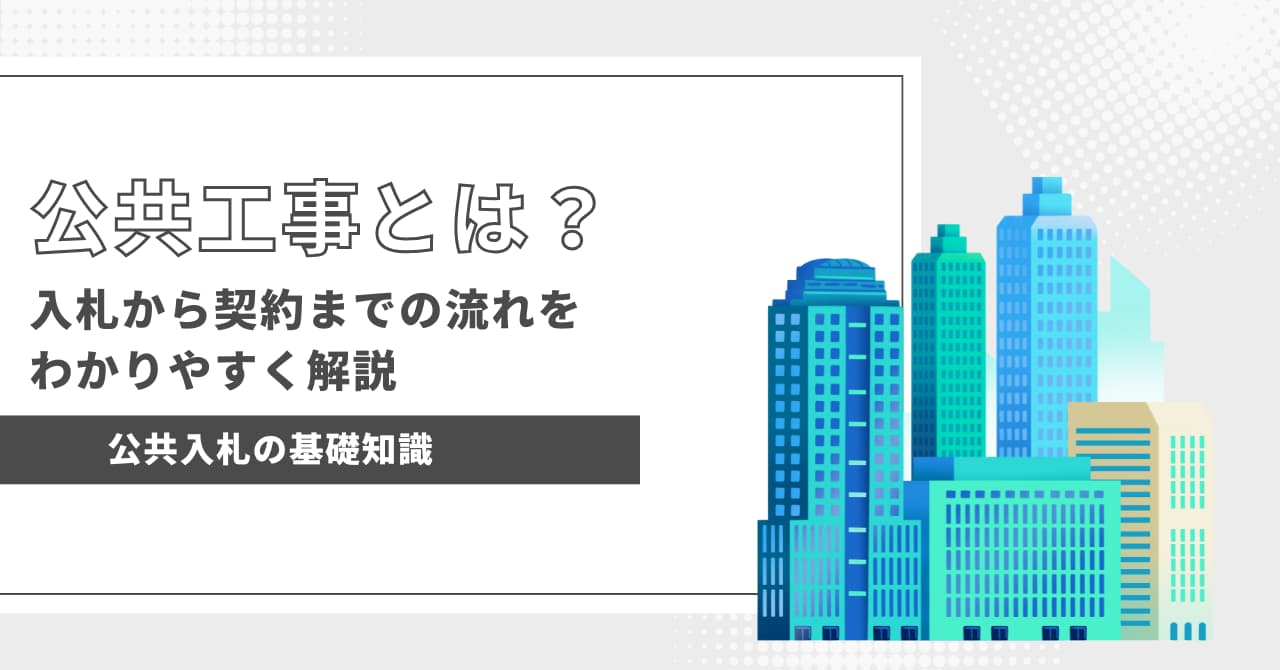- 建設業法第20条に基づき工事金額に応じて見積期間が定められる
- 500万円未満は中1日以上、5,000万円以上は中15日以上など
- 法定日数を下回る期間設定は建設業法違反につながる
- 期間が不十分だと工事の品質低下やトラブルの原因となるため、実質的に検討できる期間の確保が必要
建設工事の見積を依頼する際、「期間は何日以上必要なのか」「休日は期間に含まれるのか」といった疑問は多くの実務者が抱えるポイントです。見積期間の設定を誤ると、建設業法違反のリスクや誤積算・品質低下などにつながるおそれがあります。
そこでこの記事では、見積期間の基本ルール、正しい日数計算、短縮できる条件、不当に短い場合のリスクを解説します。
もくじ
建設業法で定められた見積期間の基本ルール
建設工事の見積もりを依頼する際、発注者側(元請を含む)は、建設業法に基づき、適切な期間を設けなければなりません。このルールは、特に下請業者を保護し、適正な競争環境を確保するために設けられています。
工事金額別に定められた法定最短日数
建設業法第20条は、建設工事の発注者が請負契約の当事者でない者に工事の見積もりを依頼する場合、その見積もりをするために必要な相当の期間を設けなければならない、と定めています。
これを受け、建設業法施行令第6条で、この「相当の期間」の最短日数が具体的に定められています。
建設業法で定められた見積期間は、原則として工事の請負代金の額(予定価格)によって異なります。施行令第6条で規定されている法定の最短日数は以下の通りです。
- 500万円未満の工事:中1日以上
- 500万円以上5,000万円未満の工事:中10日以上
- 5,000万円以上の工事:中15日以上
これは、あくまで発注者が設けなければならない最短日数です。この日数より長く期間を設けることは、下請業者がより精度の高い見積もりを作成できるようになるため、何ら問題ありません。発注者(元請を含む)は、工事の規模や複雑性、見積もりに必要な準備期間を考慮し、この最短日数に余裕を持たせた期間を設定することが望ましいです。
国と地方公共団体での規定の違い
発注者が国や地方公共団体の場合、競争入札における入札公告日から入札日までの期間(実質的な見積期間)の設定には、建設業法の規定に加えて、別の法令が関係します。
国の発注工事の場合
国が発注者となる公共工事については、予算決算及び会計令(予決令)の規定が適用されます。この予決令によって定められた入札公告期間が、建設業法施行令第6条で定める見積期間の特例として扱われます。
地方公共団体の発注工事の場合
地方公共団体が発注者となる工事については、地方自治法や各自治体の規則が適用されますが、国のように建設業法上の見積期間を代替する特例規定はありません。
したがって、地方公共団体は、以下の二つの法令の要件を両方とも満たすように、入札公告から入札日までの期間を設定する必要があります。
- 建設業法施行令第6条の定める、工事金額に応じた最短見積期間。
- 地方自治法などが定める、入札手続きに必要な公告期間。
実務上は、両方の規定が要求する期間のうち、長い方の日数を適用し、入札期間を設定することになります。官公庁案件への参入を検討している担当者は、建設業法だけでなく、地方自治法の規定も合わせて確認することが不可欠です。
見積期間の日数の数え方と、休日の扱い
建設業法に基づく見積期間を実務で適用する際には、「いつから数え始めるのか(起算日)」や「土日祝日を期間に含めるのか」といった具体的な日数の数え方が重要になります。計算方法を誤ると、意図せず法定期間を下回り、法令違反となるおそれがあるため注意が必要です。
起算日は「見積依頼日の翌日」から数える
期間の計算方法については、民法の原則が適用されます。民法第140条の「期間の初日を算入しない」という原則に基づき、建設業法上の見積期間は、見積もりを依頼した日(見積依頼日)の 翌日 を1日目として数え始めます。
工事金額別の法定最短日数に合わせた具体例
建設業法施行令6条では、工事金額に応じて次のように定められています。
- 500万円未満の工事:1日以上
- 500万円以上5,000万円未満:10日以上
- 5,000万円以上の工事:15日以上
これに沿って期間を計算してみましょう。
例えば、12月1日に見積を依頼した場合、工事1件の予定価格に応じて以下のようになります。
- 500万円未満の工事:12月3日以後
- 500万円以上5,000万円未満の工事:12月12日以後
- 5,000万円以上の工事:12月12日以後
休日(土日・祝日)は“原則として含めて数える”
見積期間の計算では、土日・祝日も通常どおりカウントするのが原則です。
法令上、休日を除外する明確な規定はありません。
しかし、実務では相手方への配慮として「見積作業が実質できない日をカウントしない」運用や、休業日を加味した期日の設定が行われる場合があります。
見積期間の例外と「やむを得ない事情」
見積期間の例外
建設業法施行令6条では、工事の予定価格に応じた見積期間の最短日数(1日以上/10日以上/15日以上)を規定しています。
この規定のただし書きとして「やむを得ない事情があるときは、第二号(10日以上)及び第三号(15日以上)の期間は、五日以内に限り短縮することができる。」とあります。
- 500万円以上5,000万円未満(10日以上)→ 最短5日まで短縮可能
- 5,000万円以上(15日以上)→ 最短10日まで短縮可能
「やむを得ない事情」とは
短縮には「やむを得ない事情があるとき」とされています。
この「やむを得ない事情」について、建設業法、同法施行令では明確な定義がありません。
例えば、国が建設工事を発注する場合の見積期間は、予算決算及び会計令(予決令)第74条の規定を建設業法施行令の見積期間とみなすこととされています。
予決令第74条では、以下のとおり規定されています。
- 入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に公告しなればならない
- ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる
建設業法施行令のただし書きと同様に、予決令にもただし書きが存在します。
そして、この「急を要する場合」は、一般的には発注者の都合ではなく、何らかの外部要因で早期契約が必要とされる場合とされています。
したがって、例えば、
- 発注者都合で工程を短縮したいだけ
- 仕様書・図面の準備が遅れたことが発注者の内部要因によるもの
- 単にスケジュールがタイトなだけで、外部要因がない
などは、「やむを得ない事情」と認められない可能性を含んでいます。
見積期間が不当に短い場合のリスク
見積期間は、建設業法20条の趣旨である「下請保護」を実現するために設けられた重要な制度です。
したがって、発注者が法定最短日数を下回る見積期間を設定したり、実質的に十分な期間を与えないまま見積提出を求めたりした場合、発注者・受注者の双方に大きなリスクが生じます。
発注者側のリスク:建設業法違反(行政指導・監督処分)につながる可能性
建設業法20条は、発注者に対して「適切な見積期間を与える義務」を課し、その期間は建設業法施行令第6条で規定されています。
建設業法第28条第1項第2項では、国土交通大臣または都道府県知事に対し「建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき」に、当該建設業者に対し必要な指示を行うことができると規定しています。
また、同条第3項では、こうした不誠実な行為に該当するときや、これに対する指示に従わないときは、1年以内の期間を定めて営業の全部または一部の停止を命ずることができると規定しています。
受注者側のリスク:誤積算・原価割れの懸念
見積期間が短すぎると、下請側は図面・仕様書の確認、現地条件の把握、他工種との取り合い確認、資材単価・労務費の最新価格確認などを、余裕をもって実施できません。
その結果、工程・数量の見落とし、施工条件の読み違い等を引き起こすリスクが高まります。
誤積算が発生すると、工事実施段階で人員・機械の不足による工期遅延などを引き起こし、品質不良や安全面のリスクにまで波及する可能性があります。
見積期間は“形式上の日数”ではなく“実質的に検討できる時間”が必要
見積期間は、単に日数が満たされていればよいわけではなく、実質的に適切な積算・工程確認が可能な期間を確保することが建設業法20条の趣旨に沿う考え方です。
そのため発注者は、
- 法定最短日数を下回らないこと
- 実務的に検討できる期間を確保すること
- 必要であれば十分な資料を早期に提供すること
が重要です。
一方受注者側も、期間が不十分と判断した場合には、
- 発注者へ確認や説明を求める
- 図面・資料の不足を指摘する
- 期間延長の要否を相談する
といった対応により、適正な見積期間や見積に必要な材料を確保する必要があります。
まとめ
見積期間は、建設業法20条および同法施行令6条によって、工事金額に応じた最低限の期間(1日以上・10日以上・15日以上)が定められています。
これは下請企業が適切な積算やリスク評価を行えるようにするための制度であり、発注者が恣意的に期間を短縮することは認められていません。
日数計算は「起算日は依頼日の翌日から」「休日は原則として含める」など注意点が多く、誤ると法定日数を下回るおそれがあります。
また、やむを得ない事情がある場合に限り短縮が可能ですが、具体的な例示が法律にないため適用は慎重に行う必要があります。
期間が不当に短い場合、建設業法違反につながるだけでなく、誤積算・品質低下・追加費用トラブルなど、受発注双方に大きな影響が生じます。
特に、建設工事のうち公共工事を受注しようとする企業にとっては、こうした建設業法の制度理解のほか、発注情報を迅速かつ正確に把握することが重要です。
公共工事は入札方式や契約手続が法令で細かく定められており、競争環境が整備されているため、いち早く発注情報を収集できるかどうかが、営業活動の効率や受注機会の確保に直結します。
こうした公共工事の情報収集に有用なのが、NJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報をまとめて検索でき、自治体ごとに異なる入札システムへ個別にアクセスする手間を削減できます。
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上