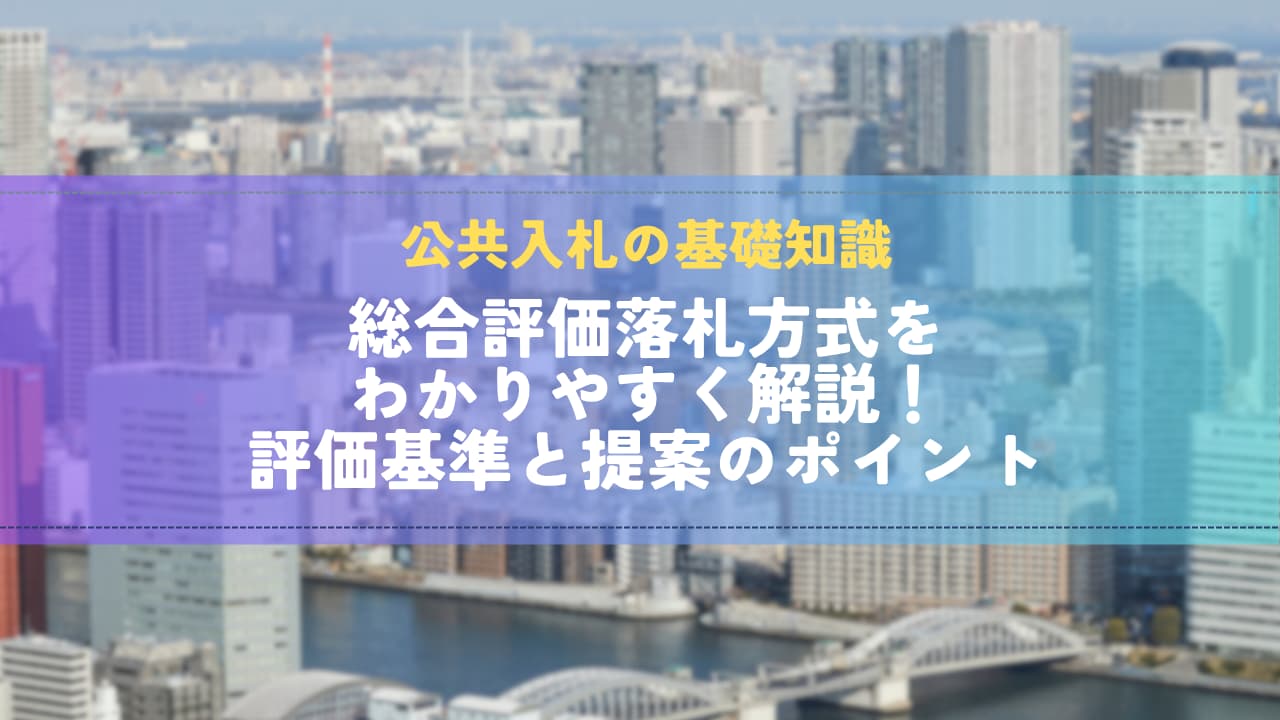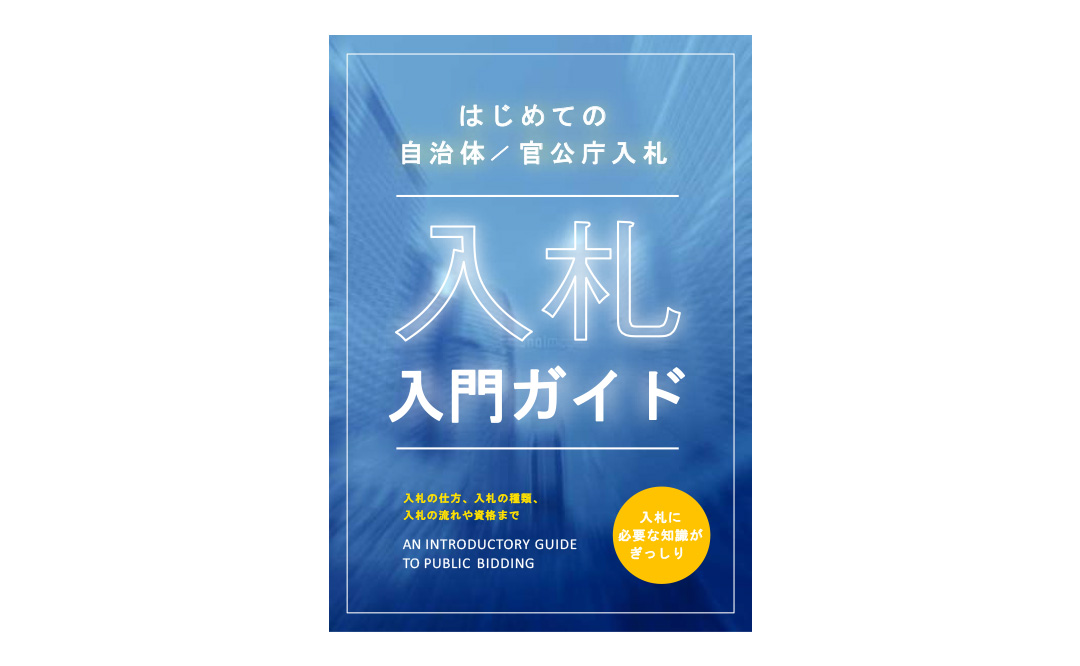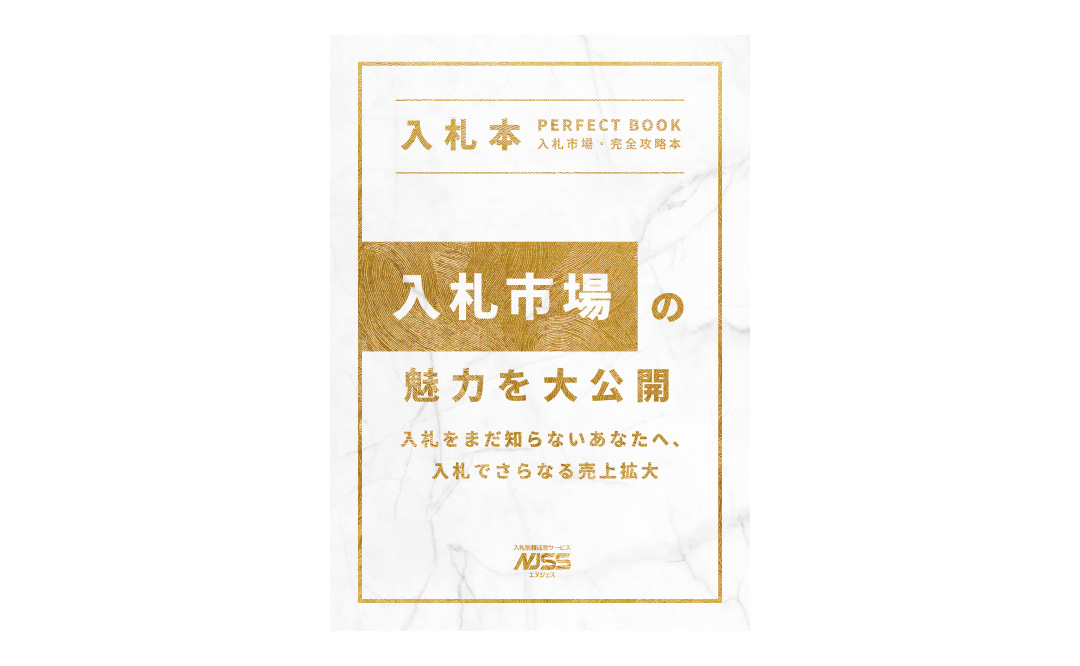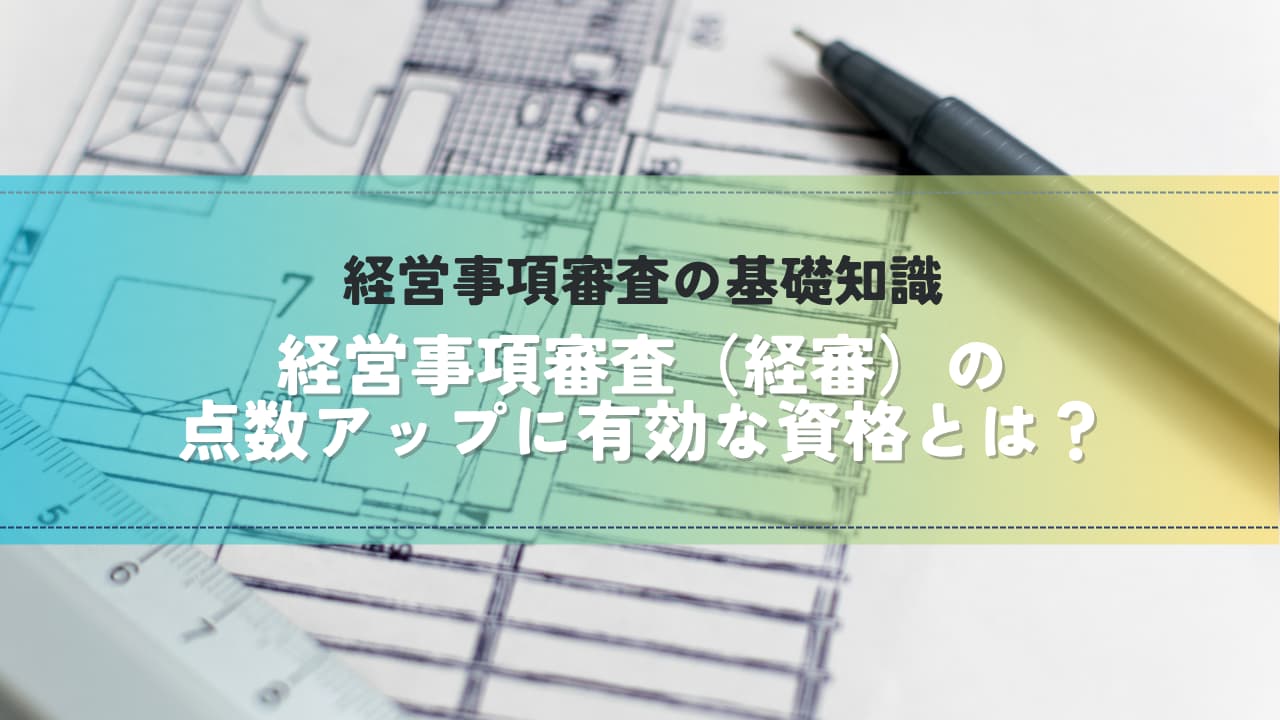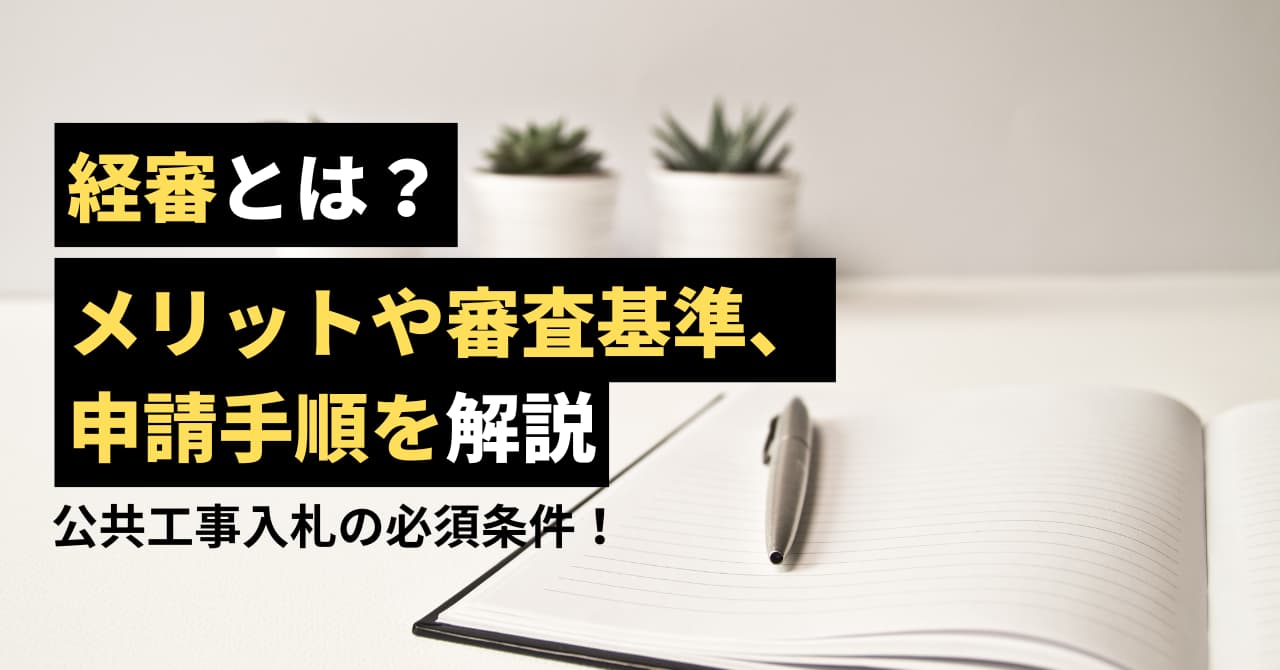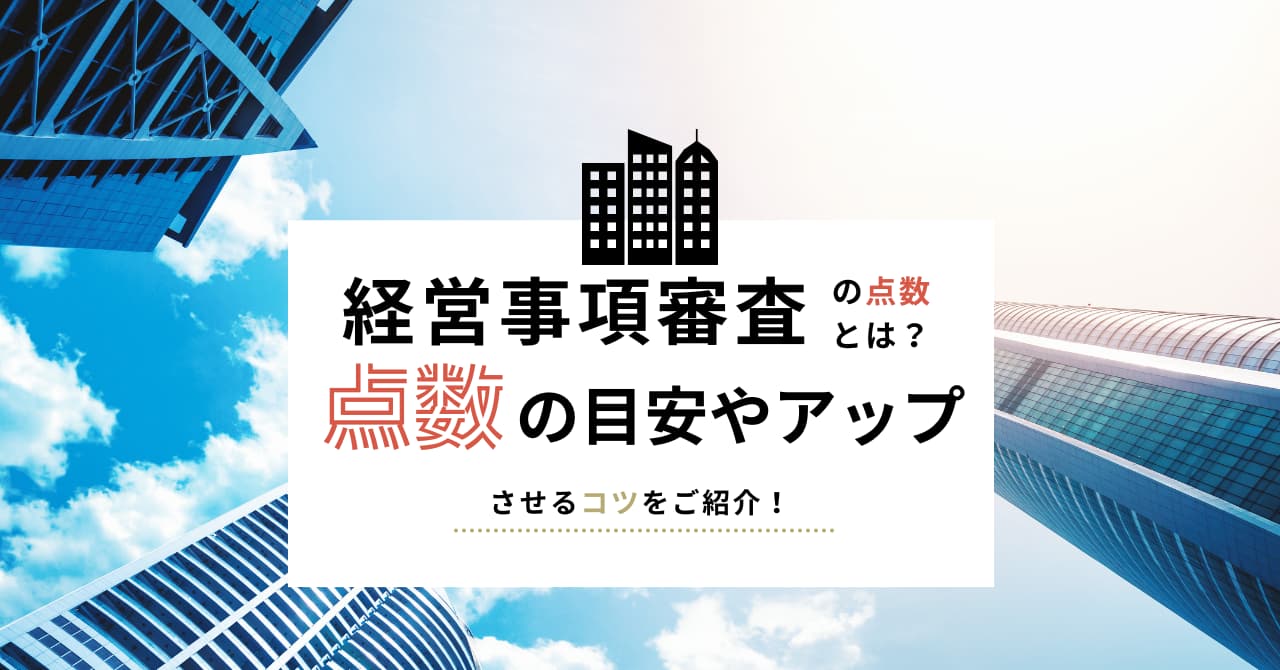- ISO認証は経審の「社会性等(W点)」に加点される
- 総合評定値(P点)が向上し、公共入札で有利に働く
- 経審加点以外にも多様なメリットがある
公共工事の受注を左右する経営事項審査(経審)において、評価対象は企業の技術力や財務状況だけでなく「社会性」も重要な評価項目です。
その他審査項目(社会性等)W点として、様々な取り組みが評価の対象となっており、その一つが国際標準化機構(ISO)認証の取得です。
本記事では、「ISO認証が経審でどのように加点されるのか」という仕組みから、経審加点以外の多岐にわたるメリット、さらには認証取得にかかるハードルや注意点まで、詳しく解説します。
ISO認証取得が公共工事市場における競争力強化にどのように貢献するかを理解し、入札参加戦略検討の参考にしてみてください。
もくじ
ISO認証取得で経営事項審査が加点される仕組み
ISO認証の取得は、経審の総合評定値Pを構成する要素の一つであるW点(社会性等)に反映されます。
W点は、各種保険への加入状況や法令遵守の状況など、技術力や財務状況以外の側面から企業を評価する項目です。
ISO認証の取得は、W点のうち「国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)」で評価されます。
具体的に加点対象となる主なISO規格は、以下の二つです。
ISO 9001(品質マネジメントシステム)
顧客満足度の向上と品質保証を目的とした国際規格です。製品やサービスの品質を継続的に改善するための仕組みが整っていることを示します。建設業においては、施工品質の安定化や顧客からの信頼獲得に直結するため、非常に重要視されます。
ISO 14001(環境マネジメントシステム)
環境負荷の低減と環境パフォーマンスの向上を目的とした国際規格です。事業活動が環境に与える影響を管理し、改善するための仕組みが整っていることを示します。持続可能な社会への貢献が求められる現代において、企業の環境配慮への姿勢は公共工事の発注者からも高く評価されます。
これらのISO認証を取得している企業は、W8点においてそれぞれ5点加点が得られます。ISO 9001とISO 14001の両方を取得している場合は、それぞれの加点が合算されるため、より大きな評価点を得ることが可能です。
認証取得によって、企業は単に事業を行うだけでなく、そのプロセスや結果が一定の国際基準に準拠していることを示すことができ、公共工事の入札において競争力を高める要因となります。
ISO認証取得は、企業の内部管理体制を強化し、業務の効率化やリスク低減にも寄与します。これは、経審の加点だけでなく、企業価値そのものを高める上でも大きなメリットとなります。
なお、これらの加点はISO認証の範囲が企業全体である場合のみ評価されます。認証範囲に建設業が含まれていない場合や一部の支店のみ認証を受けている場合は加点されません。
また、W8点では、ISO9001・ISO14001のほか、環境省が策定した「エコアクション21」認証・登録事業者に対して3点の加点があります。(ただし、ISO14001:5点に該当する場合は加点なし)
ISO認証取得による経審以外のメリット
ISO認証の取得は、経営事項審査(経審)での加点に加えて、公共工事の受注機会拡大や企業としての競争力強化においていくつかのメリットがあります。
各発注者の「格付け」における評価対象
国や地方公共団体などの各発注機関は、競争入札参加資格審査において、客観的評価である経営事項審査(経審)の点数に加え、企業独自の取り組みや実績を評価する「主観点」を定めている場合があります。
この客観点と主観点を総合して算出される総合得点をもとに、発注標準に適合した企業を仕分けるのが「格付け」です。
ISO認証の取得は、この主観点において、企業の品質管理体制や環境配慮への意識の高さを示す客観的な証拠として、評価の対象となることがあります。
これにより、より高い格付けを獲得し、より契約金額が大きい入札案件へ参加する機会が増える可能性があります。
総合評価落札方式での加点
総合評価落札方式は、価格だけでなく、企業の技術力、施工能力、信頼性、環境配慮といった非価格要素を総合的に評価して落札者を決定する入札方式です。
この方式において、ISO認証(特にISO 9001やISO 14001)の取得は、「品質確保への取り組み」、「環境配慮」または「企業の信頼性」といった評価項目において、加点対象となる場合があります。
企業イメージと信頼性向上への寄与
ISO認証の取得は、国際的なマネジメントシステム基準への準拠を意味し、その事実自体が企業の対外的なイメージと信頼性を大きく向上させます。
これにより、公共工事の発注者だけでなく、民間企業や金融機関、地域社会など、あらゆるステークホルダーからの評価が高まることが期待できます。
結果として、新たなビジネスチャンスの創出や、企業のブランド価値向上にも繋がります。
ISO認証取得のハードルと注意点
ISO認証の取得は、経営事項審査(経審)での加点や企業価値向上に多大なメリットをもたらす一方で、一定のハードルと継続的な取り組みが求められます。
認証取得を検討する際には、これらを十分に理解し、計画的に進めることが重要です。
認証取得プロセスとマネジメントシステムの構築
ISO認証を取得するためには、外部の審査機関による厳格な審査を受ける必要があります。
この審査を通過するためには、まず自社内に選択したISO規格(例:ISO 9001、ISO 14001)に適合したマネジメントシステムを構築することが不可欠です。
マネジメントシステムの構築とは、例えばISO 9001であれば品質方針の策定、品質目標の設定、文書化された手順の確立、記録の管理、内部監査の実施、マネジメントレビューといった一連のプロセスを社内に導入し、運用することを指します。
これらは、単に書類を揃えるだけでなく、実際の業務にシステムが組み込まれ、継続的に改善される体制が求められます。
取得にかかる期間とリソース
ISO認証の取得には、一般的に半年から1年程度の期間を要します。これは、マネジメントシステムの設計から文書化、実際の運用、内部監査、そして最終的な外部審査に至るまでの準備期間が必要となるためです。
自社のみでこのプロセスに取り組むことも可能ですが、ISO規格の解釈やシステム構築のノウハウが不足している場合、時間と労力が過大になる可能性があります。そのため、ISO認証取得を専門とするコンサルティング企業の支援を受けることも有効な手段です。
認証の維持と継続的な改善活動
ISO認証は一度取得すれば終わりではありません。認証取得後も1年に1~2回実施される定期審査と3年毎に行われる更新審査を受ける必要があります。
この審査に合格し続けるためには、構築したマネジメントシステムが継続的に適切に運用する必要があります。
経審加点以外の効果を加味した実施判断
ISO認証取得の最大の目的が経営事項審査での加点のみである場合、投入するリソース(時間、労力、費用)に対して、得られる点数はW8で最大10点です。
そのため、認証取得の判断にあたっては、経審加点という直接的なメリットだけでなく、前述した「業務プロセスの標準化と効率化」「企業イメージと信頼性向上」「リスク管理の強化」「従業員の意識向上と組織力の強化」といった、経審加点以外の長期的な経営メリットも十分に加味して、総合的な費用対効果を評価することが重要です。
ISO認証は、企業そのものの体質を強化し、持続的な成長を促すための投資であるという視点を持つことが肝要です。
結局、経審対策でISO認証を取得すべきか
ISO認証の取得は、経営事項審査(経審)での加点だけでなく、企業の多角的な競争力強化に貢献します。
しかし、その実施判断には、自社の状況と得られる効果を総合的に評価することが不可欠です。
自社の状況と加点効果の評価
ISO認証取得の是非を検討するにあたり、まず自社の現在の経審点数と入札参加する発注者による格付けの状況を把握することが重要です。
例えば、ISO9001・14001をそれぞれ取得した場合、W8で10点の加点です。審査基準日が令和5年8月14日以降の場合、W点はW1~W8の各点数に「1,750/200」を乗じて算出しますので、10点×1,750/200=87.5点引き上げられることになります(その他評点W算出時の小数点以下端数は、切り捨て)。
経審の総合評定値(P点)の計算式は「P点 = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W」です。そのため、W点が87.5点引き上げられることで、P点は「0.15×87.5=13.125点」引き上げられることになります。
認証の取得によってP点が最大約13点加点されることで、公共工事の発注者が独自に定める「格付け」で上位の区分を獲得できる可能性が高い場合は、取得を検討する意義が大いにあります。
上位の格付けは、より規模の大きな案件や、特定の専門工事への入札参加資格に直結するため、将来的な受注機会の増大という形で、直接的な利益が見込めます。
しかし、ISO認証取得のみでは上位格付けの獲得が期待できない場合は、経審以外の様々なメリットを考慮して判断することが重要です。
経審加点以外の多角的なメリットの考慮
ISO認証取得のメリットは、経審の点数加点だけではありません。
上述のとおり、総合評価落札方式での加点や、マネジメント体制の構築により企業そのものの価値を高め、長期的な企業成長に貢献する可能性も十分にあります。
ISO認証自体は、経審・入札での評価を目的としたものではありませんので、むしろISO認証取得プロセスを通じて経営課題の解決を図っていくことこそが認証制度本来の機能とも言えるかもしれません。
投資対効果を軸にした最終判断
ISO認証の取得と維持には、審査費用、コンサルティング費用、そして内部リソース(時間や人件費)といった一定の投資が必要です。
この投資が、自社にとって見合う効果をもたらすかを軸に最終的な判断を下すことが肝要です。
ここでいう「効果」は、企業の状況や経営戦略によって異なります。例えば、上位格付けの獲得を主な目的とするのであれば、それに伴って期待される将来の受注機会の増分と、ISO認証にかかる総投資額を比較検討することが重要です。
また、経審点アップや入札優位性だけでなく、企業価値向上といったより中長期的な視点での経営判断も加味するのであれば、ISO認証は単なるコストではなく、企業体質の改善と持続的成長のための戦略的な投資と位置づけることができます。
短期的な加点点数のみに目を向けるのではなく、企業全体の競争力強化という広い視野で、ISO認証取得の意義を評価することが求められます。
まとめ
ISO認証の取得は、経営事項審査(経審)での加点に加え、企業の信頼性向上や競争力強化などのメリットがあります。しかし、その実施判断においては、投入するコストと得られるメリットのバランスを慎重に考慮することが不可欠です。
特に、ISO認証取得によって上位の「格付け」を狙う企業にとっては、過去の公共工事案件を詳細に調査し、どの程度の受注機会を拡大できるかを分析することが、投資対効果を評価する上で極めて重要になります。この分析を通じて、ISO取得にかかる費用や労力に見合うリターンが期待できるかを具体的に見極めることができます。
受注機会の分析にあたっては、基本的に各発注者の入札システムを個別に確認する必要がありますが、入札参加する機関の数が増えると確認先も膨大になり莫大な時間が必要となってしまいます。
そこでおすすめなのが、NJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSは全国約8,900機関の入札情報を網羅しており、地方自治体や準公的機関も含めた広範な案件を一元的に検索できます。
過去の発注情報や落札者情報も確認できますので、受注機会を検討する際の負担軽減につながります。
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、この機会に活用し利便性をぜひ体感してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上