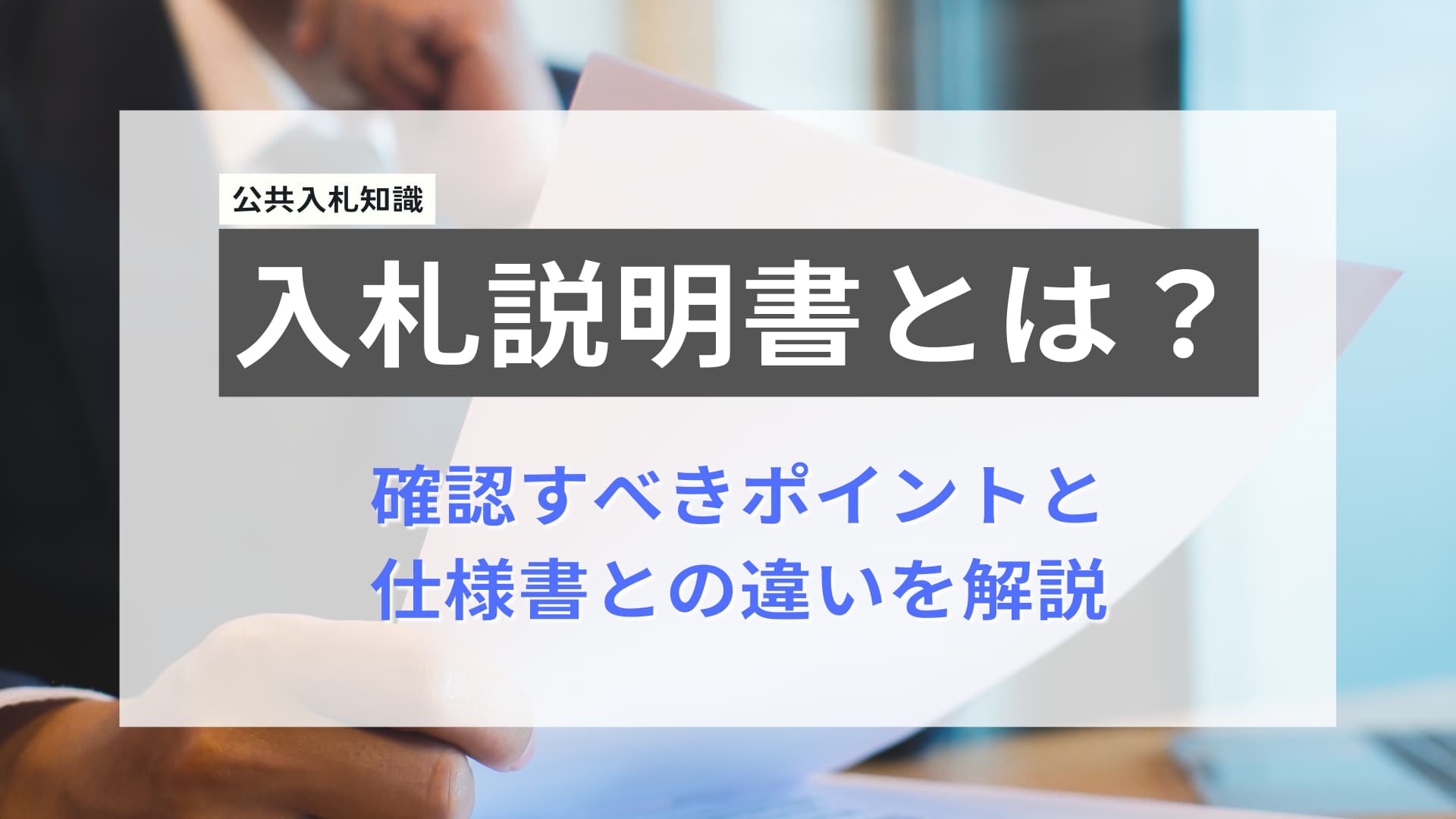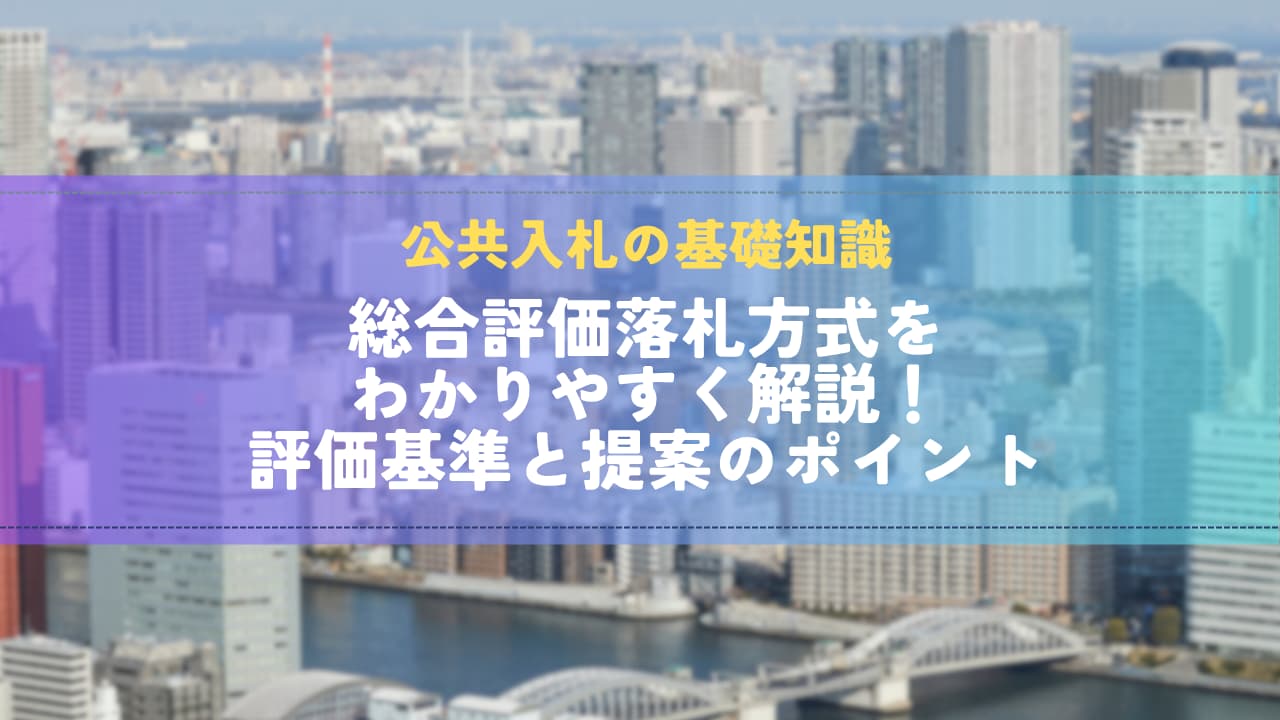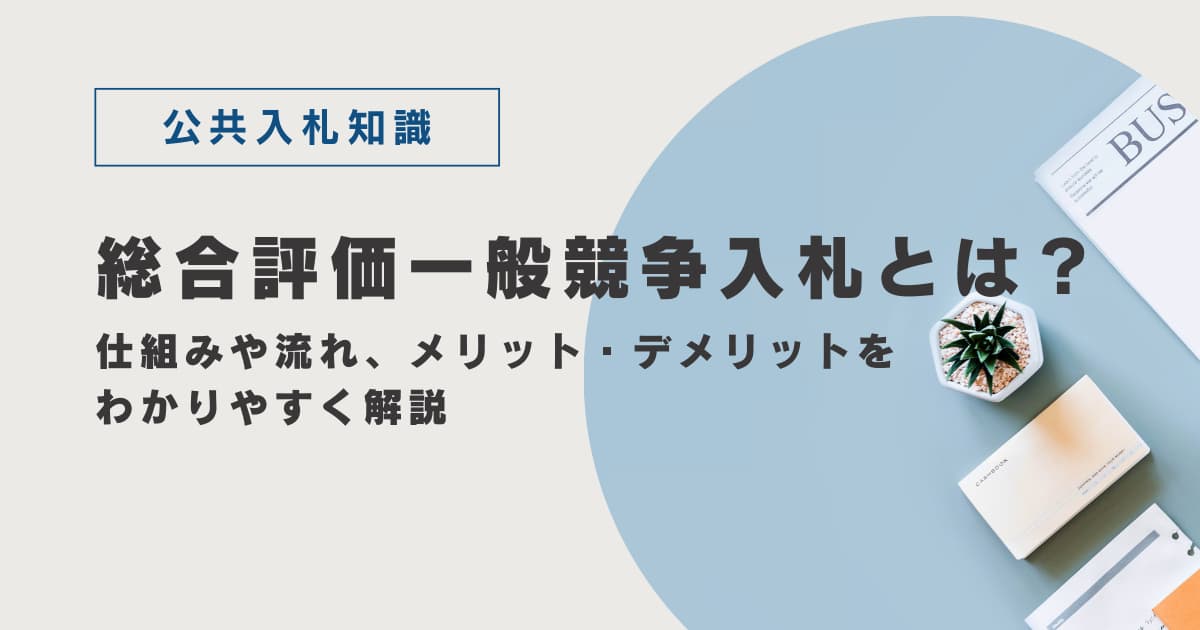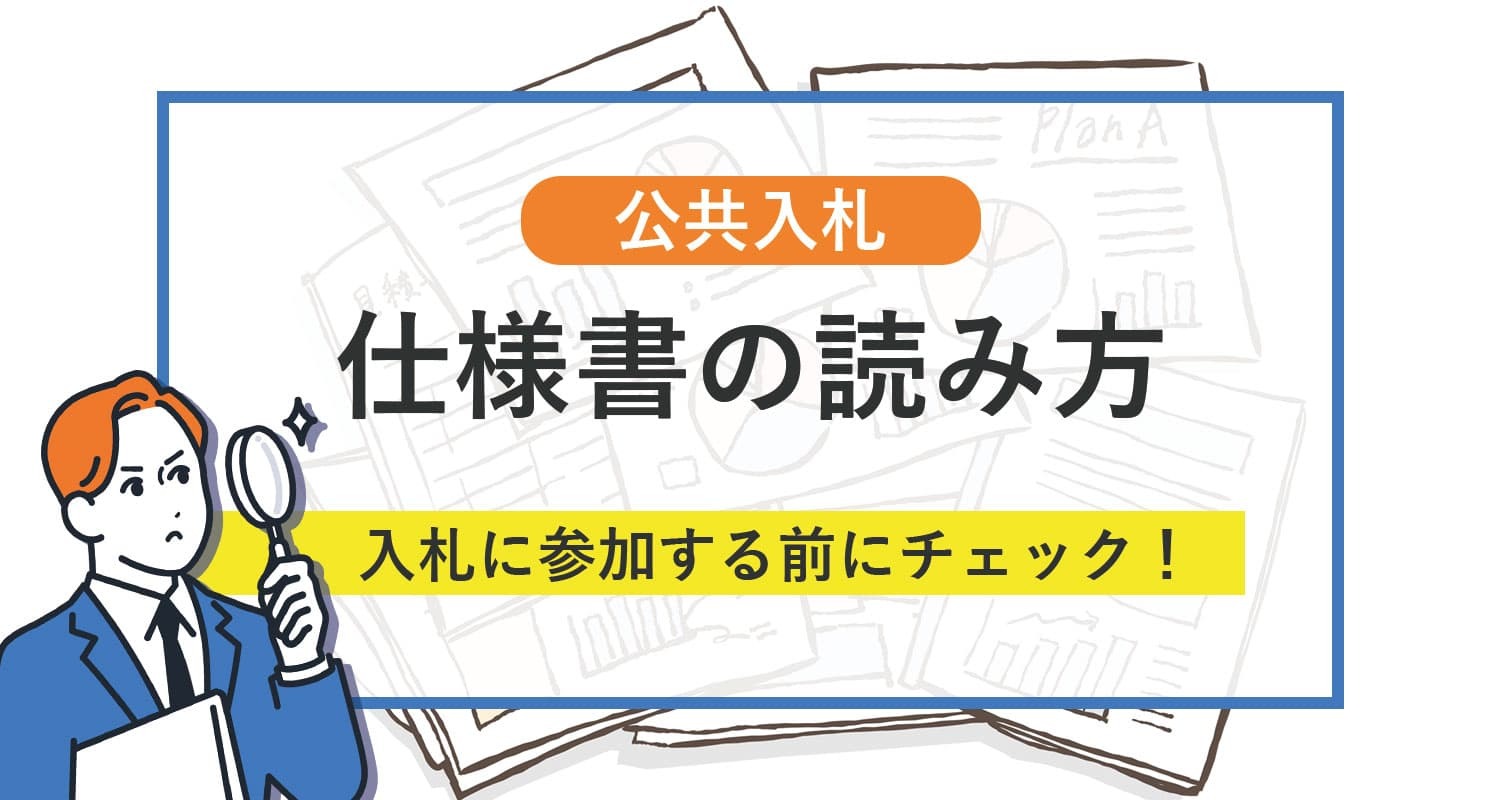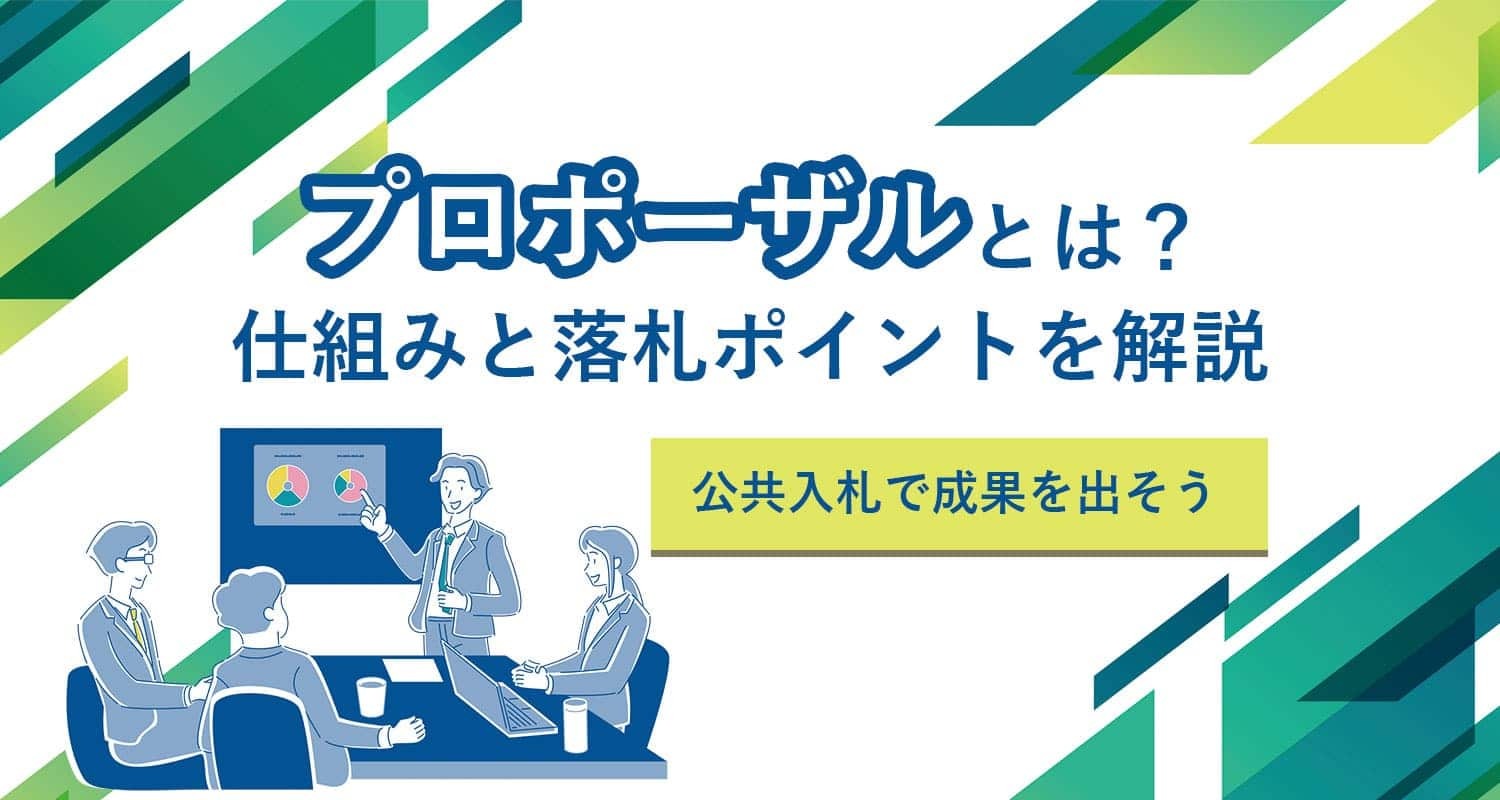- 入札説明書とは、参加資格、提出書類、評価方式など、手続きの詳細を定めた文書
- 仕様書は業務内容や品質、数量など、調達の「中身」を説明する文書
- 入札説明書にかかれている要件を満たさないと失格になるリスクがある
国や地方自治体の入札公告に添付される資料に「入札説明書」があります。
この書類は、入札手続のルールや提出書類の指定、締切日時など、入札に参加するために欠かせない情報がまとめられた重要な資料です。
特に、総合評価落札方式や公募型プロポーザル方式など、価格以外の要素も評価対象となる入札では、入札説明書の記載を正確に理解していなければ、形式不備で失格となる可能性もあります。
この記事では、入札説明書とは何かを基本から解説し、仕様書との違いや特に注意して確認すべきポイントをわかりやすく紹介します。
もくじ
入札説明書とはどんな資料か?
入札説明書の概要
入札説明書とは、国や地方自治体などの公的機関が実施する入札において、調達の対象や入札の手続きに関する詳細情報を記載した資料です。
多くの場合、入札公告時に「関係図書」として添付される場合が一般的です。発注内容や入札方式によっては提供されない場合もあります。
発注機関のホームページや電子入札システム上で、公告情報とともにダウンロードできる形式で提供されることが多くなっています。
すべての案件において入札説明書が作成・添付されているとは限らず、案件の内容や規模、契約方式によっては別資料(仕様書や募集要領等)に情報が分散している場合もあるため、関係資料全体の確認が重要です。
入札説明書に記載される主な内容
入札説明書には、例えば以下のような情報が記載されます。
事業の概要
調達対象となる工事・業務・物品の内容や目的
入札の参加資格要件
建設業許可や経営事項審査(経審)などの資格条件
手続きのスケジュール
公告日、質問受付期間、入札書提出期限、開札日など
提出書類の一覧・記載方法
入札書、内訳書、技術提案書などの提出様式と記載要領
入札方法と評価方式
一般競争入札/指名競争入札、総合評価/価格競争などの決定方式
注意事項
無効となる入札の条件、契約手続に関する特記事項など
したがって、入札公告に入札説明書が添付される場合は、その内容を熟読して参加申請、入札方法を正しく把握して必要な手続きに臨む必要があります。
入札説明書と仕様書の違い
入札公告には「入札説明書」と「仕様書」という2種類の文書が添付されていることがあります。
どちらも非常に重要な資料ですが、目的や内容に明確な違いがあります。それぞれの役割を正しく理解することで、適切な応札準備につながります。
仕様書の役割
仕様書は、発注機関が求める業務や工事の内容、品質、数量、施工方法などを記載した文書です。たとえば建設工事であれば、工法、使用材料、施工基準、工期、検査の方法などが詳細に定められています。
この資料は、業務の「中身」に関する理解を深めるために不可欠であり、応札価格の見積や作業計画の検討に直結します。
技術提案書や内訳書を作成する際にも、この仕様書の記載事項に沿って内容を構成する必要があります。
入札説明書の役割
入札説明書は、入札手続そのものの進め方やルールを記載した文書です。公告日や開札日などのスケジュール、必要書類、提出先や提出方法、評価基準、無効入札となる条件など、「いつ・なにを・どう提出するか」が定められています。
公共入札は高い透明性・公平性が要求されます。入札説明書の確認を怠り、形式的な要件を満たせない場合は、入札参加そのものが認められないことが想定されます。
そのため、入札説明書は業務内容が記載された仕様書と併せてよく確認すべき資料と言えます。
入札説明書の確認が重要な理由
公共入札には高い透明性・公平性が要求されます。そのため、入札金額や技術提案の検討はもとより、形式面の要件を確実に満たすことが重要です。
こうした入札参加の手続き方法が記載されているのが入札説明書です。特に以下の点で入札説明書の確認は重要です。
入札参加に必要な情報が記載されている
入札説明書には、提出書類の種類や方法、提出期限、入札方式、質疑応答のルール、スケジュールなど、入札参加に必要な情報が網羅されています。公告文や仕様書では記載されないことも多く、説明書を確認しなければ正しい手続きを進めることはできません。
また、説明書に記載された条件や様式を満たさなければ、内容が優れていても入札自体が無効とされることがあります。例えば「指定様式を使わなかった」「提出期限を過ぎた」「必要部数を揃えていない」といった形式的な不備も失格の原因です。
つまり、入札説明書は「参加のためのガイド」であると同時に「失格を避けるためのチェックリスト」としての役割を果たしています。
効率的な準備のために不可欠
総合評価落札方式や公募型プロポーザルでは、準備の早さと正確さが結果を大きく左右します。
例えば「A4で20枚以内」「電子データも同時提出」といった要件を早い段階で把握できれば、必要な資料作成や社内外との調整を前倒しで進められます。
その結果、限られた時間の中で提案内容を磨き上げ、他社との差別化につなげることができます。
入札説明書で特に確認すべき事項
入札説明書は必ずしも作成されるものではなく、公告本文に同等の情報が含まれる場合もあります。したがって、まず「説明書が用意されているかどうか」を確認し、なければ公告本文を隅々まで読み込むことが重要です。
入札説明書や入札公告には、入札参加の可否を左右する実務的な条件がまとめられており、確認を怠れば思わぬ失格につながる可能性があります。特に以下の事項は注意が必要です。
提出書類と提出方法
提出すべき書類の種類や提出先、提出期限、提出形式(紙媒体・メール提出・システム上にアップロードなど)は発注者・入札案件ごとに異なります。これらは説明書または公告に詳細が記載されており、一つでも不備があれば形式上の理由で失格となることがありえます。
例えば、電子データと紙媒体の両方で提出を求められているのに電子データのみを提出した場合や、押印が求められているにもかかわらず失念した場合などは典型的な失敗例です。
仕様に関する質問の方法
疑問点や不明点がある場合の問い合わせ方法についても記載されています。質問の受付期間、質問の方法(書面、電子メール、専用システムなど)、回答の時期や手段が示されているため、仕様書の内容で不明点があれば早めに確認を行い、必要に応じて質問手続きをとる必要があります。
質疑応答の内容はすべての応札者に共有されるため、回答内容が見積もりや提案に影響することもあります。
入札の方法(入札金額の算定方法)
入札の方式(一般競争、指名競争、随意契約など)や、金額の算定方法に関する記載もよく確認する必要があります。
たとえば、内訳書の提出が必要か、税抜・税込どちらの金額を記載するのか、予定価格との関係性(最低制限価格や調査基準価格の設定)があるかなどが記載されています。
とくに総合評価落札方式の場合は、価格とあわせて技術提案の配点構成にも注意が必要です。
技術資料の作成・提出方法
総合評価落札方式や公募型プロポーザルなど、価格以外の要素も評価対象となる案件では、技術資料の提出が求められることがあります。入札説明書には、以下のような記載が見られます。
提出方法・形式
多くは電子データ(PDF等)での提出を求められ、メール送付や専用ポータルへのアップロードなど、提出先が指定されています。ファイル名の付け方が決められているケースもあり、誤ると受理されないこともあります。
様式の指定
提案書や自己採点シートなど、指定の様式を使って記載する必要があります。書き漏れや順序の誤りは減点の対象になりやすいため注意が必要です。
ページ数や体裁の制限
「A4で5ページ以内」「文字サイズは10.5ポイント以上」など、枚数や文字サイズが定められている場合があります。超過すると失格扱いとなる例もあります。
記載内容の精度
評価項目ごとに根拠資料の提示が求められることが多く、単なる主張だけでは不十分です。虚偽や誇張は無効につながるため、客観的事実に基づいて整理することが求められます。
提出期限
技術資料の提出期限は入札書の期限とは異なる場合があります。提出順序を誤ると参加資格を失う恐れがあるため、必ず事前にスケジュールを確認することが重要です。
技術資料は加点の根拠となる一方で、形式や内容の不備によって失格となるリスクも高い書類です。公告や説明書の記載を丁寧に確認し、早めに準備を始めることが求められます。
まとめ
公共工事の入札に参加する際、入札説明書の確認は不可欠です。入札の手続きや条件に関する詳細が記載されており、これをおろそかにすると、どれほど内容が優れていても形式要件を満たさず無効となる可能性があります。特に、総合評価落札方式やプロポーザル方式では、指定された書式や提出方法に従わなければ、評価の対象にすらなりません。
また、参加を検討している案件については、過去に同様の業務が入札に付されていないか確認することも有効です。発注機関は、前年や数年前と同様の形式・条件で再度発注することが多いため、過去事例を確認することで、提出資料の方向性や落札傾向を把握するヒントになります。
こうした過去の入札情報を効率的に調べる手段としておすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。全国の官公庁・自治体が発信する入札・契約情報を一括で検索できるため、情報収集の手間を大きく削減できます。無料トライアルも提供されているため、導入前に使い勝手を確認することも可能です。
入札においては、情報収集と準備が何より重要です。入札説明書の読み込みと過去情報の活用を徹底し、確実に成果につなげていきましょう。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上