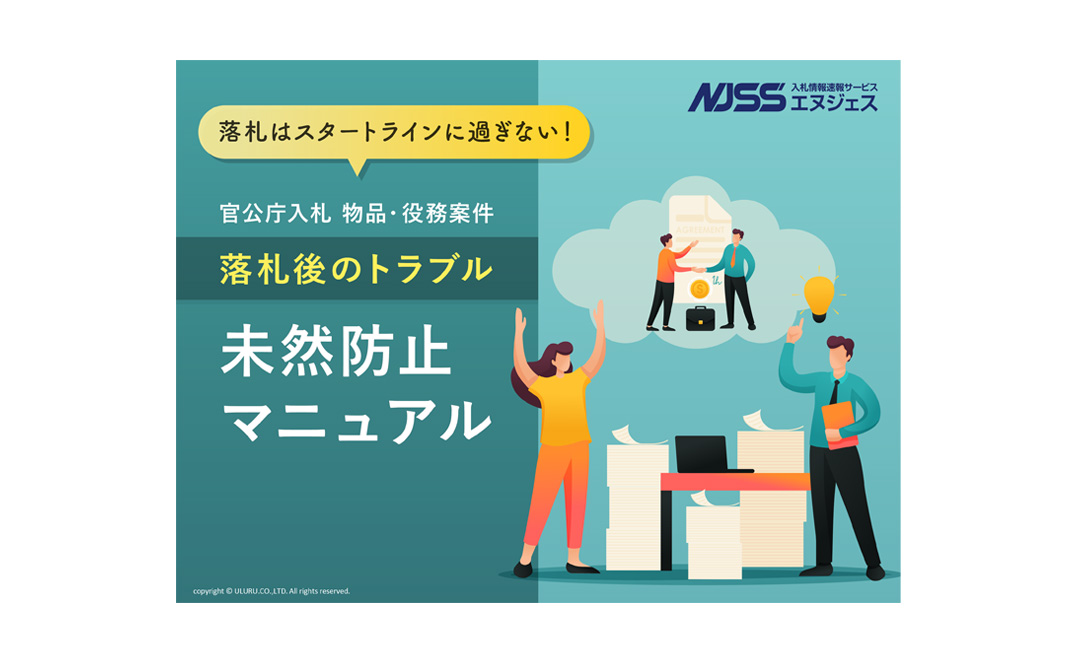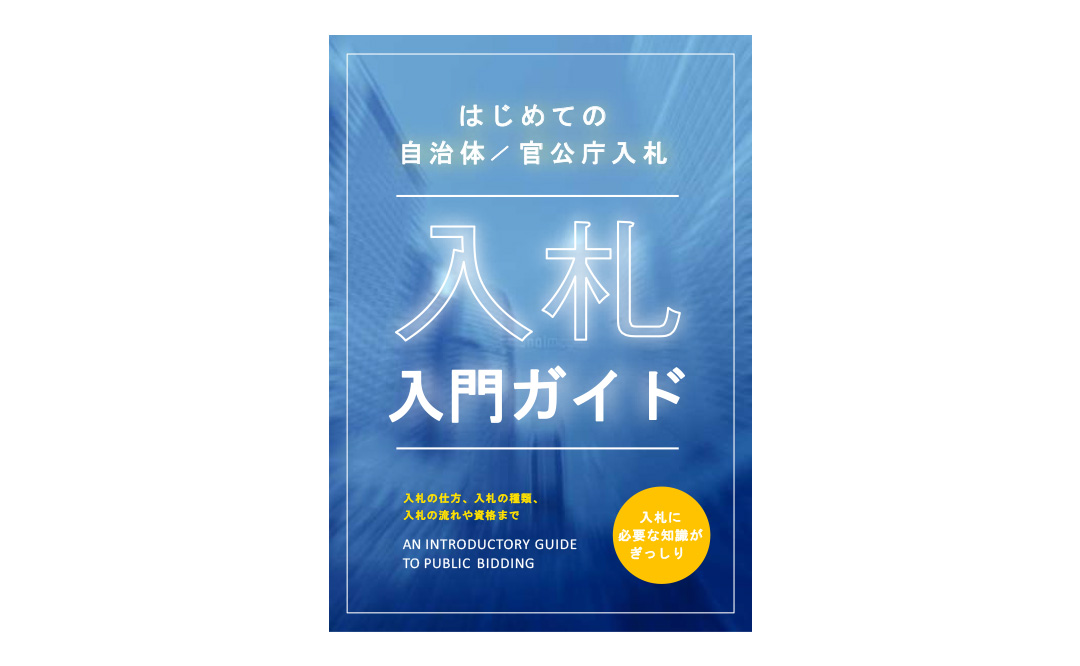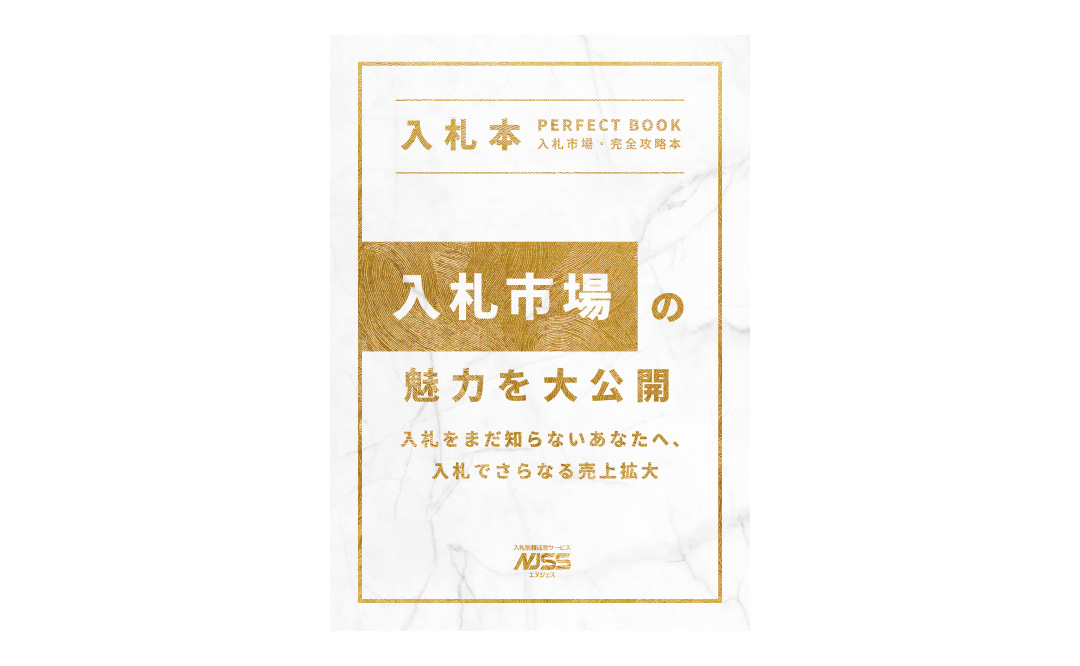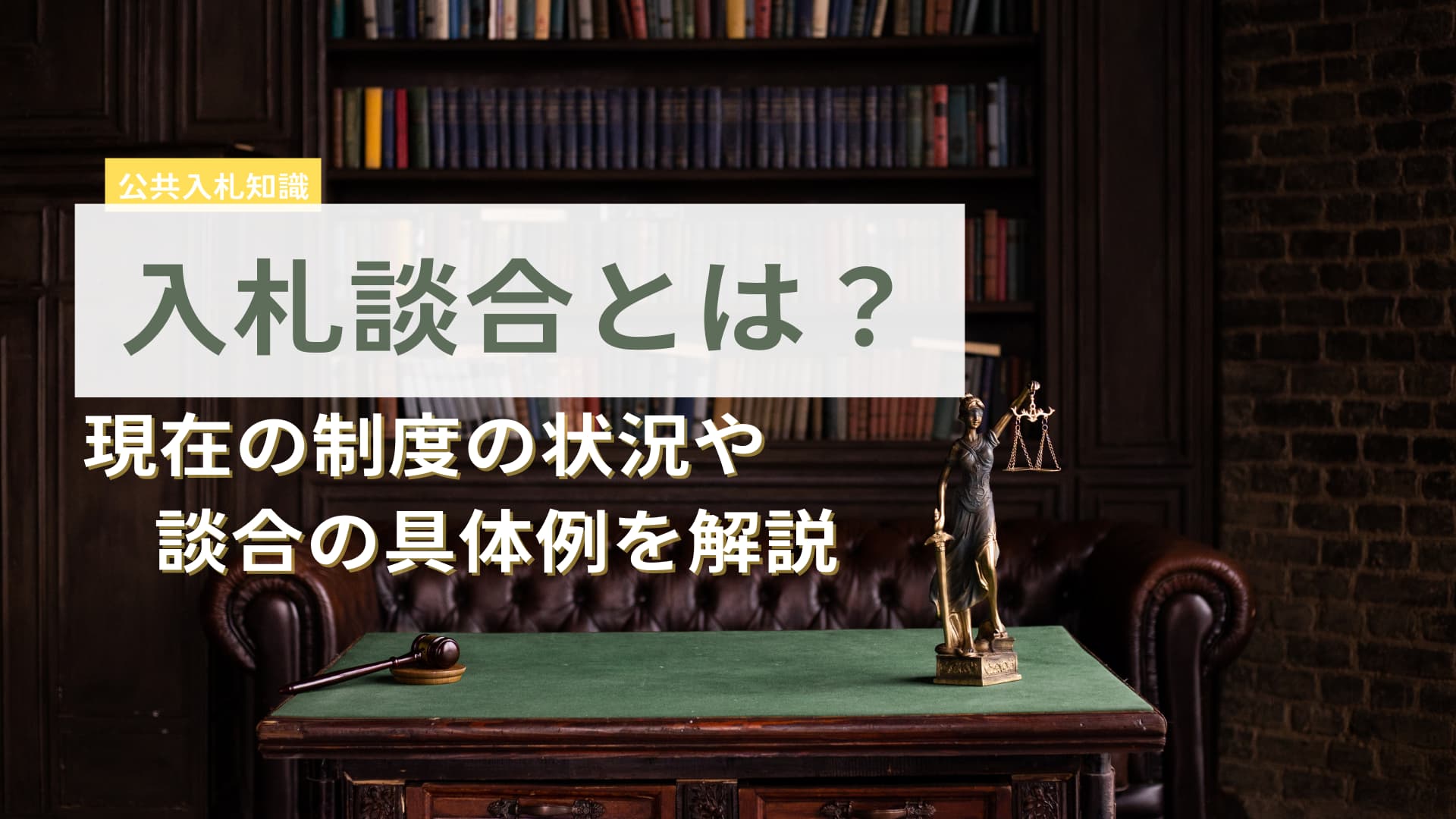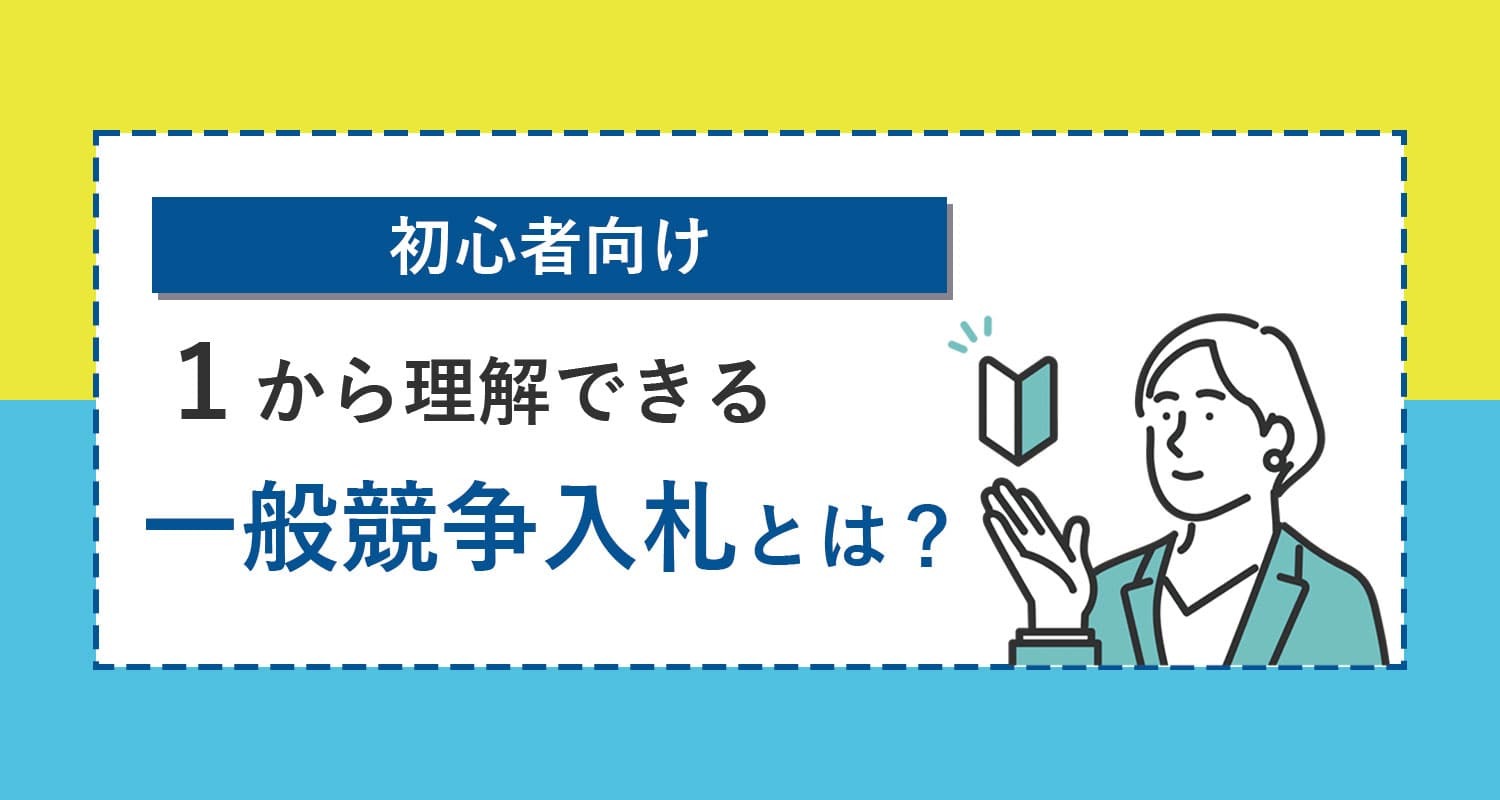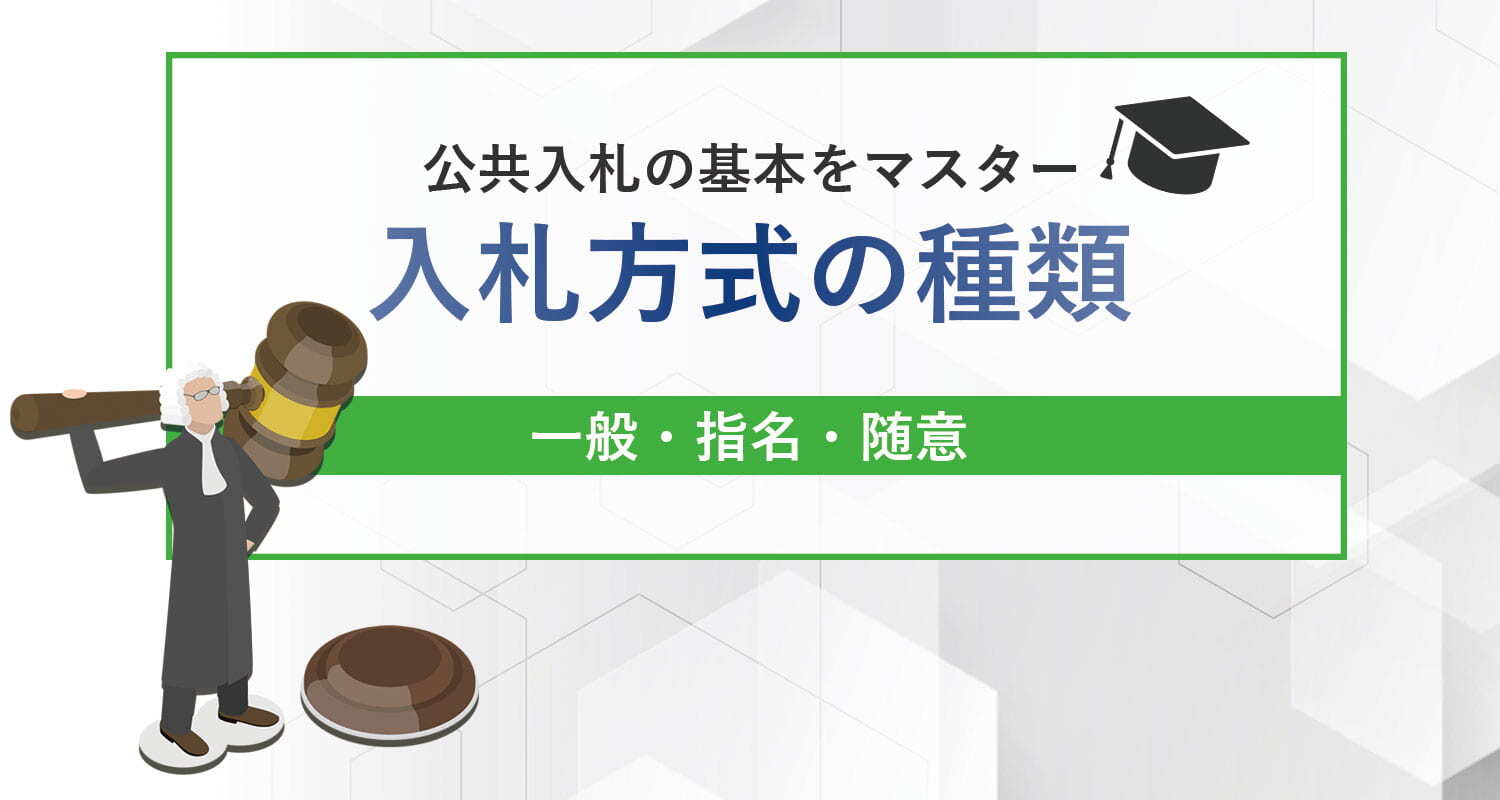- 指名停止処分とは一定期間の入札参加資格を停止する措置
- 処分期間は違反内容によって異なり、他の発注機関にも波及する可能性がある
- 処分理由は多岐にわたり、虚偽記載、契約不履行、談合、法令違反などがある
指名停止処分は、事業者の不正行為や契約違反などを理由に一定期間その企業を入札の対象から除外する措置です。
本記事では、指名停止処分の基本的な仕組みや対象となる行為、処分期間の例、企業側への影響について、制度的な側面からわかりやすく整理しています。
入札に関わる方は、リスク管理の観点からもぜひ確認して役立ててください。
もくじ
指名停止処分とは?
発注機関による入札資格の一時停止措置
指名停止処分とは、公共機関や自治体などの発注者が、特定の事業者に対して入札への参加資格を一定期間停止する措置です。自治体によっては、「入札参加資格停止処分」や「契約に係る参加資格の停止」など、異なる名称が用いられていますが、実質的な内容は同様です。
指名停止処分は、「指名競争入札」における指名を見送るだけにとどまらず、直接または間接的に一般競争入札や随意契約を含むあらゆる契約形態への参加が制限される場合が一般的です。
たとえば、東京都では「東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」によって、資格停止処分の対象となった事業者に対して、一般競争入札・指名競争入札における競争入札参加資格確認申請の受付・結果の通知、随意契約における競争見積依頼を行ってはならないとされています。
そのため、処分期間中は特命随意契約以外の契約方法ができないことになります。
出典:東京都電子調達システム
国の機関の場合は、発注機関ごとに「指名停止等措置要領」により指名停止措置の運用がなされています。
例えば、厚生労働省の「工事請負契約指名停止等措置要領」では、工事の請負契約のため指名を行う際(指名競争入札)に当該業者を指名してはならないこと、特命随意契約を除く随意契約の相手方としてはならないことが記載されています。
出典:厚生労働省「工事請負契約指名停止等措置要領」
一般競争入札への参加については、各業務の入札公告にて「○○省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。」と条件設定されることで事業者指名がない一般競争入札にも参加ができないようになっています。
指名停止期間中は、処分を行った発注機関の入札参加(要綱により随意契約も含む)ができなくなるほか、ある発注者の指名停止処分の情報を基に、他の発注機関も事実関係を確認のうえで同様の処分が課す可能性があります。
指名停止の期間
指名停止処分の期間は、違反の内容やその悪質性、発注者への影響度に応じて決定されます。
各自治体の要綱で基準が定められており、処分期間は数か月から最長で2年程度に及ぶ場合もあります。
たとえば、東京都の「競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」では、違反行為の類型に応じて以下のような基準が示されています。
- 贈賄や談合等の不正行為:原則として12か月(情状により6〜24か月)
- 入札書や契約書類への虚偽記載:原則6か月(情状により3〜12か月)
- 契約違反(工期遅延、仕様不適合等):原則3か月(情状により1〜6か月)
- 粗雑工事・著しい施工不良:原則6か月(情状により3〜12か月)
期間の長短について、例えば東京都発注業務に係る事案であれば処分期間が長くなり、他自治体での事案であれば東京都発注業務での事案と比較すると短くなります。
なお、実際の処分期間は、当該企業の過去の指名停止歴、社会的影響の大きさ、是正措置の有無などを総合的に勘案して決定されます。
営業活動全般の制限ではない
指名停止はあくまで「発注機関との契約行為」に関する制限であり、事業者の営業活動そのものが法律で禁止されるわけではありません。
したがって、処分期間中であっても、民間企業との取引や、他の非該当機関との業務遂行は可能です。
ただし、処分の原因となった事案が法令違反や重大な不誠実行為を含む場合は注意が必要です。
たとえば、建設業者が談合や粗雑工事により指名停止を受けた場合、建設業法に基づく営業停止処分や建設業許可の取消しといった、別途の行政処分が行われる可能性があります。
また、医療機器業者が医薬品医療機器等法違反で処分を受けた場合も、厚生労働省所管の業法に基づく制裁が加えられることがあります。
このように、指名停止処分は自治体など発注者による独自措置ですが、その背景に法令違反がある場合は、業法・監督官庁による行政処分や刑事処分と重なるケースがあることを理解しておく必要があります。
主な処分理由と基準
指名停止処分は発注機関が定める要綱等に基づき行われます。
ここでは、実際にどのような行為が処分の対象となるのか、東京都の「競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」を例に代表的な処分理由を解説します。
入札関係書類への虚偽記載
一般競争入札や指名競争入札において、参加資格確認申請書や価格調査資料などに虚偽の記載をした場合、指名停止処分の対象となります。電子入札での虚偽入力も同様です。
契約履行成績不良等(粗雑工事等)
契約履行における施工不良や著しく低い成績評価(たとえば40点未満など)があった場合、業務履行に際し知り得た秘密を漏えいさせた場合などにも、処分が行われます。
安全性や品質への配慮に欠ける行為は、都民への影響が大きく、厳格に扱われます。
契約不履行
契約を締結したにもかかわらず、正当な理由なく履行しない、または履行を放棄した場合は、発注者の信頼を大きく損ねる行為として処分対象になります。
贈賄
発注機関の職員やその関係者に対して金品を渡すなどの贈賄行為を行った場合は、逮捕や起訴を問わず、長期の指名停止となる可能性があります。
特に法人の代表者などが関与していた場合は、最長で36か月の処分が科されることもあります。
独占禁止法違反
私的独占や不当な取引制限(いわゆる談合)など、独占禁止法に違反した場合も処分の対象です。
東京都発注案件での談合であれば、最大24か月の指名停止措置が課される可能性があります。
入札妨害
他社の入札を妨害する行為(虚偽の苦情申立て、誹謗中傷、脅迫など)や、秘密情報の不正入手なども処分対象に含まれます。発注機関の公正性や透明性を損なう行為として、重く扱われます。
不正行為等
労働基準法、税法、建設業法などの法令違反、または逮捕・起訴に至るような重大な不祥事があった場合も、契約相手方として不適切と判断され、指名停止が行われることがあります。
このように、指名停止処分の対象となる行為は多岐にわたります。処分期間も、軽微な違反で1か月から、重大な法令違反では24か月以上に及ぶこともあり、企業活動に与える影響は小さくありません。
したがって、日々の契約履行においては、形式的なルール遵守にとどまらず、社会的信用を損なわない行動が求められます。
処分を受けた場合の影響
指名停止処分を受けた企業は、処分を行う発注者が実施する入札に参加することができませんが、このことによる影響を整理して解説します。
入札機会の喪失による売上減
最大の影響は、公共調達案件への参入機会が閉ざされることによる売上機会の減少です。
特に、売上に占める官公需の割合が高い企業ほど、経営に与える影響は深刻です。
他の行政機関にも処分が波及
指名停止処分の効力は、処分を行った発注機関に限定されます。しかし、各省庁・自治体は他機関の処分情報を入手した後、各々の指名停止処分基準に照らし別途指名停止処分を課す場合があります。
たとえば、国の機関で処分を受けた企業が、都道府県や市区町村でも同様に入札除外されるケースがあるため、実質的な影響範囲は広範です。
企業イメージの毀損
指名停止は、社会的な信用に関わる行政処分であり、公表によって企業のイメージが毀損することは避けられません。
これにより、既存の取引先との関係性が悪化したり、新規の契約機会において不利になる可能性も考えられます。
復帰後も評価に影響
処分期間が満了し、再び入札に参加できるようになった場合でも、直近で処分歴がある企業として見られることは避けられず、過去の評価が影響を及ぼす場合があります。
特に総合評価落札方式などでは、企業の信頼性や過去の実績が加点要素となるため、処分歴のある企業は不利に働くおそれがあります。
指名停止を防ぐ3つの対策
指名停止処分は、一度科されると一定期間、公共調達からの受注機会を失うことになり、企業経営に大きな影響を及ぼします。特に、公共工事や物品納入を主要業務とする企業にとっては、売上の大幅減や企業イメージの毀損にもつながりかねません。
このような事態を未然に防ぐためには、企業としての予防的な取り組みが不可欠です。具体的には、日常的な法令順守や施工管理だけでなく、事業戦略や営業方針そのものにも目を向けたリスクマネジメントが求められます。
ここでは、特に重要とされる3つの対策を紹介します。
法令順守と社内コンプライアンスの徹底
まず基本となるのが、関係法令の正確な理解と社内におけるコンプライアンス体制の構築です。
独占禁止法、入札契約適正化法、地方自治法その他発注機関ごとに定める要綱など公共契約に関連する法令は多岐にわたり、違反行為が確認された場合には指名停止の対象となることがあります。
特に注意したいのが、入札とは直接関連がない事象であっても、社会的信用を著しく失ついし契約相手として不適切と判断されれば、指名停止の可能性がある点です。
例えば東京都の「競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」では、「有資格者である個人、有資格者である法人又はその法人の役員若しくは使用人が、次の各号に掲げる法令(筆者註:各種税法、業法)違反の容疑等により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合で、社会的信用を著しく失ついしたと認められる場合」は最長9か月の指名停止と規定されています。
出典:東京都電子調達システム
そのため、社員一人ひとりが自社の事業と関連する法令を理解し行動できるよう、定期的に研修を実施したり、抑止策として内部通報制度等を整備することが重要です。
安全・品質管理の強化
公共工事や役務提供において、重大な事故・トラブルが発生したり施工不良が判明した場合、それ自体が重大な信頼毀損とみなされ、指名停止の対象となることがあります。
このようなリスクを回避するには、社内で品質確保体制を強化することが重要です。
必要に応じ外部の助言を受けるなど、多面的な品質・安全確保の仕組みを構築することが有効です。現場任せにせず、全社的なリスク管理の視点が求められます。
無理な案件受注を避ける
上記①②で挙げた事態が発生する背景には、リソースや技術が不足したまま無理に案件を受注してしまう場合があります。
「売上確保のために無理をして落札」した案件が、後にトラブルを引き起こし、売上を上回る損失が発生してしまうことさえあります。
多くの自治体では、「業務遂行能力を欠く行為」や「契約履行の放棄」も処分理由とされています。自社の施工体制・人員体制・外注先の管理体制などを客観的に見直し、引き受け可能な業務範囲を明確にしたうえで入札・提案を行うことが重要です。
まとめ
指名停止処分(入札参加資格停止処分)は、企業にとって極めて重大なリスクであり、特に公共調達の比率が高い企業ほど影響は深刻です。
処分を受けると、一定期間にわたり様々な発注者からの受注機会が減り、売上の低下だけでなく、その後の受注活動にも大きな影響を及ぼします。
指名停止処分の背後には、どこかで起こるべきでない事象が発生しています。
指名停止処分が発生しないことが社会にとっても望ましいといえます。
しかしながら、ある企業の入札参加資格が停止されるということは、またある企業にとっては特定分野の競合が減り、新たな参入機会が生じるという側面もあることも事実です。
実際のところ、官公庁入札に挑戦する際は指名停止処分の状況を含む競合企業の動向を把握することも重要です。入札で戦略的に受注していくためには、競合企業の参加見込みを検討したり、類似案件での競合企業の応札価格を調査することで「いくらで応札すれば落札の可能性があるか」を分析することが重要であるからです。
こうした競合企業のリサーチにおすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。
全国8,900以上の官公庁・自治体の発注情報を網羅しており、過去の入札案件や落札企業の傾向、処分履歴を確認するためのデータベース機能が提供されています。
NJSSを活用することで、競合企業の行動パターンや市場の変化を把握し、より的確な入札戦略を立てることが可能です。
官公庁入札で持続的に成果を出すためには、リスク管理と情報収集が欠かせません。指名停止処分を含む競合企業の動向を広く情報収集し、戦略的に活用していくことが重要です。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上