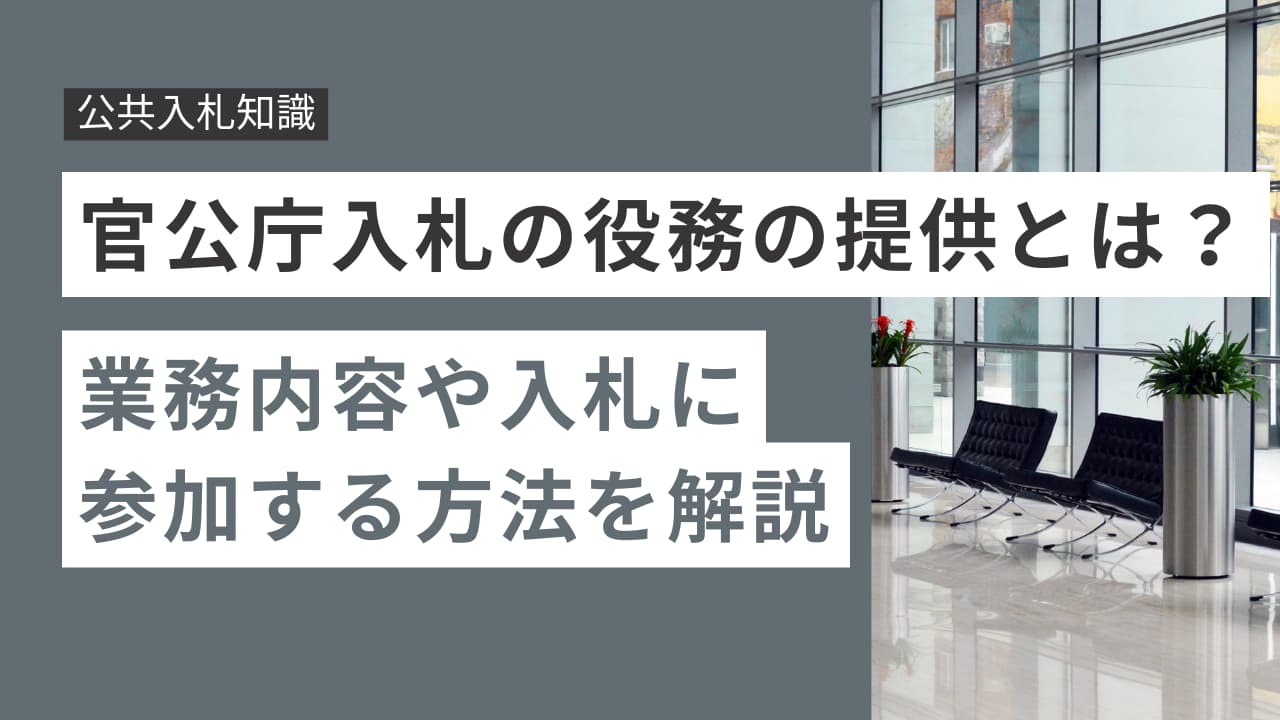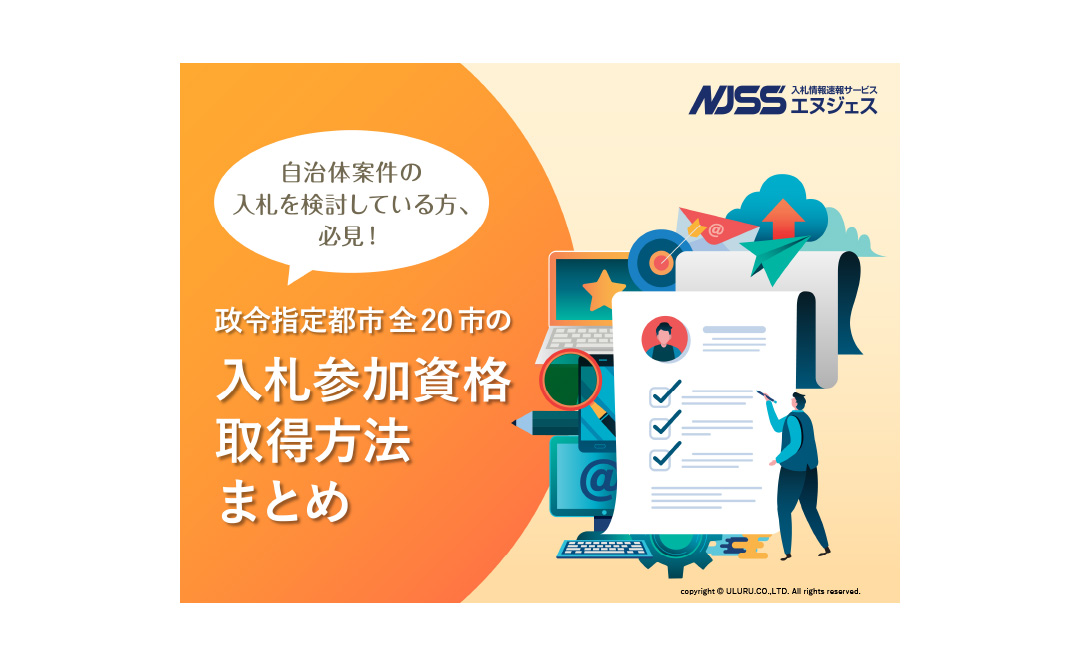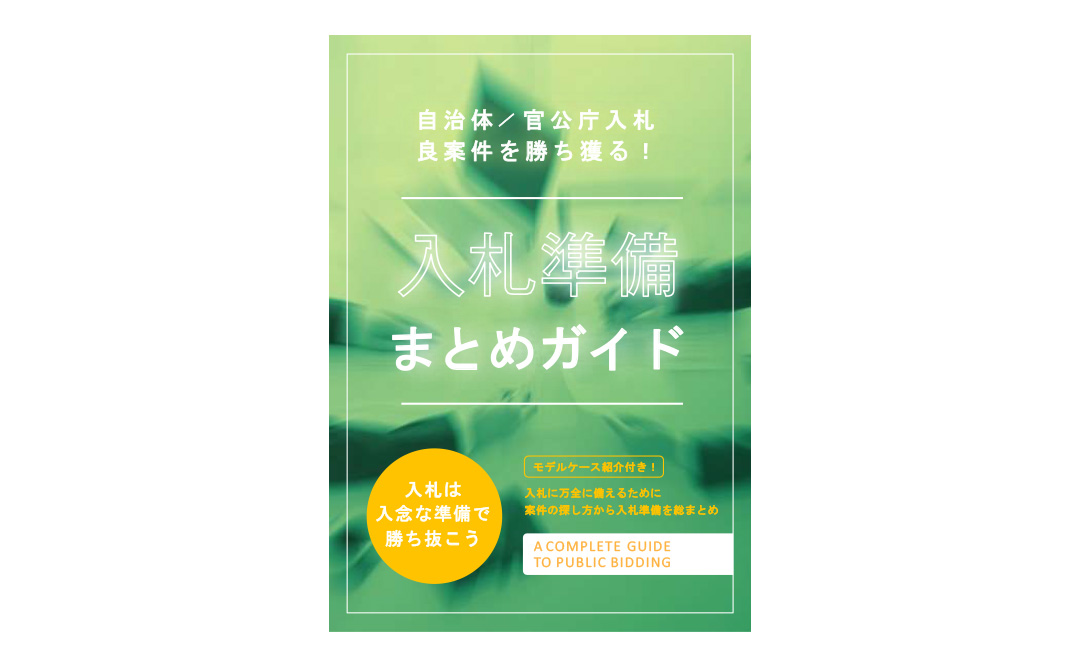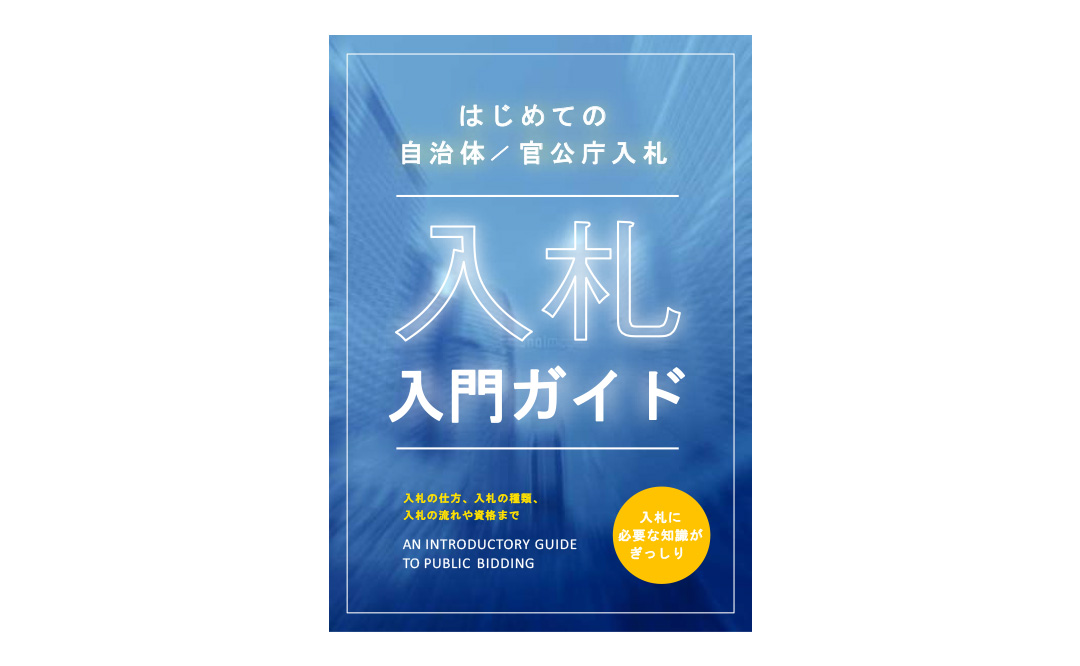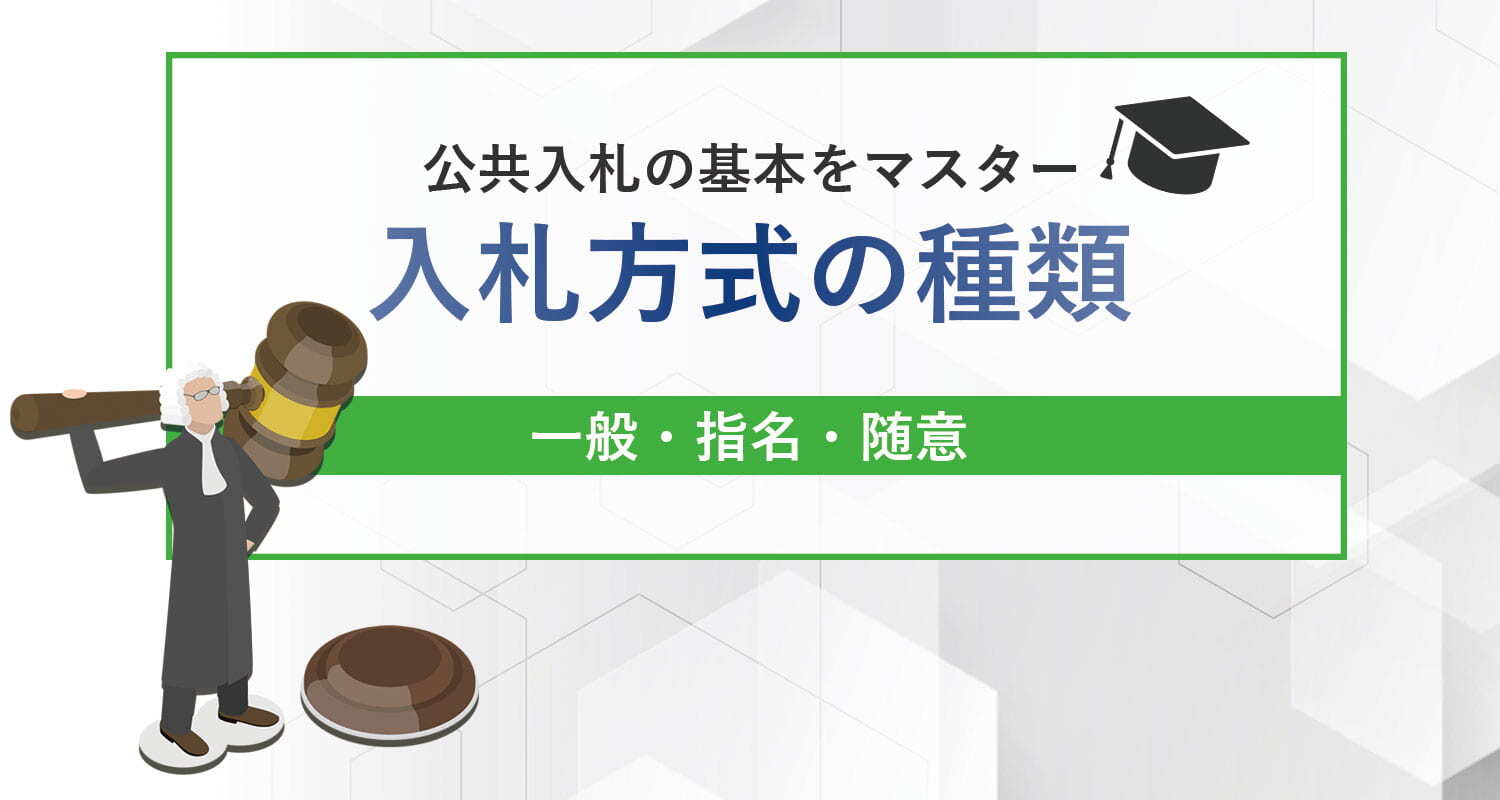- 役務の提供とは幅広いサービスを対象とした入札区分
- 物品の納入や工事と異なり、人が行う労働やサービスの提供を指す
- 具体的には、システム開発、清掃、警備、BPO、研修など多岐にわたる業務が含まれる
- 役務の入札に参加するには、国や地方自治体ごとに「物品・役務」の入札参加資格が必要
国や地方自治体が実施する入札にはいくつかの区分がありますが、その中でも「役務の提供」は幅広い業務を対象としています。システム開発や研修、清掃、警備といったサービスの提供がこれにあたり、民間企業にとって新たなビジネスチャンスとなる分野です。
もっとも、入札に参加するには発注機関ごとの資格申請や案件情報の収集が必要であり、仕組みを理解することが欠かせません。
そこでこの記事では、「役務の提供」の入札参加資格の仕組みや参加手続きの流れ、情報収集の方法について詳しく解説します。
もくじ
入札における「役務の提供」とは
官公庁の入札制度では、発注内容によって「工事」「物品・役務」などの区分が設けられています。
その中でも「役務の提供」は、多くの事業者が参加しやすい分野ですが、日常生活ではあまり使わない言葉なので少し分かりにくいかもしれません。
ここでは、まず「役務」という言葉の意味と、入札制度の中での位置づけを確認していきます。
役務の一般的な意味
「役務(えきむ)」とは、物品の納入や建設工事のような有形の成果物ではなく、人が行う労働やサービスの提供を指す言葉です。平易に言えば「他者のために働くこと」「代わりに作業を担うこと」を表します。
たとえば、庁舎の警備業務や清掃業務、情報システムの運用・保守など、成果物そのものよりも継続的なサービスや作業提供が中心となるものは「役務」に分類されます。
入札における役務区分の位置づけ
官公庁が発注する業務には大きく分けて「建設工事」と「物品・役務」という2つの区分があります。
「物品・役務」の区分のうち、「物品の製造」「物品の販売」などの分類の一つが「役務の提供」です。
入札に参加する事業者は、この区分に応じた入札参加資格を有していることが必要です。
入札に参加する事業者は、自社の提供するサービスがどの区分に該当する業務を担えるのかを確認し、適切な資格を取得しておく必要があります。
「役務の提供」以外の入札参加資格の種類
官公庁が行う入札に参加するためには、事業者はあらかじめ「入札参加資格」を取得しておく必要があります。
この資格は、提供する業務の種類ごとに区分されており、事業内容に合致する区分で登録していなければ、対象案件に参加することはできません。
入札参加資格は大きく分けると「建設工事」と「物品・役務」に分類されます。
建設工事
「建設工事」は、道路や橋梁、学校や庁舎といった建物の新設や修繕など、公共工事に関わる案件に参加するための資格です。
さらに建設業法上の業種区分(建築工事業、電気工事業、土木工事業など)に応じた登録が必要となり、工事規模に応じて経営事項審査(経審)の点数や格付けによって参加できる案件の範囲が変わります。
建設工事は大規模事業者から地域の中小事業者まで幅広い層が関わっており、入札参加資格は公共工事に従事するための前提条件となります。
物品・役務
一方で、「物品・役務」は、建設工事以外の幅広い分野をカバーしています。国の機関の入札参加資格である全省庁統一資格では、「物品・役務」の資格は以下の3つに細分化されています。
物品の製造
官公庁が必要とする物品を製造するための資格です。たとえば備品や機器の製造、印刷物の作成などが該当します。
製造能力や品質管理体制が審査対象となり、自社が生産者であることが前提となります。
物品の販売
製造業者だけでなく、商社や販売会社が参加できる資格です。机や椅子といった庁舎用家具、パソコンやプリンターなどのOA機器、消耗品や日用品の供給が典型例です。製造は行わずとも、調達や安定供給ができることが評価されます。
役務の提供等
清掃や警備といったサービス、システム開発や人材派遣、研修や調査など、労務や知識を伴う業務がここに含まれます。本稿における「役務の提供」も、全省庁統一資格ではこの区分を指します。
このように「物品・役務」は製造、販売、サービス提供といった形態ごとに整理されており、事業者は自社の業務に合った区分で資格を申請・取得しなければなりません。
資格の区分を誤ると、対象案件に参加できずビジネスチャンスを逃す恐れがあるため、登録時には注意が必要です。
「役務の提供」で行われる入札の具体例
「役務の提供」として発注される業務は幅広く存在します。ここでは代表的な事例を取り上げ、どのようなサービスが官公庁に求められているかを具体的に見ていきます。
庁舎警備業務
官公庁の庁舎や出先機関では、利用者の安全を守り不審者の侵入を防ぐために常駐警備が行われます。
入札案件では、警備員の配置計画、緊急時対応のマニュアル整備、巡回体制などが求められるケースが多く、長期的に契約が結ばれることもあります。
清掃・ビルメンテナンス業務
庁舎や研究施設、教育機関などの公共施設においては、日常清掃や定期的な設備点検を委託する入札案件も見られます。
環境衛生の維持だけでなく、エレベーターや空調設備の保守点検なども含まれる場合があり、専門的な知識や資格が必要とされることも少なくありません。
システム開発・運用保守業務
行政実務で使用する各種業務システムのほか、行政機関におけるICT活用の推進に伴い、システム開発やクラウドの構築・運用といったIT関連の役務の入札が今後より増えていく可能性があります。
単なるシステム導入だけでなく、保守・運用サポートまで含む委託もあります。
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業務
例えば、補助金申請や各種調査業務の事務処理を外部に委託するケースがあります。書類受付から審査補助、問い合わせ対応、集計・報告業務まで一括して外注することで、官公庁の負担軽減を図ることが狙いです。
こうした業務は一定の人員配置とマニュアル整備が前提となり、入札に参加する企業には事務処理能力の高さが求められます。
研修・セミナーの実施業務
職員研修や市民向け講座を専門事業者に委託する事例もあります。研修プログラムの設計、講師派遣、運営サポートなどが対象となり、専門的な知識や実績を持つ企業が受注しやすい分野です。
このように「役務の提供」は、警備や清掃といった物理的なサービスから、システム開発や事務処理支援のような知的業務まで多岐にわたります。
入札に参加する事業者は、自社の強みを生かせる分野を見極め、案件ごとに求められる仕様書や基準に沿った提案を行うことが重要です。
「役務の提供」の入札に参加する方法
役務の提供に関する入札に参加するためには、まず入札参加資格を取得することが必要です。一般的な流れは下記ステップで進みます。
- 資格申請
- 入札参加資格者名簿への登載
- 案件情報収集
- 入札参加
入札参加資格申請と資格者名簿への登載
入札に参加するには、発注機関ごとに入札参加資格申請を行い「入札参加資格」を取得する必要があります。
国、都道府県、市区町村ごとに申請窓口や条件が異なります。参加を希望する機関ごとに申請手続きを行う必要があります。
審査を通過すると、企業は「入札参加資格者名簿」に登載されます。名簿に登録されることで、その機関が発注する役務案件に参加できるようになります。名簿は通常、一定期間ごとに更新されるため、継続して入札に参加するためには定期的な更新申請も欠かせません。
案件情報の収集と入札参加
資格を取得した後は、実際に案件情報を収集し、希望する案件に入札します。案件情報は、各発注機関の公式サイトや入札システムで公表されています。
案件には公告日や参加申込期限、入札実施日などが明示されているため、情報収集は常にタイムリーに行うことが重要です。案件内容(仕様書や業務範囲)を確認し、自社が対応可能かを判断した上で入札手続きを進めます。
「役務の提供」の入札情報を効率的に収集する方法
役務の提供に関する案件情報は、基本的に各発注機関のホームページや入札システムに掲載されています。例えば、国の機関の「物品・役務」に関する入札は、デジタル庁が運営する「調達ポータル」でまとめて確認できます。
しかし、都道府県や市区町村の場合は、国のように一元化された公的システムが存在せず、それぞれの自治体の公式サイトを個別にチェックする必要があります。
そのため、確認対象となる発注機関が多い場合には、情報収集に大きな手間がかかるうえ、案件を見逃してしまうリスクも少なくありません。特に中小企業にとっては、情報収集に割く時間や人員を十分に確保するのが難しいケースもあります。
こうした課題に対して有効なのが、入札情報速報サービス(NJSS)の活用です。NJSSは全国の発注機関の入札情報を自動的に収集しており、自社に関連する条件を設定することで、新着案件をメールで通知してくれる機能があります。
これにより、複数の自治体サイトを個別に巡回する手間を大幅に削減でき、見逃しを防ぐことが可能です。
効率的に入札情報を収集するためには、各発注機関の公式サイトを定期的に確認することに加え、NJSSのような有料情報サービスを併用することが現実的です。
特に役務提供の案件に幅広く参加を検討している企業にとっては、情報収集の効率化が入札機会の拡大につながるでしょう。
まとめ
「役務の提供」は、官公庁が行う入札区分のひとつであり、その範囲はシステム開発や研修業務、清掃や警備など幅広い内容を含んでいます。民間企業にとっては、こうした入札に参加することで安定した契約機会を得られる可能性がある一方、発注機関ごとに入札参加資格を申請し、資格者名簿に登載されなければならないといった手続き上のハードルも存在します。
実際に入札に参加していく上で重要となるのは、効率的な情報収集です。
国の機関や自治体が公開している入札情報は分散しており、すべてを個別に確認するのは大きな負担となります。
こうした課題を解決する手段として有効なのが、NJSS(入札情報速報サービス)の活用です。NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を一元的に検索できるサービスで、従来のように発注者ごとに異なるシステムへアクセスする手間を大幅に削減できます。
NJSSでは8日間の無料トライアルも提供されており、情報収集の効率化を実際に体験することができます。ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上