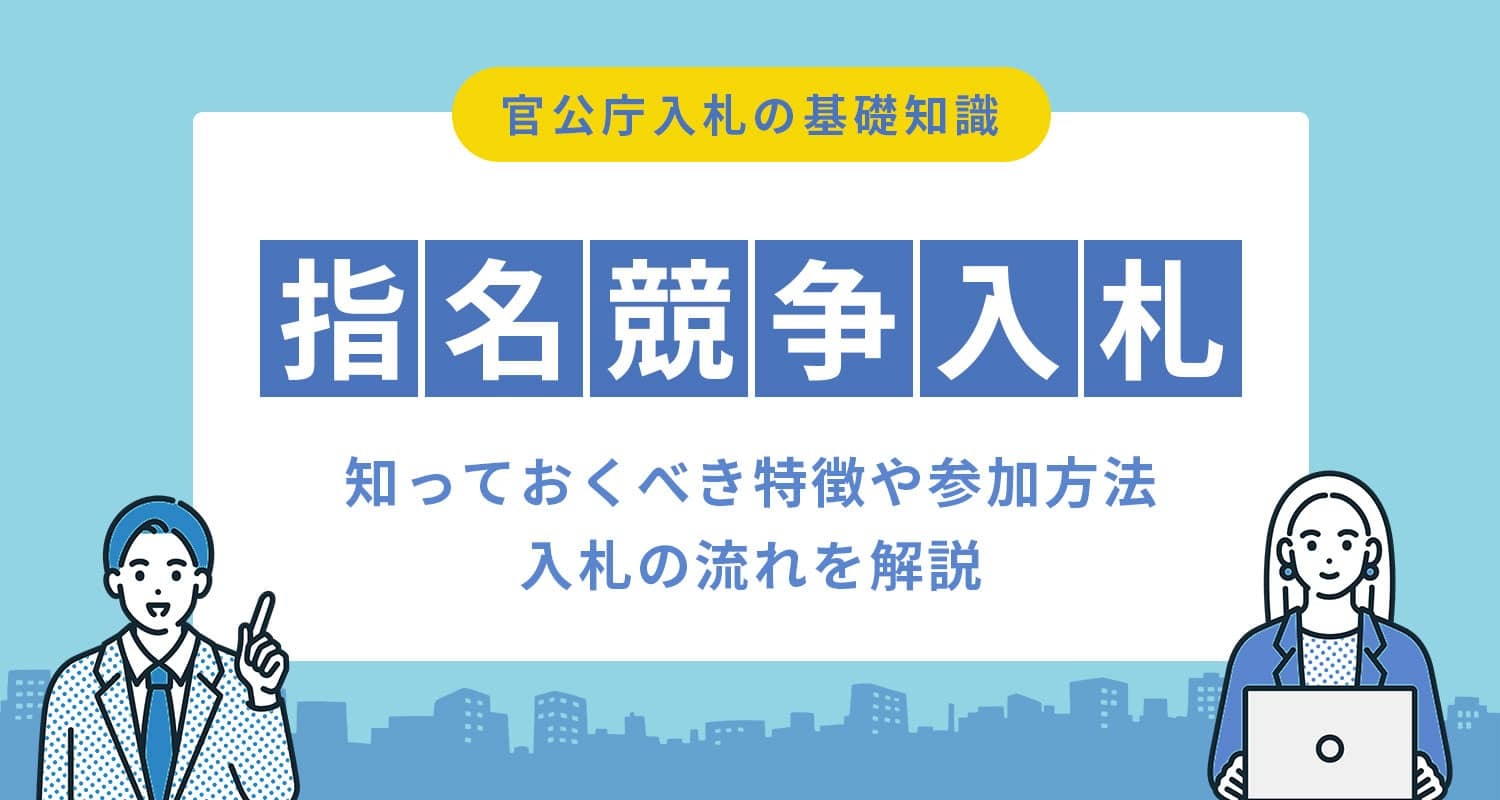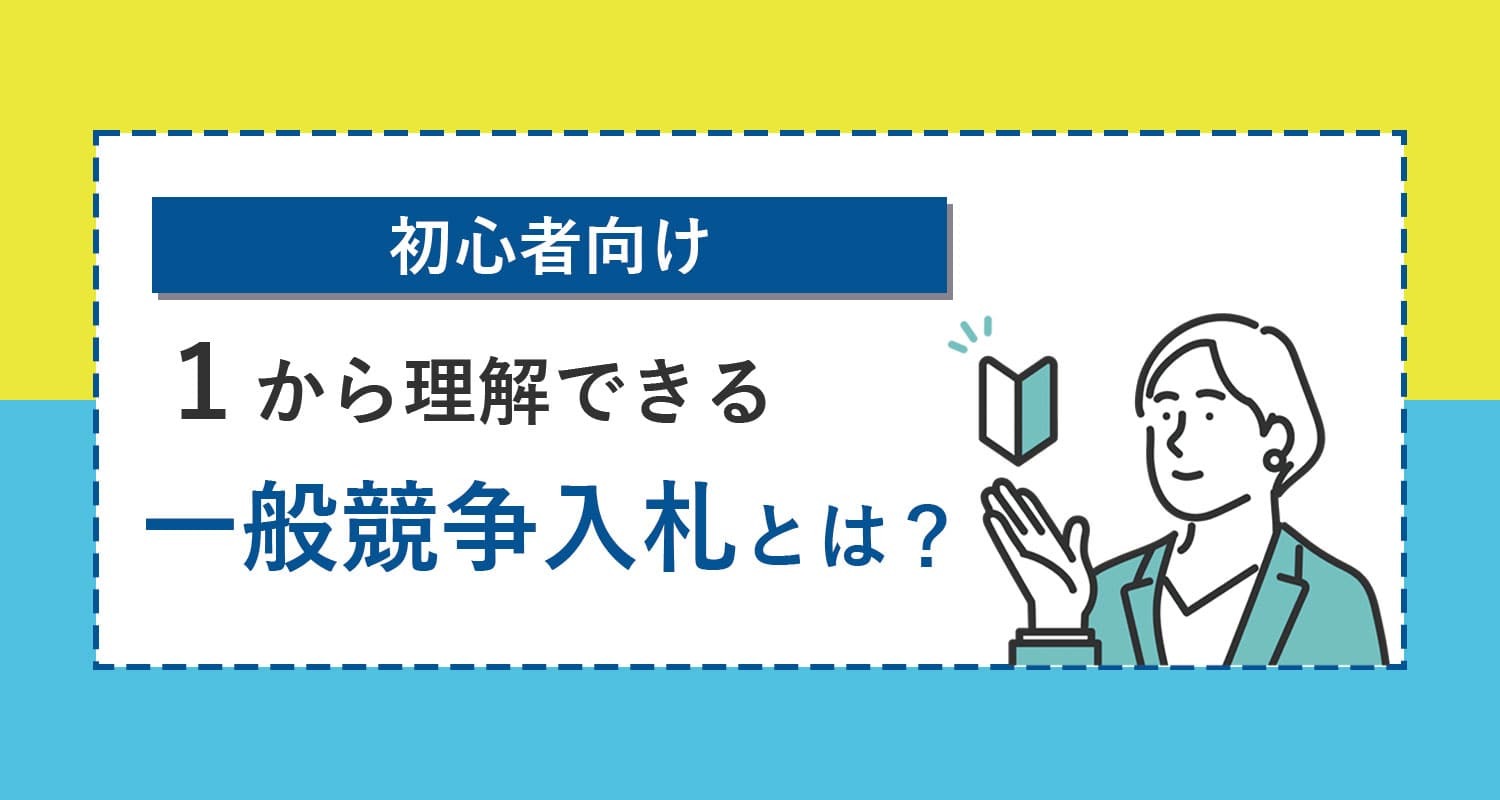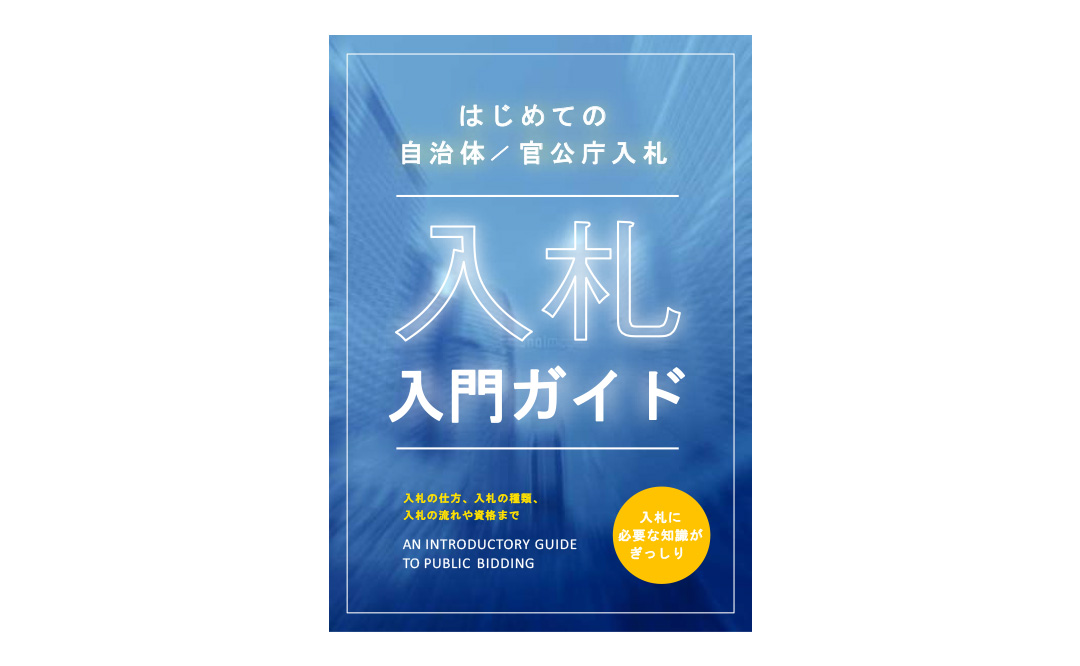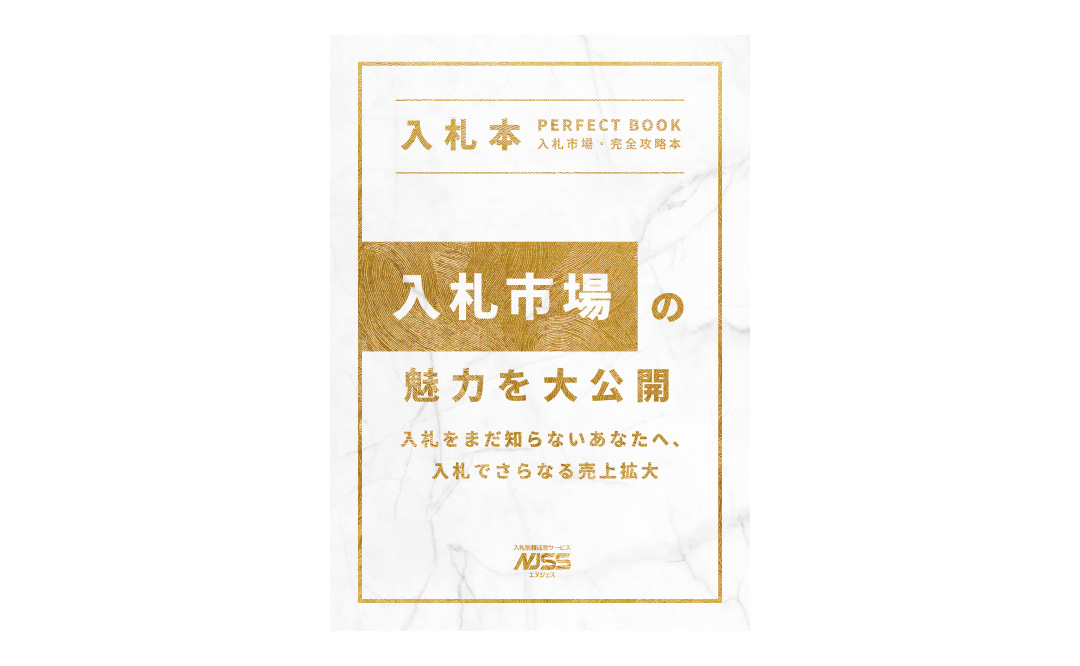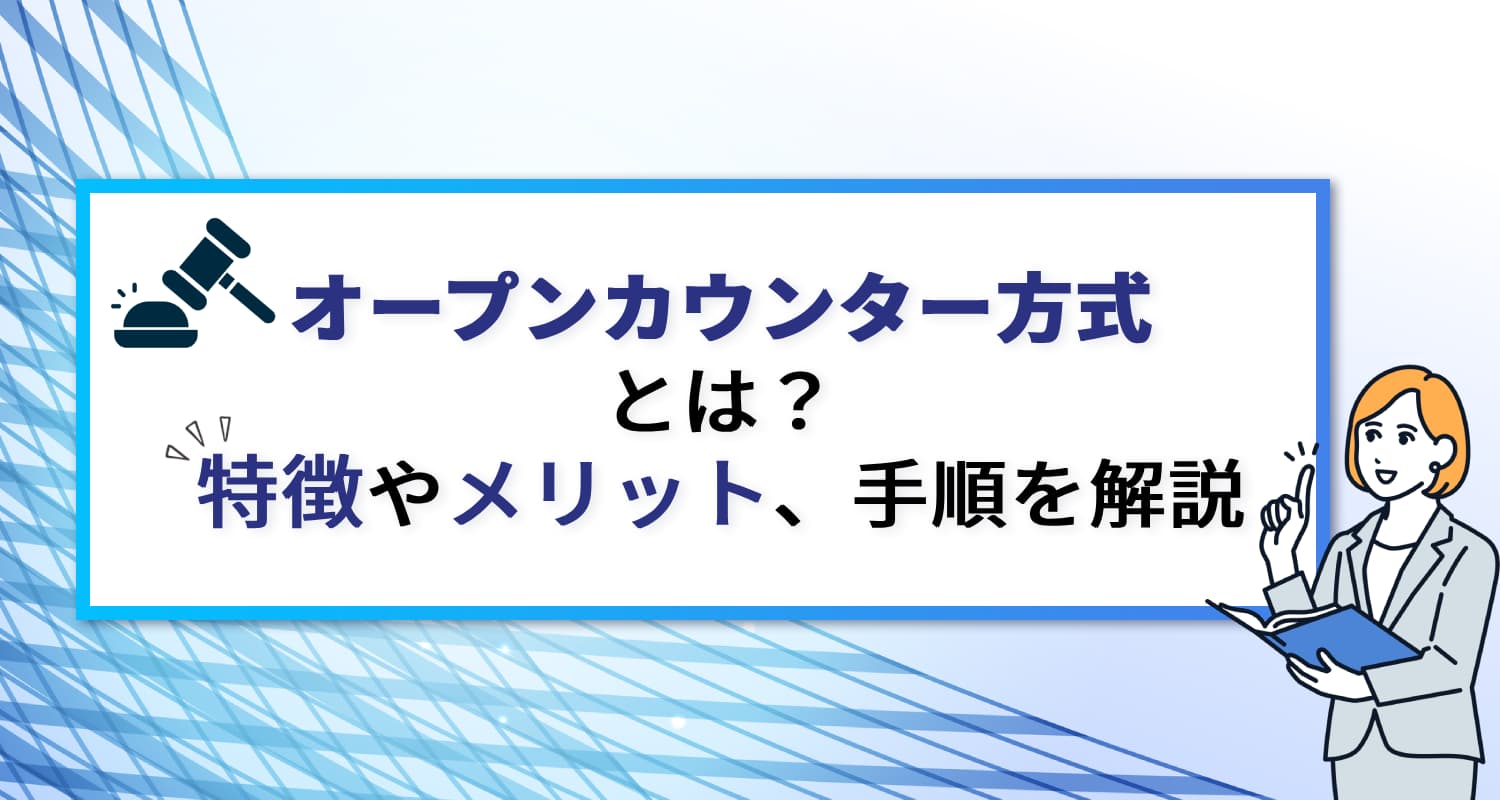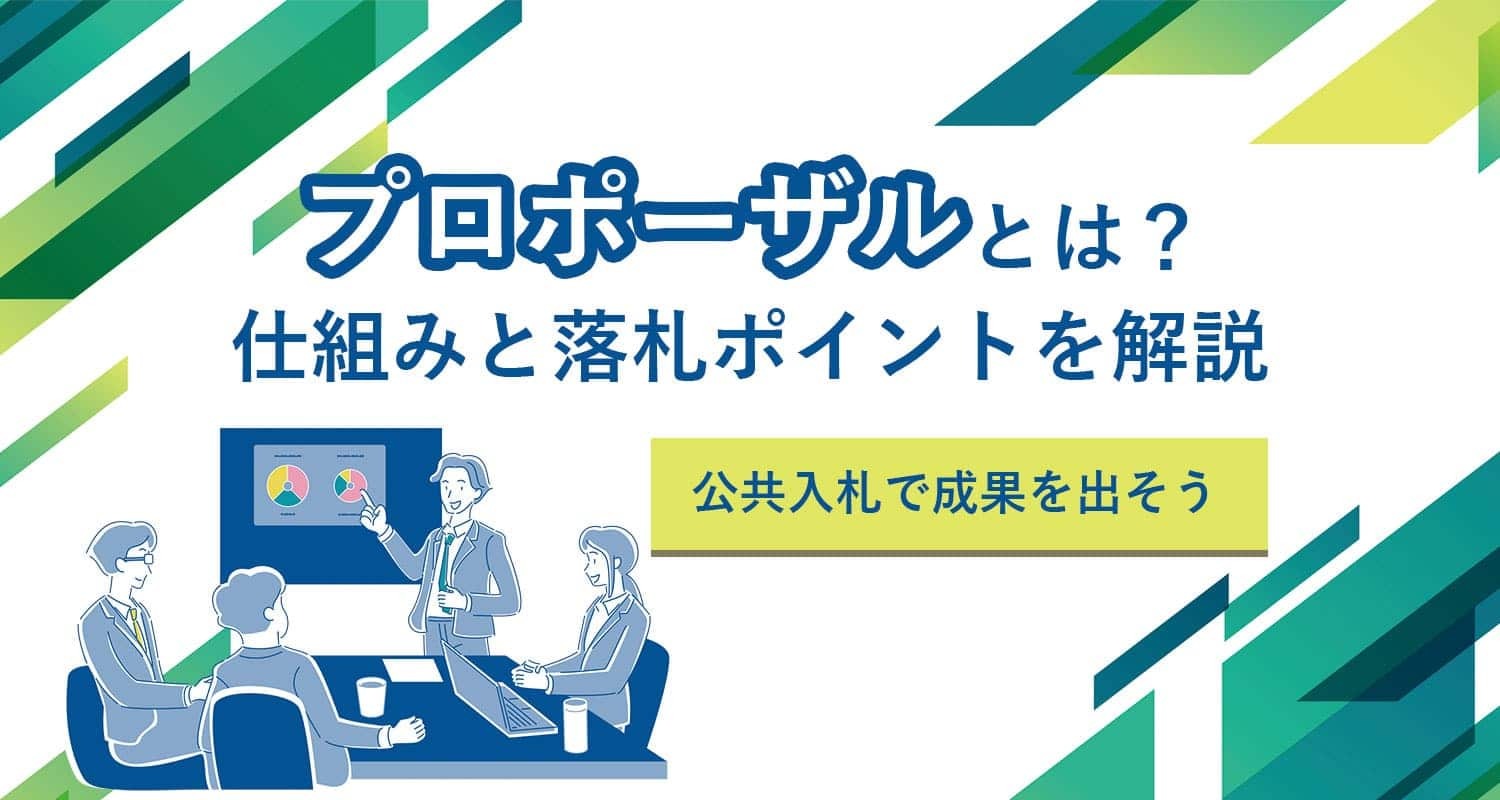公募型指名競争入札とは?指名競争入札との違い・手続きの流れを解説
- 公募型指名競争入札とは、指名競争入札の一種で事前に技術資料を提出することで、誰でも入札に参加できる制度
- 通常の指名競争入札と比べて、発注者の恣意性が入り込む余地が少なく、より公平な競争が期待できる
- 発注者は事業者の技術力や経験を事前に把握できる
官公庁が行う工事・物品の調達は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約に大別されます。
このうち、指名競争入札の一種に「公募型指名競争入札」と呼ばれる方法があります。自治体によっては「希望型指名競争入札」などの名称を用いている場合があります。
公募型指名競争入札は、通常の指名競争入札のデメリットを補うことができ、入札参加を希望する事業者にとってもメリットがある方法です。
この記事では、公募型指名競争入札の概要、他の入札方式との違い、応札者にとってのメリット、手続きの流れなどを詳しく解説していきます。
もくじ
公募型指名競争入札とは
「公募型指名競争入札」とは、発注者が業務の履行に必要な技術力を判断するための資料の提出について公示し、入札参加希望者から提出された技術資料を審査し、指名基準を満たす者を指名して競争入札を行う方法です 。
この「技術資料」とは、工事の場合、同種の工事の施工実績、配置予定技術者、手持ち工事の状況、施工計画等が該当します。資料の作成方法や記載事項の詳細は、案件の公示時に公示文等に記載されています。
公募型指名競争入札は指名競争入札の一種であり、従来の指名競争入札を改良した方式と言えます。
通常の指名競争入札では、入札参加資格者名簿に掲載された事業者の中から、発注者が指名基準に基づき複数の事業者を指名します。この方法では、実績・資力・信用等が十分にある「特定少数」の事業者のみを入札に参加させることができ、発注者にとって業務品質の確保、事務負担の軽減が期待できます。その一方で、指名にあたって発注機関の恣意性が発揮されやすいこと、企業間の自由競争を阻害する等のデメリットが指摘されています。
一方、公募型指名競争入札では、業者の指名に先立って案件の公示が行われます。技術提案書等の必要書類を提出した者のうち、指名基準を満たす業者が指名されます。ただし、発注者によっては、指名基準を満たした業者を全て指名する場合と一定数の業者に絞り込む場合があります。
公募型指名競争入札では、入札への参加が事業者の意思決定に基づくほか、従来の指名競争入札と比較し業者指名の過程で発注者の恣意性が発揮されにくい方法と言えます。
発注機関にとっても、指名前に入札参加希望者の技術力・適正等を資料から判断できるため、指名競争入札のメリットが活かされた方法です。
公募型指名競争入札とその他の入札方式の違い
公募型指名競争入札とその他の入札方式との違いを解説します。それぞれの入札方式の違いを整理すると以下のとおりです。
| 契約方式 | 落札者決定方式 | 案件の公示 | 入札参加方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札 | 価格競争方式 | あり | 参加者による申込み | |
| 総合評価方式 | あり | 参加者による申込み | ||
| 指名競争入札 | 価格競争方式 | なし | 発注者による指名 | |
| 総合評価方式 | なし | 発注者による指名 | ||
| 公募型指名競争入札 | 価格競争方式 | あり | 参加者による申込み | |
| 総合評価方式 | あり | 参加者による申込み | ||
| 随意契約 | 特命随意契約(1者随契) | 地方自治法施行令に掲げる事由 | なし | 発注者による指名 |
| 企画提案方式(プロポーザル) | あり | 参加者による申込み | ||
| 見積り合わせ | 価格競争方式 | なし | 発注者による指名 | |
| 公募型見積り合わせ (オープンカウンター) |
価格競争方式 | あり | 参加者による申込み | |
公募型指名競争入札と指名競争入札の違い
前述のとおり、公募型指名競争入札は指名競争入札を改良した方式です。
通常の指名競争入札で行われる「業者の指名」に先立って案件の公示を行い、入札参加を希望する事業者による技術資料の提出を受け付けます。
通常の指名競争入札は「特定少数」による競争ですが、技術資料提出に関する公募を行うことで「不特定少数(または多数)」での競争となります。
公募型指名競争入札と一般競争入札の違い
公募型指名競争入札と一般競争入札で異なるのは「参加できる者の範囲」です。
一般競争入札は、入札参加資格者名簿に登録し案件ごとの参加資格を満たせば、誰でも参加することができます。
公募型指名競争入札は、発注機関に技術資料等を提出し、指名基準を満たすと判断され指名通知を受けた業者が参加することができます。
なお、通常の指名競争入札は発注機関から指名通知を受けた業者のみが参加することができるため、公募型指名競争入札は「案件が公示される」「参加希望者の意志に基づき参加できる」点で一般競争入札に近い性格があると言えます。
公募型指名競争入札と随意契約との違い
公募型指名競争入札と随意契約の違いは「参加できる者の範囲」と「相手方選定の方法」です。
公募型指名競争入札は発注機関に技術資料等を提出し、指名基準を満たすと判断され指名通知を受けた業者が参加することができます。
一方で、随意契約は発注機関から当該案件に係る見積書の提出等の依頼がなければ契約に至ることはないため、誰でも参加できるものではありません。
また、公募型指名競争入札の落札者は価格競争方式もしくは総合評価方式で決定されるのに対し、随意契約の相手方は価格以外の要素で決定する場合があります。
例えば、既存システムの保守・改修業務は、当該システムを設計・開発した者以外に業務を行える者が存在しないとの理由から随意契約の相手方として選定することがあります。
ただし、複数者による見積り合わせ、公募型見積り合わせ(オープンカウンター)など、価格競争方式で随意契約の相手方を選定する方法もあります。
公募型指名競争入札と公募型企画提案競技の違い
公募型指名競争入札は指名競争入札の一種であるのに対し、公募型企画提案競技(プロポーザル方式)は随意契約における契約の相手方選定方法の一つです。
公募型指名競争入札を含む指名競争入札の落札者は、価格競争方式また総合評価方式(価格以外の要素を加味する方法)で決定するのに対し、公募型企画提案競技の採択者は、事業の実施方針、実施体制、実績などの価格以外の要素で決定されます。
「公募型」とあるように、公募型企画提案競技の案件は公示され、参加希望者の募集が行われる点は、公募型指名競争入札と同様です。
公募型指名競争入札のメリット
公募型指名競争入札のメリットは、通常の指名競争入札制度のデメリットを補完する機能があることです。
具体的には以下の2つが挙げられます。
- 事業者の意思によって参加できること
- 発注者の恣意性が発揮されにくいこと
事業者の意思によって参加できること
公募型指名競争入札のメリットの1つ目は、通常発注者から指名されない限り参加できない指名競争入札に対し、事業者の意志に基づき参加できることです。
通常の指名競争入札制度に対する指摘として、入札参加意欲のある事業者が指名されないことで企業間の自由競争や競争による経済発展を阻害しているとするものがあります。
「十分に対応できる業務であるのに指名されず参加できない」ということがないので、意欲のある事業者にとっては受注機会を失わずに済む方式と言えます。
発注者の恣意性が発揮されにくいこと
公募型指名競争入札のメリットの2つ目は、発注者の恣意性が発揮されにくいことです。
通常の指名競争入札では、発注者が業者指名を通じて、各業者の手持ちの案件状況などから落札者・入札結果を恣意的にコントロールできてしまう恐れがあります。
例えば、実績などからA社に受注して欲しい場合に、手持ち工事が多数ある事業者をほかに多く指名することで、実質的に競争に参加する者をごく少数にすることが出来てしまいます。(そうしたことがないよう、発注者は指名前に行う業者選定委員会で指名理由等の審査・検討を行っています。)
公募型指名競争入札では業者指名に先立って公募することで「不特定多数」の業者が参加する機会があります。そのため、通常の指名競争入札と比較して発注者の恣意性が発揮されにくいと言えます。
公募型指名競争入札の流れ
公募型指名競争入札の流れを解説します。公募型指名競争入札の流れは以下のとおりです。
- 調達案件の公示
- 技術資料の提出
- 技術資料の審査
- 指名通知書の発行
- 入札書の提出
- 開札
- 契約締結
調達案件の公示
国の機関の調達の場合、官報や調達ポータル(省庁等の入札情報提供サービス)に、地方自治体が発注者の場合は、各団体のホームページ(または各団体の入札システム)に案件が掲載されることで公示されます。
技術資料の提出
公募型指名競争入札に参加する場合は、発注者が求める技術資料を作成し提出します。
各発注者が運用する入札システム上に入力する事項もあれば、様式等に必要事項を記載しファイルを添付する場合もあります。
提出する技術資料の内容は、施工実績、配置予定の技術者に関する事項、手持ち工事の状況、施工計画等であり、発注者が定める要領等に基づき規定されています。
技術資料の審査
提出した技術資料を基に、指名基準に照らして審査が行われます。
指名通知書の発行
審査の結果発注者から指名されると、指名通知書が交付されます。
残念ながら指名されなかった場合は、非指名通知書が交付されます。
入札書の提出
指名通知書の発行以降は、通常の指名競争入札と同様です。
定められた入札期間内に入札を行います。
開札
入札が締め切られた後、発注者により開札が行われます。
開札後、落札者には落札者決定通知が交付されます。
契約締結
落札者決定通知が交付された後は、発注機関の担当部局と契約書を締結し、業務を開始することになります。
公募型指名競争入札の案件を調べる方法
公募型指名競争入札に関する公示は官報や、調達ポータル 、各自治体・団体のホームページで確認することができます。
しかし、個々のサイトにアクセスして検索する必要があり、思った以上に時間がかかってしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。
案件の情報収集を効率化したい場合におすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSS なら、国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。
過去の落札情報も閲覧できるため、手間をかけず効率的に情報を集めることができ、豊富な案件から自社にマッチした案件を探すことが可能です。
8日間の無料トライアルがありますので、是非一度、豊富な案件情報に触れてみてください。
まとめ
公募型指名競争入札は、通常の指名競争入札の欠点を補完する入札方式と言えます。
通常の指名競争入札に加えて入札参加者の公募手続きを行うことで、事業者にとっても参入が容易となり、発注者にとっても入札参加者の技術力を担保した上で、不特定多数による競争を行うことができます。
大規模かつ高い専門性が要求される案件であることが見込まれますが、意見招請のほか年度当初の情報公表など慎重な調達プロセスが定められていますので、受注可能性が期待できる案件はチェックしてみることも良いでしょう。
案件の情報収集を効率化したい場合におすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSS なら、国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。
8日間の無料トライアルがありますので、是非一度、豊富な案件情報に触れてみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上