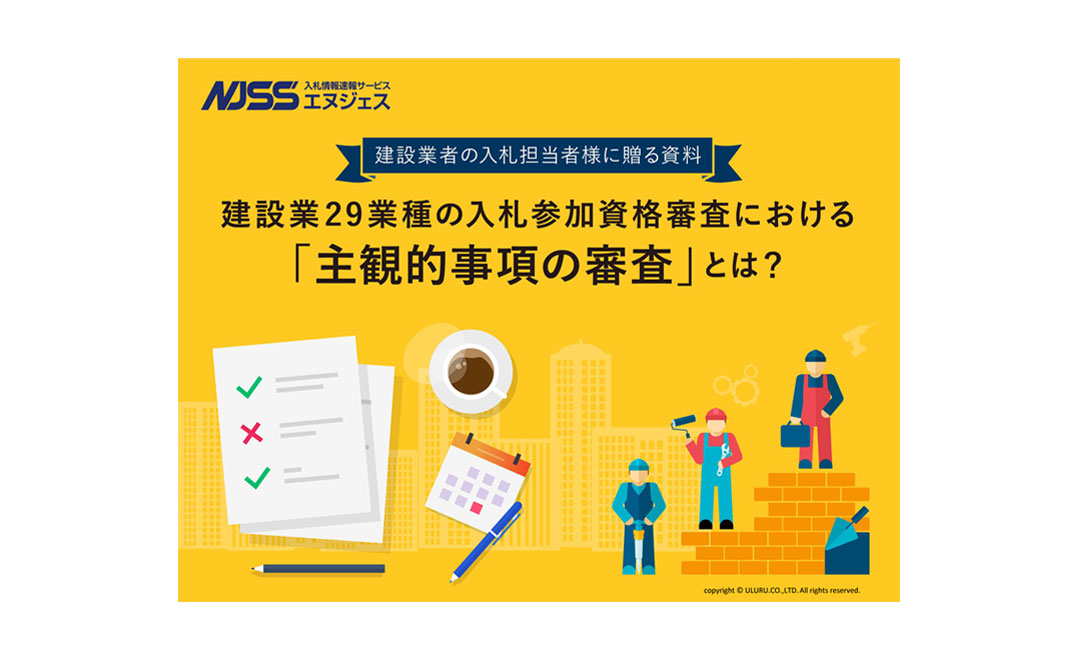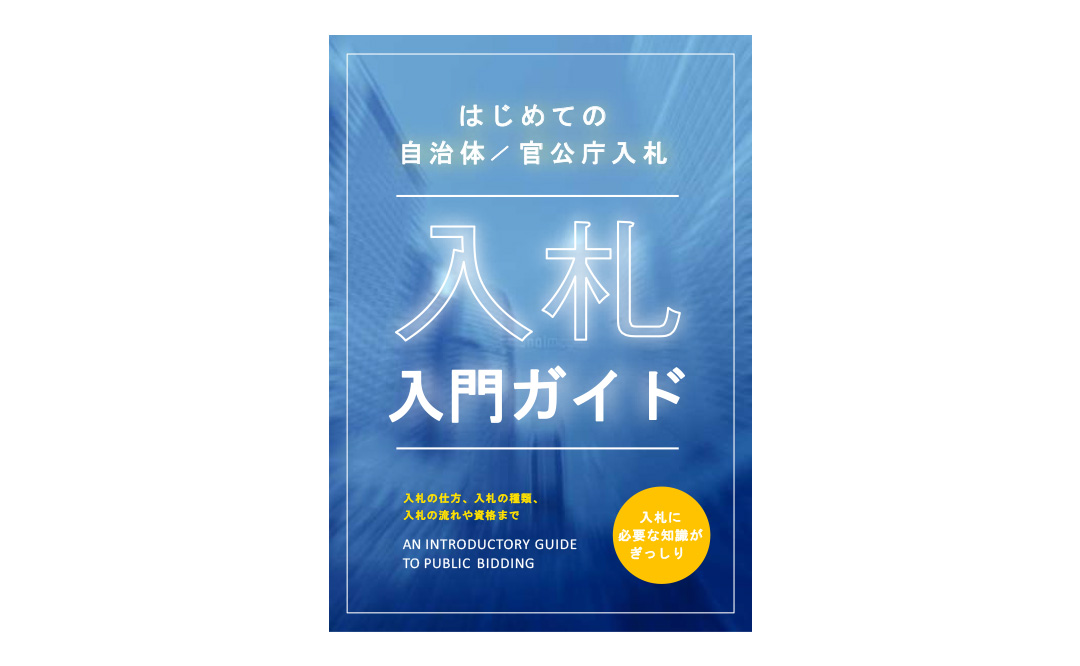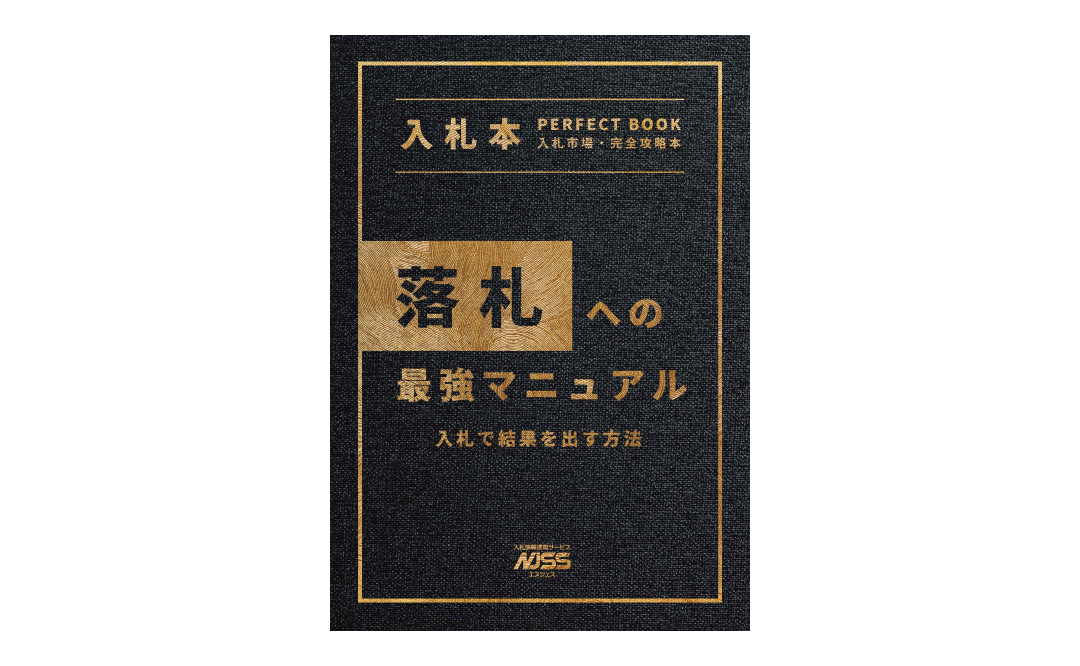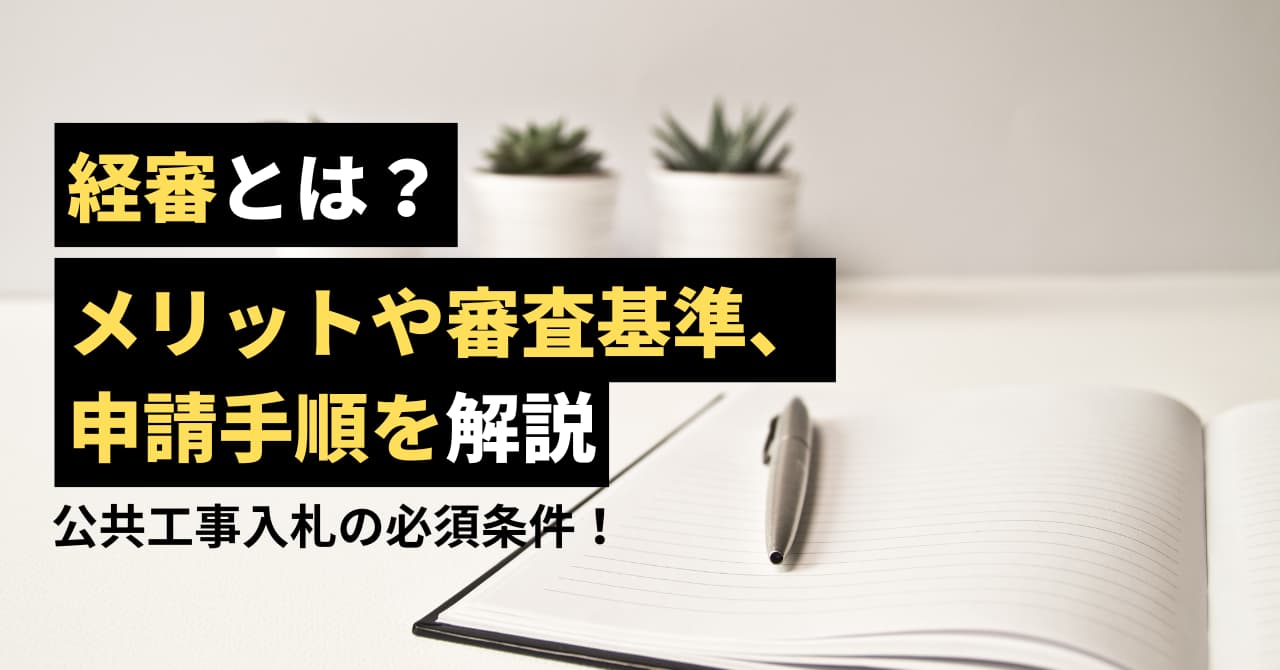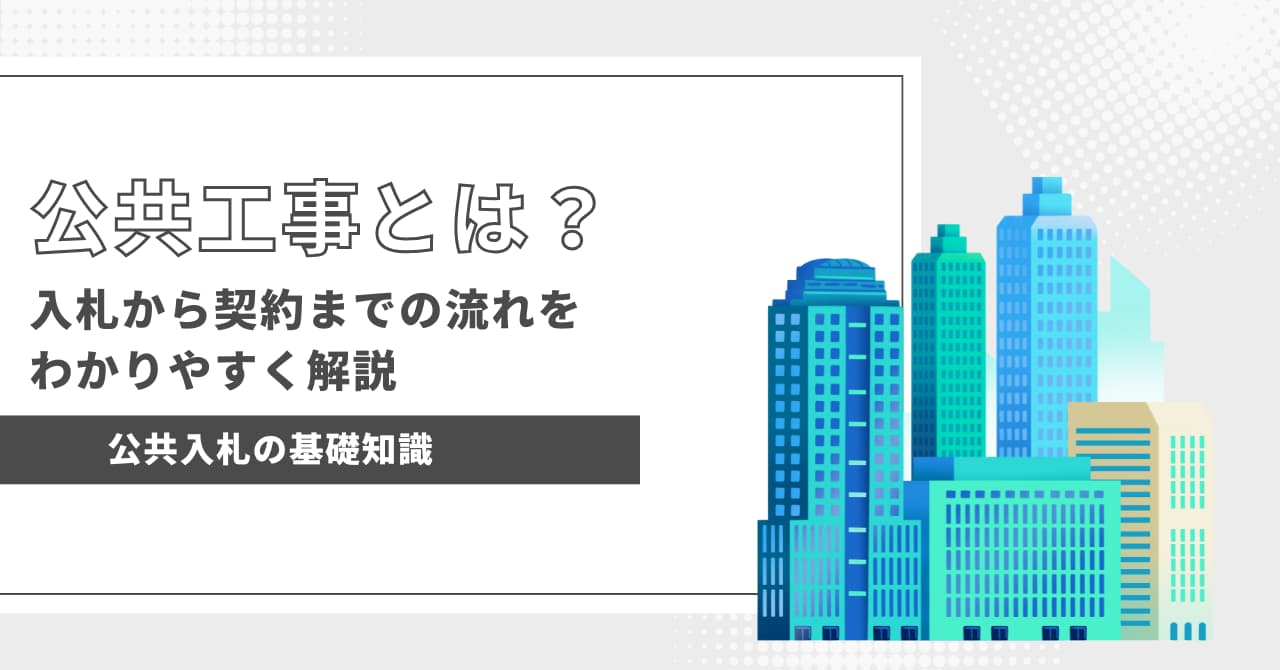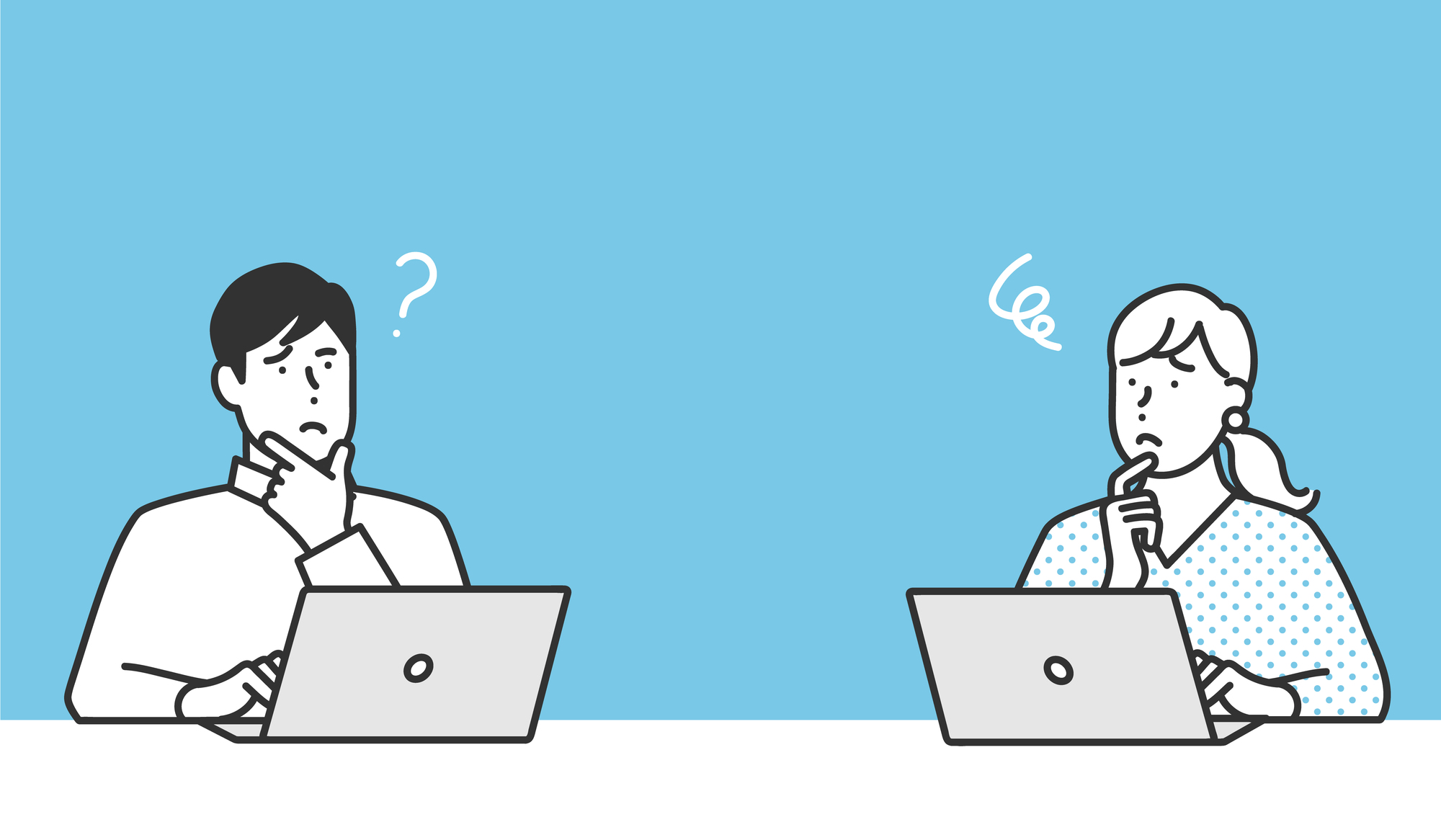- 入札ランクは参加可能な工事規模を示す仕組み
- ランク決定には「経営事項審査(経審)のP点」が重要
- ランク向上にはP点改善と戦略的な取り組みが必要
公共工事の入札において「入札ランク」や「格付け」は、参加できる案件の範囲が決まる重要な要素です。
より大きな工事を受注しようとする場合は、このランクを向上させることを避けて通れません。
この記事では、公共工事の入札ランク制度の仕組みから、経審点数との関係性、そしてランクを向上させるための具体的な方法を解説します。
もくじ
公共工事入札のランク(格付け)制度とは
公共工事の入札に参加する際、企業は「ランク」や「格付け」と呼ばれる制度を通じて、その実力に応じた等級に分類されます。
この制度は、発注機関が調達案件の難易度等に応じて適切な施工業者を選定するため仕組みですが、入札に参加しようとする企業にとっても理解することが重要です。
ランク(格付け)制度の概要
入札における「ランク」とは、発注機関が保有する「入札参加資格者名簿」に登録された事業者をその企業の経営規模や技術力、実績などの実力に応じて等級(ランク)に分類する制度です。
一般的に「格付け」とも呼ばれ、企業が参加できる工事の規模や種類を判断する基準となります。
この制度によって、発注機関は企業の能力に見合った工事への入札参加を促し、工事の品質確保と適正な競争を図っています。
評価対象と見直し頻度
企業がどのランクに位置づけられるかは、様々な評価指標に基づいて決定されます。
主な評価対象としては、「経営事項審査(経審)の結果」が挙げられます。特に、経審の総合評定値(P点)は、このランク付けの根幹をなす客観的な指標となります。
ランク(格付け)は、原則として定期的に見直しが実施されます。発注者によっては参加資格更新申請の時にランクに反映させる場合と、毎年見直す場合があります。
ランクと参加可能な工事規模
公共工事の入札ランクは、企業が参加できる工事の規模を決定づける重要な要素です。
各ランクには、それぞれ入札に参加できる工事の「予定価格の範囲」が定められています。例えば、Aランク企業は数億円規模の大型工事に、Bランク企業は数千万円規模の中型工事に、といった形で区分されます。
一般的に、ランクが高いほど、より大規模で高額な案件への参加が可能となります。
これは、大規模な工事には相応の経営体力や技術力が求められるため、発注者側がリスクを管理し、確実な工事実施を期待する意図があります。
発注機関ごとのランク区分の違い
重要な注意点として、ランク区分やその評価基準は、発注機関によって異なるという点が挙げられます。例えば、ある自治体でAランクに認定された企業が、別の自治体ではBランクとなることもあり得ます。
そのため、入札を目指す発注機関ごとに、その機関の定める格付け制度を事前に確認し、自社の立ち位置を正確に把握することが不可欠です。
経営事項審査とランクの関係
公共工事の入札に参加する建設業者にとって、経営事項審査(経審)はランク(格付け)の計算要素になっている重要な制度です。
経審の点数が、企業のランクを決定する上でどのような役割を果たすのかを理解することは、戦略的な経営に不可欠です。
経営事項審査(経審)がランク決定の土台
公共工事の入札に参加するためには、建設業者は建設業法に基づき経営事項審査を受けることが義務付けられています。
この経審によって算出される「総合評定値(P点)」は、企業の経営状況、技術力、社会性などを総合的に数値化したものであり、各発注機関が企業を入札ランクに分類する際の最も重要な客観的根拠の一つとなります。
P点が高いほど、企業の実力が高いと評価されるため、ランク付けのプロセスにおいて極めて重視されます。
ランク決定における多角的な評価要素
発注機関が企業のランクを決定する際、経営事項審査のP点のみならず、発注者ごとに定める複数の要素を総合的に加味して評価を行います。
これは、発注者別評価点や主観点などと呼ばれています。
具体的には、過去の工事実績、表彰の有無、地域への社会貢献活動の状況、企業の信頼性といった要素が評価対象となることがあります。
これらの要素を経営事項審査の総合評定値(P点)と組み合わせて、最終的なランクが決定されます。
ランク向上と入札機会の拡大
入札参加資格者名簿でのランクは「経営事項審査の総合評定値(P点)」と「発注者別評価点」で決まりますが、合計点数のうち経営事項審査の総合評定値(P点)の方が評価のウエイトが大きい場合が多いです。
そのため、入札機会の拡大を目指す場合は、経営事項審査の総合評定値(P点)の点数を引き上げることを目指すことが基本です。
その上で、加点に必要な費用を鑑みて、発注者別評点で比較的負担なく取得できる認証等にチャレンジすると良いでしょう。
入札参加資格ランクの決定方法と具体例
公共工事の入札参加資格におけるランクは、発注機関ごとにその決まり方が異なります。
主に経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)を基準としつつも、独自の評価基準を加味して企業を分類しています。ここでは、国と地方自治体それぞれのランク決定の概要と例を紹介します。
国の機関におけるランク付けの例
国の機関、例えば国土交通省や農林水産省、防衛省など複数の省庁では、それぞれが独自の基準に基づいて入札参加資格者のランク付けを行っています。これらの機関は、企業が申請した経営事項審査のP点を主要な指標とし、それを一定の点数範囲で区分することでランクを決定します。
例えば、国土交通省関東地方整備局の「一般土木工事」の等級区分は、経審の総合評定値(P点)に応じて、A、B、C、Dといった等級に区分されるのが一般的です。(地方整備局により異なる)
ランク付けに使用する総合点数は、「経営事項審査の総合評定値P点」に工事受注実績を数値化した「技術評価点数」を加えることで算出されます。
◆令和7・8年度関東地方整備局一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」における等級区分
| 等級区分 | 総合点数 | 予定価格 |
|---|---|---|
| A | 3,040点以上 | 8億2,000万円以上 |
| B | 3,040点未満~2,630点以上 | 3億4,000万円以上8億2,000万円未満 |
| C | 2,630点未満~1,660点以上 | 7,000万円以上3億4,000万円未満 |
| D | 1,660点未満 | 7,000万円未満 |
地方自治体におけるランク付けの例
地方自治体においても、都道府県や市町村がそれぞれ独自の入札参加資格ランク(格付け)制度を設けています。
国の機関と同様に、経審のP点を主な評価基準としますが、地域特性や自治体の重点政策を反映した独自の要素が加味されることもあります。
例えば、東京都の建設工事入札参加資格の格付けでは資格審査は、経審のP点を含む「客観的審査事項」と、東京都独自の「主観的審査事項」の審査結果に基づいて業種ごとに等級が決定されます。
東京都の評価制度の重要な特徴として、客観等級と主観等級が算出された際に、両者が異なる場合は「低い方の等級」が最終的なランクとして適用されるという原則があります 。
この原則は、企業が客観的な経営指標で高い評価を得ていても、東京都が重視する主観的な評価項目(例:過去の工事実績や地域貢献活動など)で基準を満たさなければ、上位ランクを獲得できないことを意味します。
したがって、東京都の入札に参加する企業は、財務や技術力といった客観的指標の向上だけでなく、東京都が求める主観的要素への戦略的な取り組みが不可欠といえます。
◆東京都「一般土木工事」の等級算定表
| 客観点数 | 客観等級 | 主観点数 | 主観等級 | 発注標準金額 |
|---|---|---|---|---|
| 900点以上 | A | 2億点以上 | A | 3億5千万円以上 |
| 750点以上 900点未満 |
B | 8000万点以上 2億点未満 |
B | 1億6千万円以上 3億5千万円未満 |
| 650点以上 750点未満 |
C | 3000万点以上 8000万点未満 |
C | 4千万円以上 1億6千万円未満 |
| 600点以上 650点未満 |
D | 700万点以上 3000万点未満 |
D | 1千万円以上 4千万円未満 |
| 600点未満 | E | 700万点未満 | E | 1千万円未満 |
※出典:令和7年3月26日付 東京都公報「特定調達第3185号」より作成
入札参加資格のランクを上げる方法
公共工事の入札において、より高いランクを獲得することは、大規模案件への参加機会を増やし、企業の競争力を高める上で重要です。
ここでは、ランク向上に効果的な具体的な方法を解説します。
完成工事高の実績を積む
完成工事高は、その規模や実績を客観的に示す重要な指標であり、経営事項審査の評価項目(X2点)に含まれます。
また、発注機関によっては、P点以外にも過去の完成工事実績そのものを評価対象とする場合があります。より多くの工事を完遂し、実績を積み重ねることで、企業の施工能力や信頼性が評価され、ランク向上に繋がる可能性があります。
計画的に工事を受注し、着実に実績を積み上げていくことが重要です。
有資格者の採用・定着と従業員キャリアアップの促進
企業の技術力は、保有する有資格者の質と量に大きく依存します。一級建築士などの上位資格者を積極的に採用し、彼らが長く定着できるような職場環境を整備することは、経審の技術力評価(Z点)を直接的に向上させます。
また、既存の従業員に対して、より上位の資格取得を奨励し、キャリアアップを促進するための支援(研修費補助、勉強会の開催など)を行うことも有効です。
従業員のスキルアップは、個人の成長だけでなく、企業全体の技術力向上に直結し、結果として経審点とランクの向上に貢献します。
自治体が政策的に推進する取り組みへの協力
多くの地方自治体は、地域の活性化や社会課題解決のために、特定の政策を推進しています。
例えば、地元企業からの優先調達、環境配慮型建設、バリアフリー化推進、女性活躍推進、災害時協力協定締結などが挙げられます。経営事項審査では、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」がW点で配点があります。
国・自治体が政策的に推進している取り組みに協力し、実績を積むことは、発注機関の主観点評価において有利に働き、ランク向上に繋がる可能性があります。
自社が営業をかける自治体の重点政策を把握し、それに沿った形で貢献する姿勢を示すことが、信頼関係構築と評価向上に結びつくでしょう。
まとめ
公共工事の入札におけるランク制度は、企業が参加できる案件の規模を決定する重要な指標です。
このランクは、企業の経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)を主軸としつつ、各発注機関が独自に定める評価基準に基づいて決定されます。
ランクは定期的に見直されるため、企業は常に経審点数(特にP点)の向上を図り、完成工事高の実績を積む、有資格者の採用・育成に努める、さらには自治体の政策的取り組みに協力するなど、日ごろから経営状況の改善と企業努力に取り組む必要があります。
そして、上位ランクの獲得を検討する場合、上位ランクで受注可能な案件の発注状況、競合の存在を調査しておくことが重要です。
こうした入札情報のリサーチにおすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の入札情報を検索することができます。これ
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上