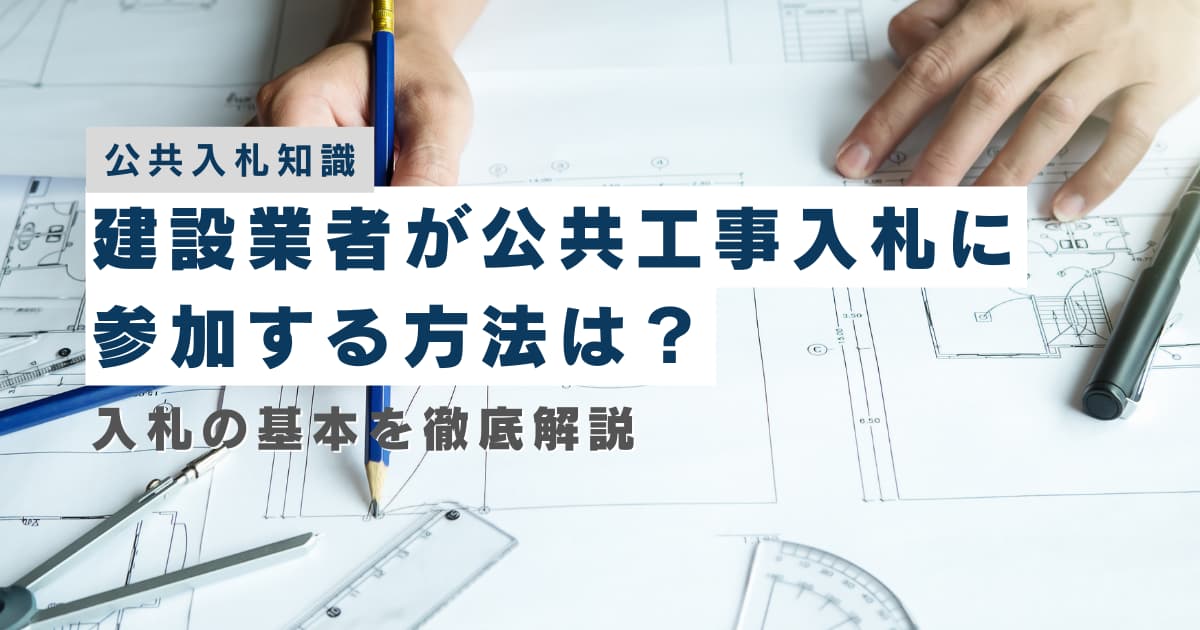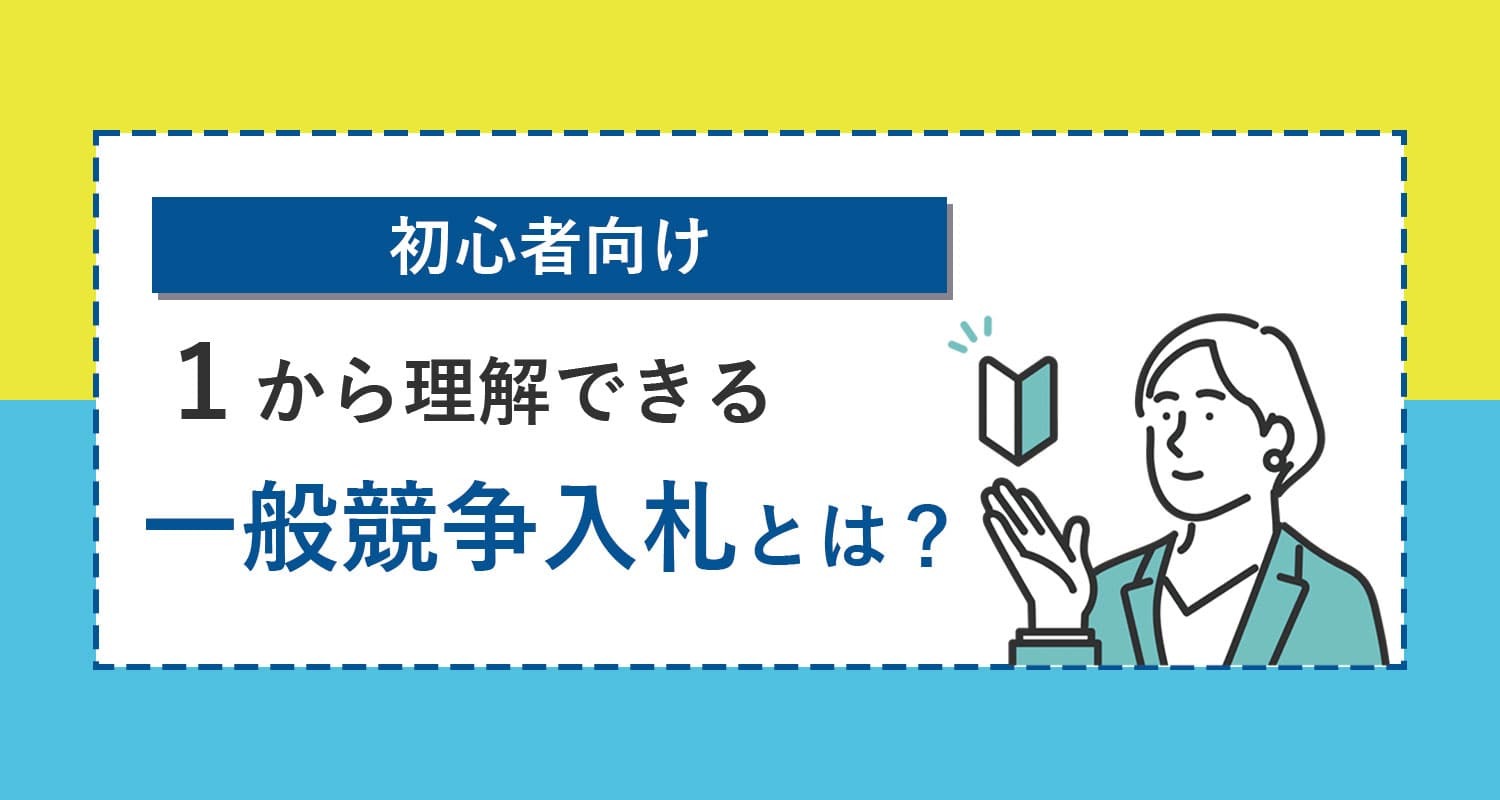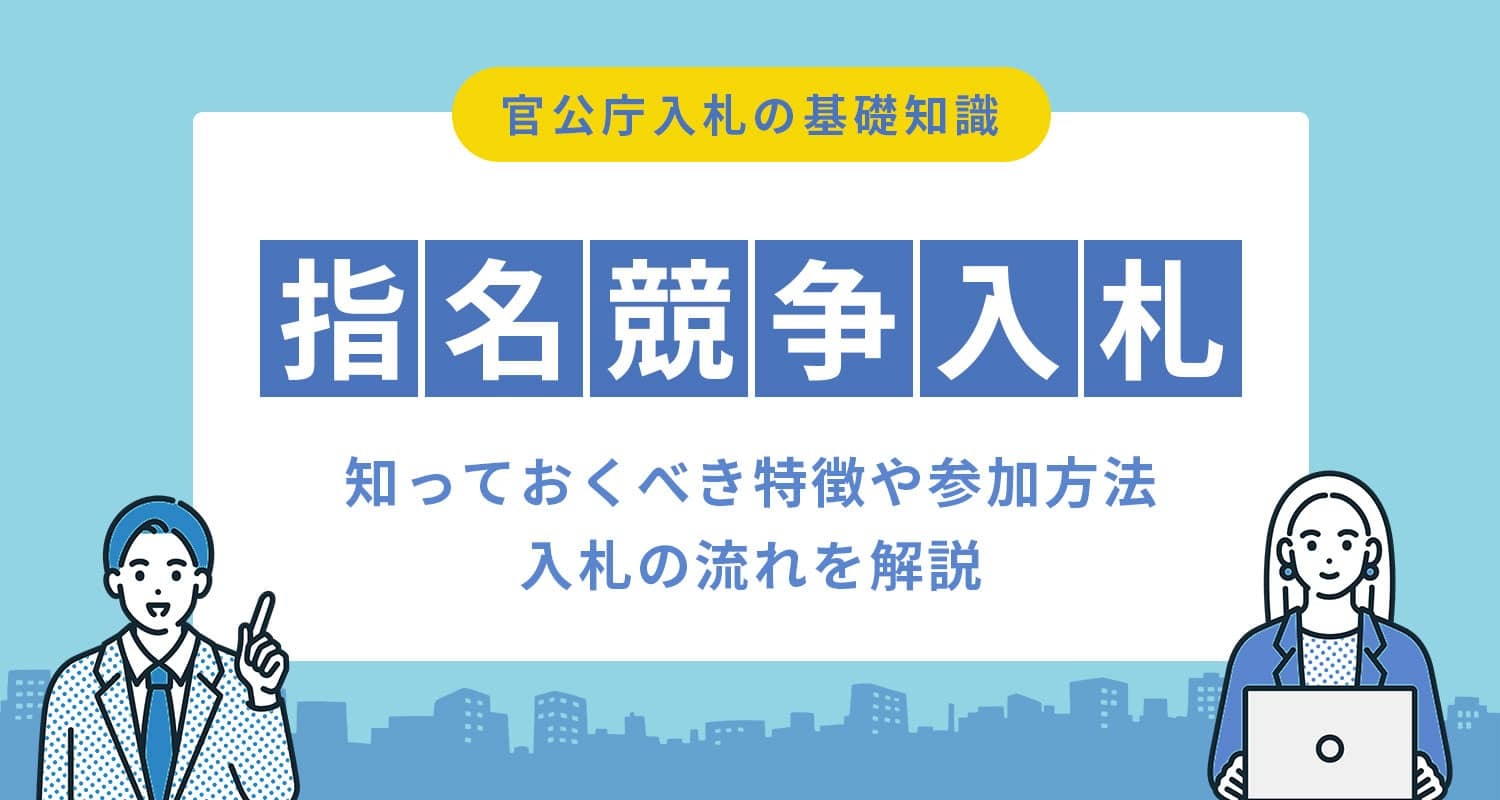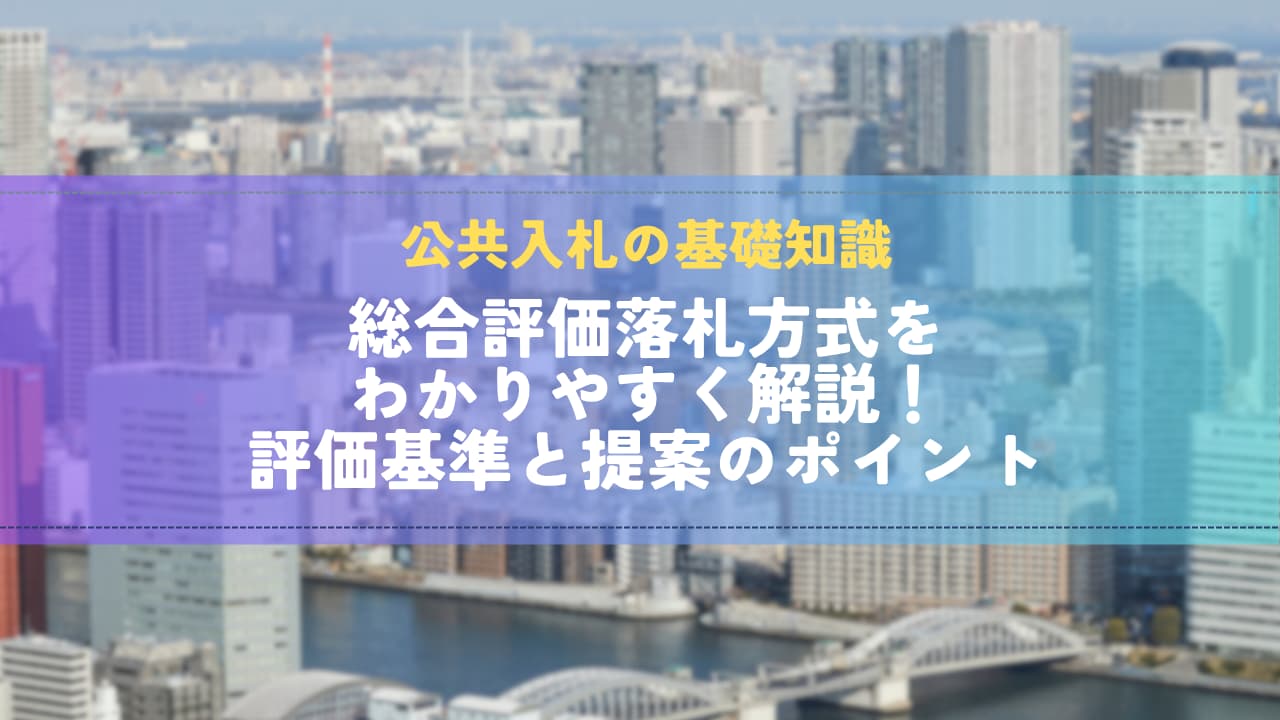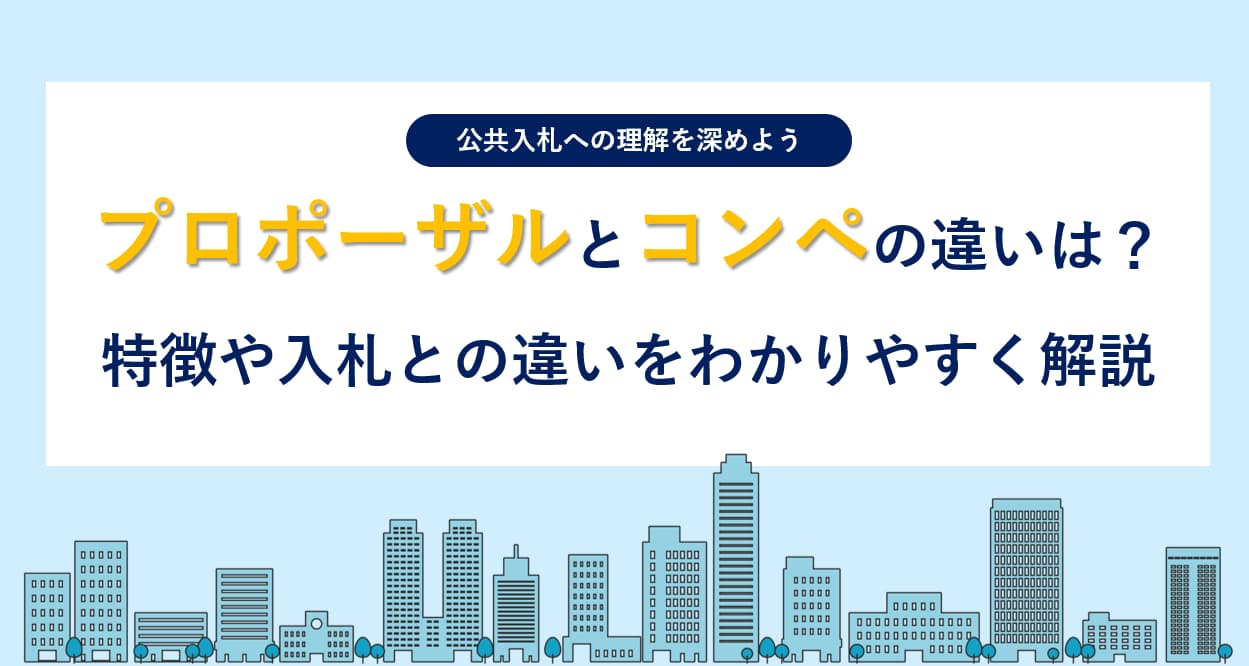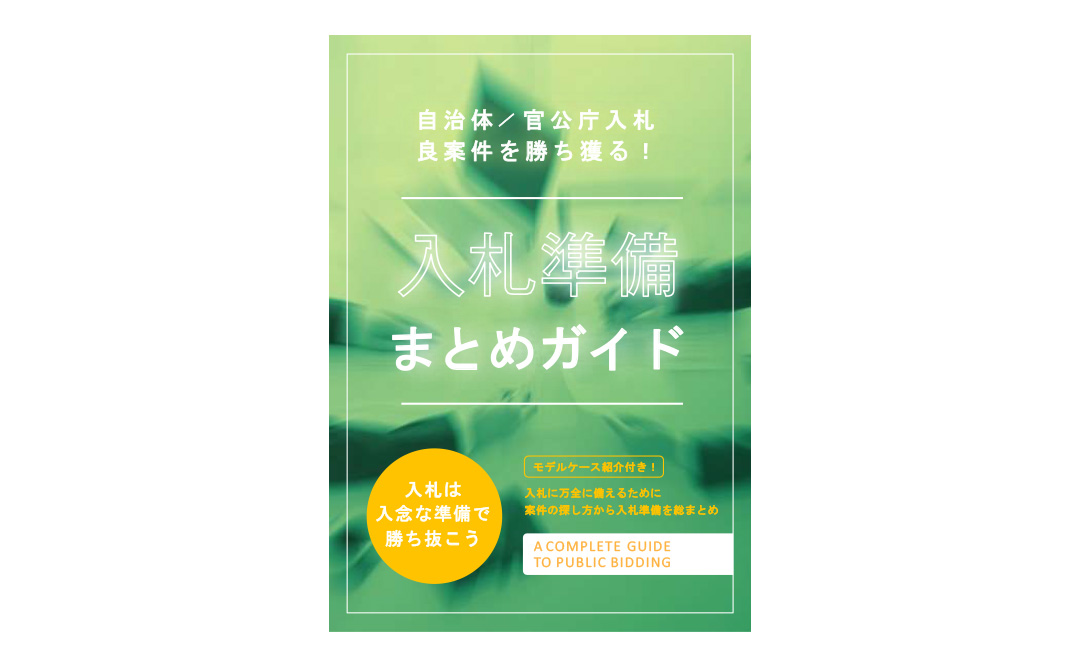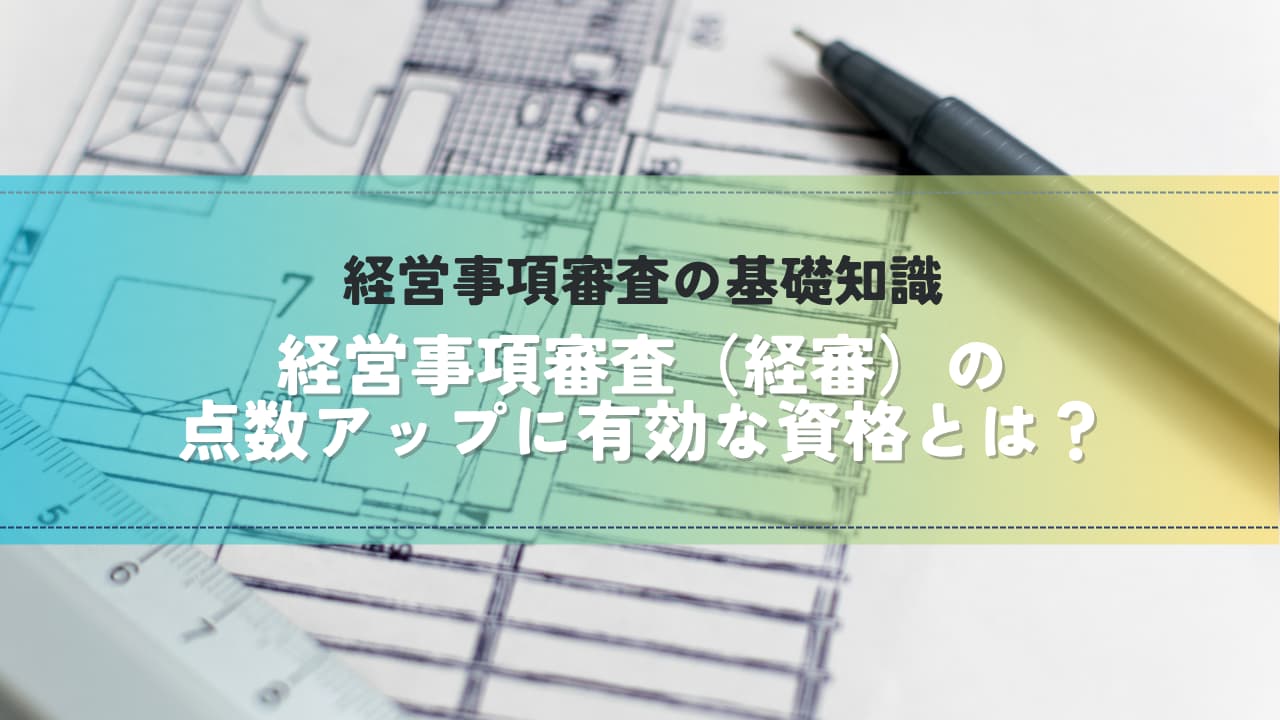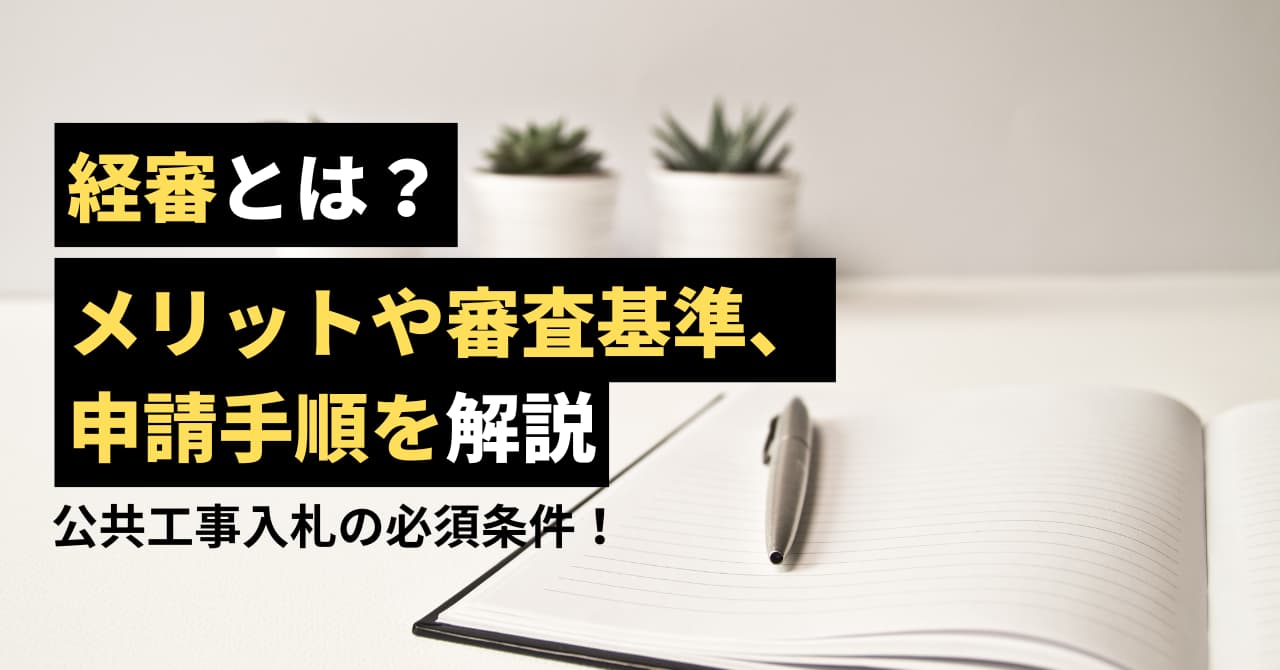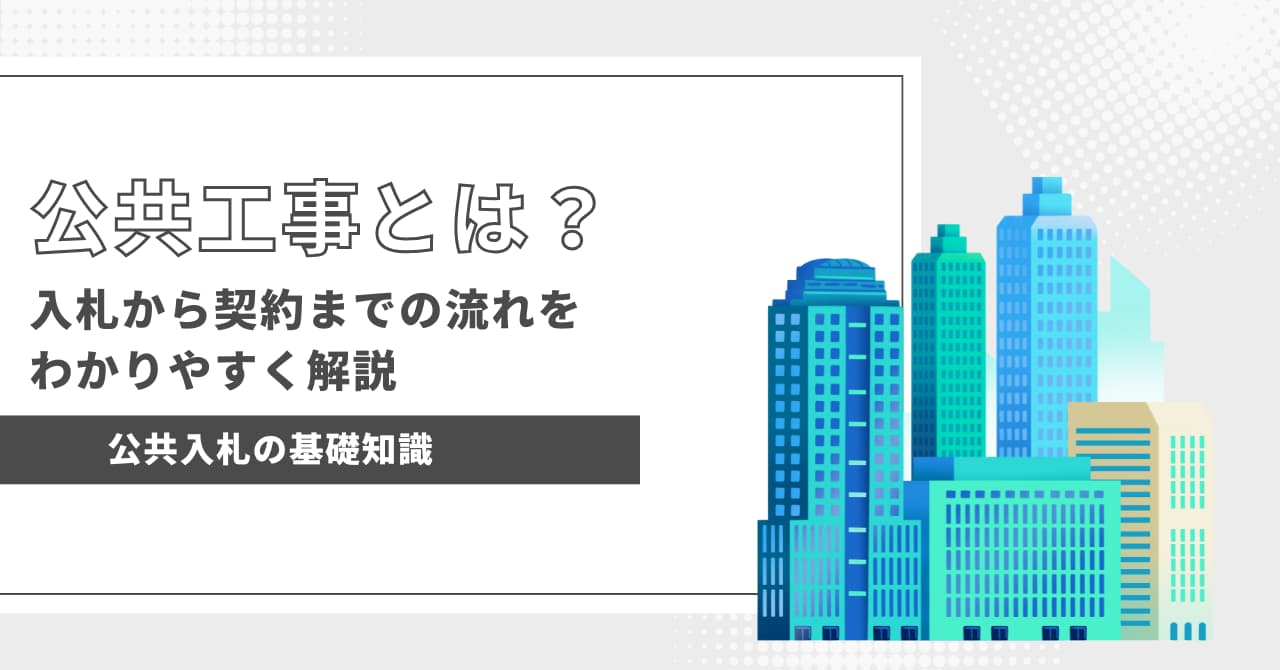- 公共工事の入札には、建設業許可の取得、経審の受審、入札参加資格の申請が必要
- 「総合評価落札方式」のように技術力や実績、施工体制なども評価される方式がある
- 入札参加資格はランクが高いほど大規模案件に参加可能
公共工事の受注を目指す建設業者にとって、入札への理解は欠かせません。安定した仕事を確保するために必要であり、事業の成長にも直結します。
ただし、入札には参加資格や準備が必要で、方式にもいくつかの種類があります。仕組みを理解していないと、せっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。
本記事では、建設業の入札に参加するための基本と流れをわかりやすく解説します。これから挑戦する方にも、改めて確認したい方にも役立つ内容です。
もくじ
建設業に関する入札の基本と具体例
公共工事においては、国や地方自治体などの発注機関が発注者となり、民間の建設業者が請負者として工事を受注します。
このような調達は、原則として「入札」によって行われます。入札とは、発注機関が示した条件に対して、請負を希望する業者が価格や提案内容を提示し、最も適した業者が選ばれる仕組みです。
入札の目的と基本原則
入札は、行政機関が支出する公費を適正に活用するための仕組みです。主に以下の3つの観点から入札が実施されています。
公平性の確保
すべての業者に平等な参加機会を提供し、特定の業者に有利・不利が生じないようにする。
透明性の担保
選定過程を公開することで、不正や癒着を防止する。
経済性・効率性の確保
市場原理を活用して、適正な価格で高品質な業者を選定する。
建設工事における入札の具体例
建設工事に関する入札では、次のような案件が典型例として挙げられます。
道路整備工事
国道、都道府県道、市区町村道の舗装敷設、修繕、改良工事など。
公共施設の建築・修繕工事
庁舎、学校、体育館、福祉施設などの新築・改築・大規模修繕。
河川・用水路・港湾関連工事
護岸工事、河川改修、堤防の草刈り、浚渫、漁港・港湾の整備など。
例えば、日本全国にある道路(公道)は、国・都道府県・市区町村が管理しています(高速道路等の一部例外あり)。
道路の新設はもちろん拡幅工事・維持管理・修繕業務が日々入札により発注されています。
建設業に関する入札の種類
建設業者が参加する建設工事における入札は、その契約方法や落札者の決定方式に応じていくつかのパターンに分類されます。
建設業者として入札に参加するためには、これらの違いを正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、入札の代表的な種類について、契約方式と落札者決定方式に分けて解説します。
契約方式の種類と特徴
まず、入札には大きく3つの契約方式があります。
一般競争入札
一般競争入札は、参加者の要件を満たしていれば、どの業者でも自由に参加できる方式です。公平性・透明性が高く、最も基本的な入札方式とされています。
指名競争入札
入札参加資格者名簿に掲載された事業者の中から、発注者が指名基準に基づき複数の事業者を指名し、指名された事業者のみで入札を行う方式です。この方法では、実績・資力・信用等が十分にある「特定少数」の事業者のみを入札に参加させることができ、業務品質の確保、事務負担の軽減が期待できます。
その一方で、指名にあたって発注機関の恣意性が発揮されやすい等のデメリットが指摘されています。
そこで、従来の指名競争入札を改良し、案件を公示し、提案書を提出した事業者から指名する「公募型指名競争入札」も行われています。
随意契約
特定の一者と相対で契約する方式です。緊急対応や特殊技術を要する工事、契約金額が小額の案件など、一定の条件を満たす場合に限られます。
厳密には入札ではありませんが、「公募型プロポーザル方式」など入札と同様に競争性を有する方法で随意契約の相手方選定が行われることがあります。
落札者決定方式の違い
入札に参加した後、どのように落札者が決定されるかについても複数の方式があります。
価格競争方式
最も低い価格を提示した業者が落札者となる方式です。価格だけで判断されるため、積算精度と価格調整力が求められます。
過去にはこの方式が一般的でしたが、いわゆる「安かろう悪かろう」の問題に対処するために、後述する総合評価落札方式との併用が進んでいます。
総合評価落札方式
価格に加え、技術提案や実績、品質管理体制なども評価対象とする方式です。価格だけでは測れない事業者の能力を総合的に判断できるため、現在では多くの大型案件で採用されています。
評価項目や配点などは発注機関・案件によって異なるため、公告内容・入札説明書をよく確認する必要があります。
プロポーザル・コンペ方式(随意契約)
主に設計業務や調査業務など、提案内容の質が重視される案件で採用される方式です。
建設工事関連では、設計・測量・調査業務で実施が見られます。
建設業に関する入札に参加する準備
公共工事の入札に参加するには、単に施工能力があるだけでは足りません。法的・制度的な要件を満たしておく必要があります。
ここでは、入札参加に必要な代表的な準備項目を紹介します。
建設業許可の取得
公共工事の入札に参加するためには、「建設業許可」を取得していることが必要です。
建設業許可は、請負金額500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上)の工事を請け負う場合に必須とされています。
許可権者は国土交通大臣または都道府県知事です。営業所を複数の都道府県に設置する場合は国土交通大臣の許可が必要で、申請先は国土交通省の地方整備局です。営業所が1つの都道府県内のみに設置する場合は都道府県知事の許可となり、申請先は各都道府県指定の窓口です。
建設業許可には、専任技術者の配置や財務要件、経営管理責任者の設置などの要件があります。未取得の場合は、まずはこの許可を取得することが最初のステップです。
経営事項審査(経審)の受審
次に必要となるのが、経営事項審査の受審です。
経営事項審査は、国や自治体が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない建設業法の規定に基づく審査です。
経営状況や技術力を審査し、総合評定値(P点)を算出します。
算出された総合評定値(P点)は後述する入札参加資格者名簿における「格付け」に影響します。経営事項審査の総合評定値(P点)が高いほど「格付け」が高ランクとなり、高額・高難度な工事案件への参加が可能になります。
入札参加資格の申請(資格者名簿への登録)
建設業許可を取得し経営事項審査を受審した後は、各発注機関に対して「入札参加資格申請」を行う必要があります。
これは、「この自治体の入札に参加できる業者」としての登録です。
国の機関であれば「全省庁統一資格」、地方自治体ごとにも独自の資格者名簿制度があり、それぞれに申請が必要です。多くの発注機関では、一定期間ごと(通常は2〜3年)に一斉受付の期間が設けられており、それ以外の時期でも随時申請を受け付けている場合もあります。
申請には、建設業許可証の写しや経審結果通知書、決算報告書などの書類が求められます。申請後、発注機関による審査を経て、資格者名簿に登録されると、ようやくその機関の入札に参加できるようになります。
格付けによる参加案件の制限
発注機関は、登録された業者に対して、経審結果などをもとに「格付け」を行い、業者ごとに参加可能な案件の範囲を決定します。格付けはS~Dなどのランクで表されることが多く、等級が高いほど大規模案件への参加が可能になります。
このため、単に登録されているだけではなく、より高い格付けを取得しておくことが、受注機会を広げるためには重要です。
建設業に関する公共入札に参加する手順
入札公告(案件情報)の収集
入札情報は、各発注機関(国・地方自治体・独立行政法人など)の入札システムやホームページで公開(公告・公示)されます。オフラインでは各機関の庁舎にある掲示板でも公開される場合もあります。
これらの媒体を定期的に確認することで、最新の案件情報を収集することができます。
また、広範囲の入札情報を効率的に収集したい場合は、民間の情報提供サービス(「NJSS」など)を利用することで、全国の入札案件を一元的に確認することも可能です。
質問受付・現地調査・仕様書確認などの準備工程
入札公告を確認した後、応札を検討する案件があれば、仕様書や設計図書などを精査します。これにより、発注者の要求事項や施工条件、納期、求められる体制などを正確に把握します。
疑問点がある場合は、公告で指定された期間内に「質問書」を提出し、公式な回答を得ることが重要です。また、現場条件が入札判断に影響する場合には、現地説明会や現場確認が設定されることもあります。これらに参加することは、入札の判断材料として非常に重要です
積算・見積書の作成、応札
自社で入札(応札)する価格を決めるために、公開された仕様書・設計図書に基づき積算を行います。積算には、材料費・労務費・機械損料・共通仮設費などを正確に反映する必要があります。
見積価格は、原価と利益のバランスを考慮しながら、過去の落札状況や同種工事の相場などを踏まえて決定します。
入札方式によっては、提出書類として見積書以外にも「施工計画書」「工期工程表」「技術者経歴書」などが求められることがあります。提出方法は、紙媒体による提出、電子入札システムによる提出など案件ごとに異なるため、公告や仕様書の指示に従うことが重要です。
開札・契約締結
期日までに入札(応札)された入札書を開封することを開札と言います。開札されると、入札書の内容が公開されます。
価格のみで落札者を決定する方式(価格競争方式)の場合は、最低価格を提示した者が落札者となるのが一般的です。一方、価格と技術提案を総合的に評価する「総合評価落札方式」では、技術点と価格点を合算した評価点に基づいて落札者が決定されます。
落札者となった者と発注者との間で必要手続を経て正式に契約が締結されます。契約内容には、工期・金額・履行条件などが明記され、契約後の工事遂行においては契約条件を遵守することが求められます。
建設業に関する入札で受注を獲得するポイント
建設業における公共工事の入札は、単に価格を安く提示するだけでは落札できないこともあります。公共工事の入札は「安かろう悪かろう」に対処するために、「総合評価落札方式」を導入するなどし、技術力や施工体制、過去実績なども重要な評価するようになっています。
ここでは、受注に向けて取り組むべき2つの観点、「応札案件を落とさないこと」と「応札可能案件を増やすこと」に分けて解説します。
応札案件を「落とさない」
入札では、形式的な不備があると入札参加が無効とされてしまいます。
たとえ自社の施工能力や価格競争力が高くても、提出書類の記載ミスや仕様との不一致があれば評価の土台に乗らない可能性があります。
そのため、応札を決めた案件については以下の点を徹底する必要があります。
仕様書・案件概要書の読み込み
入札説明書や仕様書には、提出物の形式、フォーマット、提出期限、技術提案の記載項目など、詳細なルールが記載されています。読み飛ばしや思い込みを防ぎ、仕様書に沿って漏れなく対応することが前提です。
形式要件の厳守
提出様式や押印の有無、ファイル形式など、細かな様式不備が失格につながることがあります。案件によって異なる形式要件に確実に対応するため、チェックリストを作成し、複数名による確認体制を整えることが有効です。
実績・技術の適切な整理
過去の施工実績を訴求する際は、評価対象とされる条件(例:類似工事の件数、施工年、施工規模等)に基づいて記載する必要があります。実績の過不足や対象外の記述は、減点または無評価となる場合があります。
こうした基本的な対応を徹底することで、せっかくの応札機会を無駄にせず、確実に評価対象として受け止められる状態をつくることができます。
応札可能案件を増やす
受注機会を広げるには、「自社が入札できる案件の範囲」を拡大することも必要です。そのためには、資格格付けの向上や案件情報の効率的な収集がカギとなります。
上位格付けの獲得
公共工事では、入札参加資格者に対して施工実績・経営事項審査(経審)・財務内容などをもとにした「格付け」を行っています。上位の格付けであるほど大型・高額案件への入札が可能になります。
そのため、上位格付けを得ることで案件の選択肢が増え、収益性の高い案件にも挑戦できるようになります。
格付け向上のためには、技術者の雇用・研修、適切な原価管理と利益確保、完成工事高の維持といった経営努力が必要です。
公共工事以外の民間工事も、施工能力の裏付けとして評価されるケースがあります。
案件情報収集の効率化
入札情報は各発注機関の入札システムやホームページで公開されるため、入札参加する発注者の数が増えるほど確認先のサイトが増えることになります。また、基本的に主体的に情報を確認する必要があり見逃してしまう懸念があります。
そのため、入札情報速報サービス(NJSSなど)を活用しすることで、効率的に自社向け案件を拾い上げることが可能です。
建設業に関する入札の情報収集を効率化するポイント
建設業者が公共工事の入札に効率よく対応するためには、日々の情報収集が不可欠です。しかし、入札情報の収集には手間がかかるという課題があります。
NJSSなら全国の入札情報をまとめて確認可能
こうした課題を解消する手段として有効なのが、入札情報サービス「NJSS」です。NJSSでは、全国の官公庁・自治体の入札情報を一元的に集約しており、検索条件を設定すれば、自社に合った案件のみを抽出して確認できます。
また、毎日配信されるメールによって、新着案件情報をタイムリーに受け取れるため、案件の見逃しを防ぎつつ、担当者の業務負担も大幅に軽減されます。
まとめ
建設業における公共工事の入札は、国や自治体が発注する事業に参加し、安定した受注を目指す上で重要な手段です。入札にはさまざまな契約方式や落札方式があり、案件の種類や規模、発注者の方針によって適用される仕組みが異なります。
また、入札に参加するには、建設業許可や経営事項審査、入札参加資格の取得など、事前に必要な手続きを整えておくことが不可欠です。これらの準備が整っていなければ、そもそも入札に参加することができません。
さらに、応札案件を確実に落とさないための書類作成や仕様書の理解、上位格付けの獲得のほか、情報収集の効率化も重要です。
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください。
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上