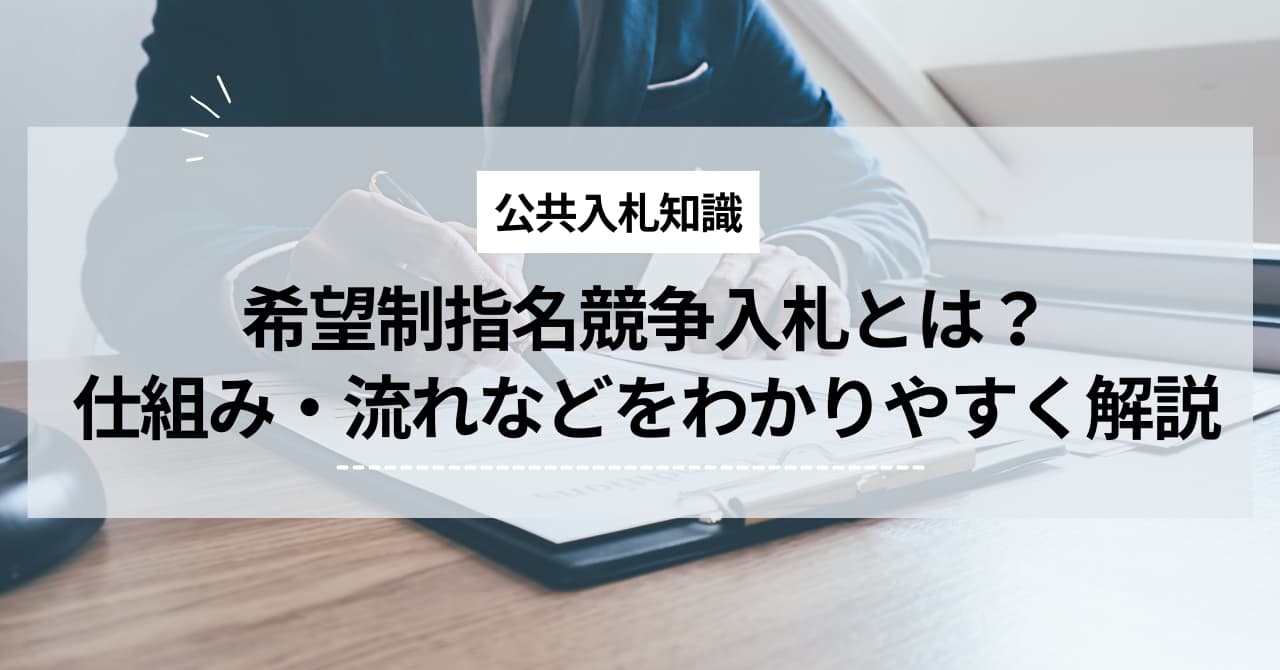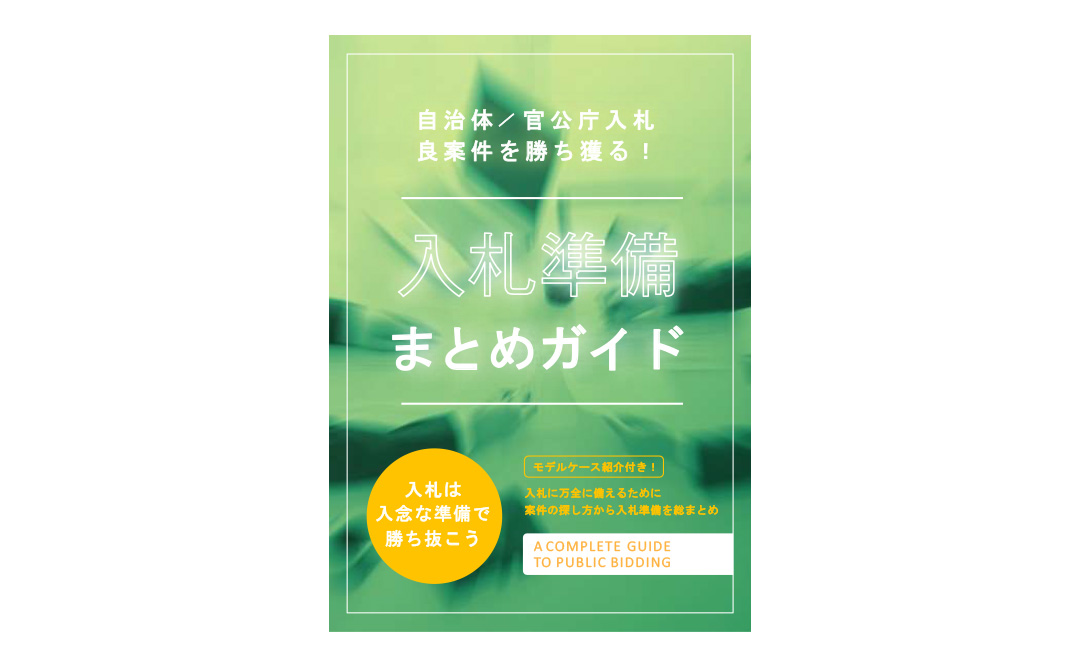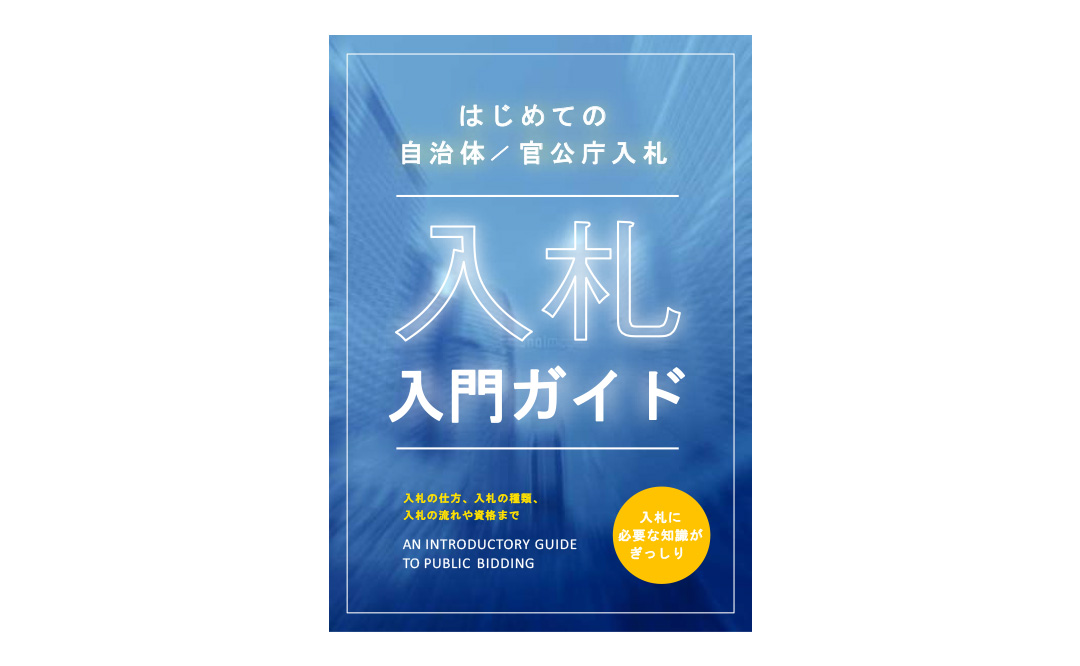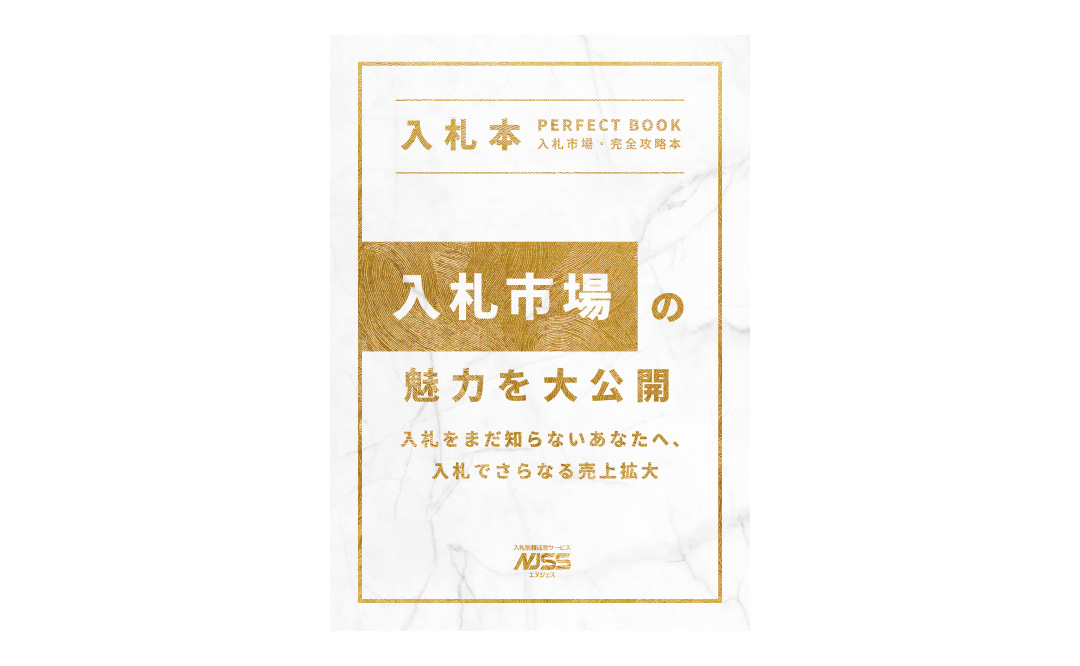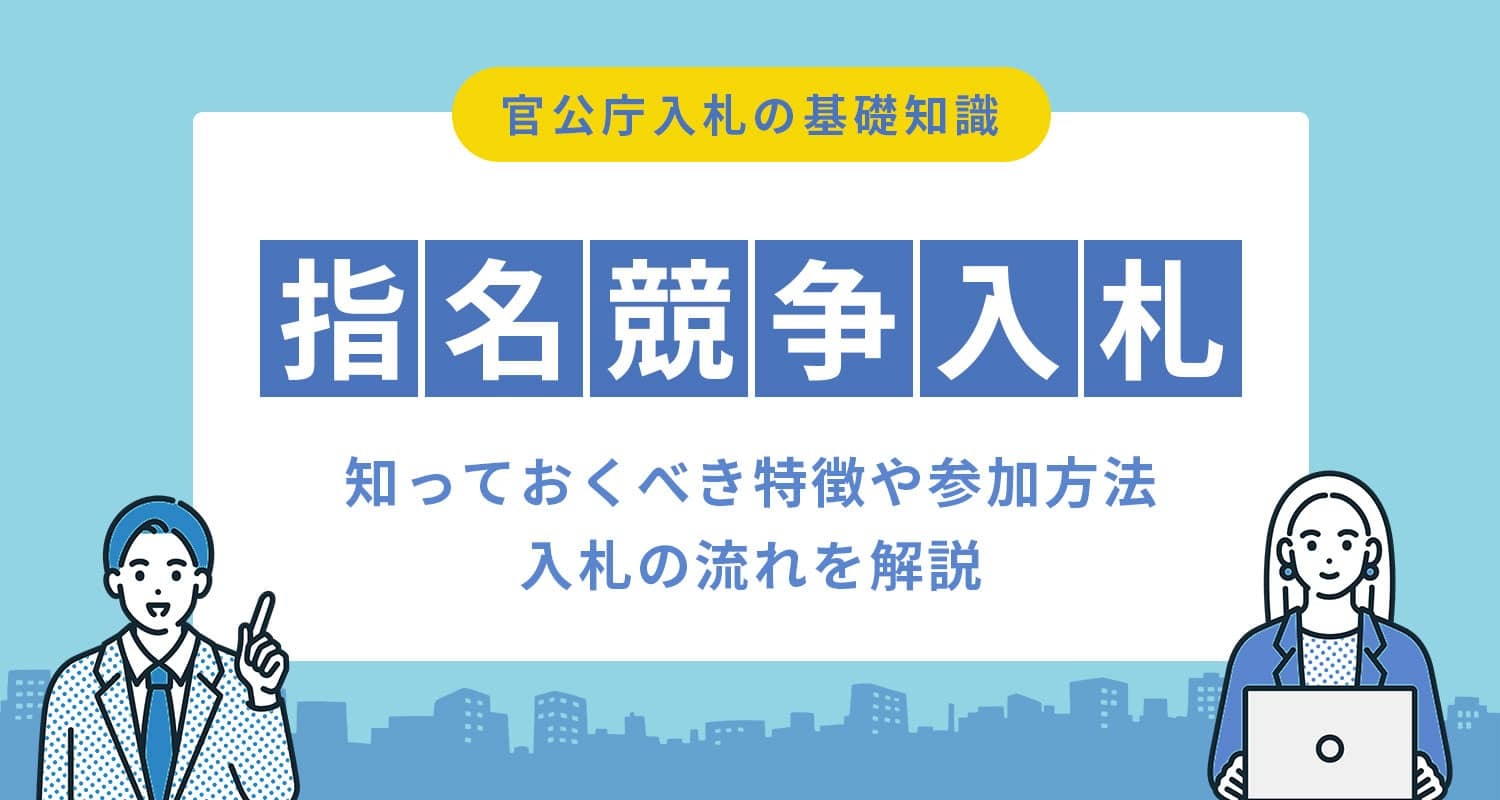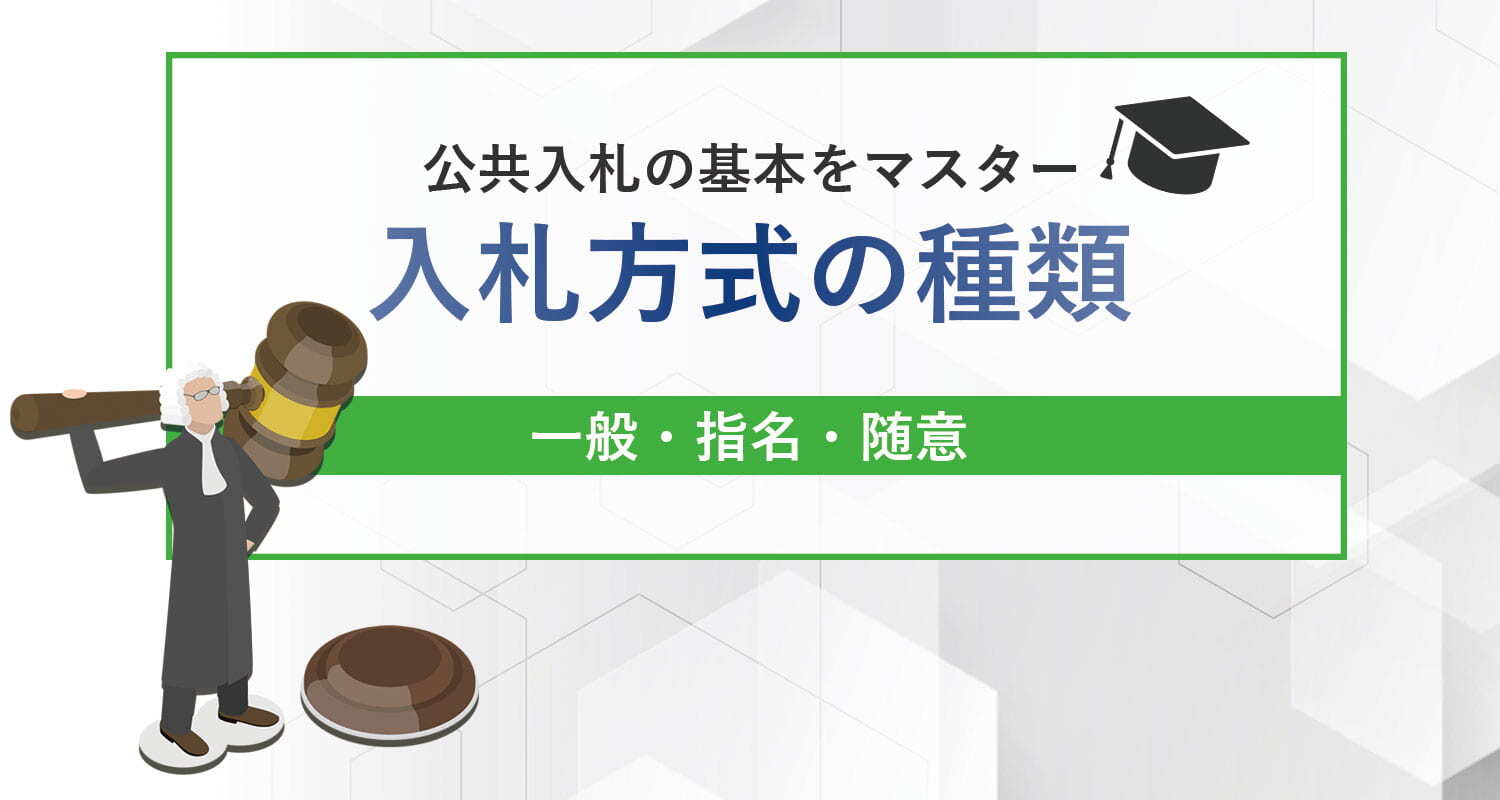- 希望制指名競争入札は参加希望者を募りその中から条件を満たした事業者を指名して行う入札方式
- 従来の指名競争入札と異なり参加機会が広がり、新規事業者にも参加できる機会が増える
- 品質と競争性を両立させることを目的とした透明性の高い制度
指名競争入札の一種に「希望制指名競争入札」というものがあります。
その名のとおり、事業者による希望を反映させた指名競争入札であり、従来の指名競争入札のメリットを残しつつデメリットを軽減させる方法とされています。
この記事では、希望制指名競争入札の仕組みや導入背景、一般競争入札や指名競争入札との違い、実際の入札の流れまでをわかりやすく解説します。
もくじ
希望制指名競争入札とは
「希望制指名競争入札」は、発注機関があらかじめ競争入札への参加希望者を公募し、応募者の中から技術力や実績など一定の条件を満たす事業者を指名して競争入札を行う方式です。
従来の指名競争入札とは異なり、「指名する前に参加の希望を募る」というステップが加わることで、参加機会を広げる制度となっています。
自治体よっては「公募型指名競争入札」と表現されることがあります。しかし、基本的な制度の内容は共通しており、「公募」→「指名」→「入札」という流れとなっています。
希望制指名競争入札が実施される背景とは
希望制指名競争入札(公募型指名競争入札を含む)は、発注者側の透明性や公平性、競争性を確保する目的で導入されてきました。
具体的には、以下のような背景から導入されてきました。
透明性・公平性の要求の高まり
指名競争入札は、発注者が事前に技術力・履行実績・地域事情への理解などを総合的に勘案し、履行確実性の高い事業者を指名して競争させる方式です。
複雑・高度な案件や、品質確保や工程管理が重視される案件では、無制限に参加を許すよりも、一定水準を満たす事業者間で競争させることで、品質と調達効率を両立しやすいという意義があります。
一方で、指名の過程が外部から見えにくいことに起因するデメリットも指摘されてきました。例えば、以下のような指摘があります。
- 指名基準や選考プロセスが不明瞭だと、恣意性が疑われやすい
- 「慣例的な指名」が続くと、新規参入が難しくなる
- 競争範囲が狭い場合、価格競争が十分に働かず、談合の温床になり得るとの懸念
こうした批判に対応しつつ、指名競争入札の利点を生かすために導入されたのが希望制指名競争入札です。従来の指名競争入札の品質確保・事務効率という利点を残しながら、透明性・公平性・新規参入機会を強化する仕組みになっています。
受注機会の拡大と新規事業者への配慮
希望制指名競争入札は、新規参入事業者や小規模業者にも門戸を広げる可能性があります。
事業者自ら入札参加を申込む機会があり、基準を満たせば指名されるため、「基準は満たすが他社より取引実績が少ない」「これまで指名されたことのない業者」にも受注機会が期待できます。
自治体によっては、受注能力および意欲のある事業者に十分な受注機会を与えることを制度目的として、指名競争入札を実施する調達において、積極的に希望制(公募)をする運用とする自治体もあります。
発注機関の事務効率化・手間の軽減
発注機関にとって、一般競争入札は指名競争入札と比較して、特に入札参加資格申請の審査で事務処理が膨大になりがちです。
一方、指名競争入札では、発注機関が一定の条件を満たす事業者を指名し当該事業者間で競争入札を行います。しかし、指名事業者の入札参加意欲が低く、入札不調(入札・開札前に指名業者が入札を辞退すること)になり、再度入札等の対応が必要になる懸念があります。
希望制指名競争入札では、最初に条件を公表して参加希望者を募ることで、一定の要件を満たした事業者のみが参加申請するため、事務負担の軽減が期待できます。
また、参加する事業者は一定の受注意欲があることが期待できますので、入札不調のリスクも軽減することが期待できます。
希望制指名競争入札と他の入札方式との違い
希望制指名競争入札は「公募による間口の広さ」と「事前審査による品質確保」を組み合わせた、指名競争入札のメリットを生かしながらデメリットを軽減させる方式です。
ここでは、希望制指名競争入札と代表的な入札(契約)方式との違いを解説します。
指名競争入札との違い:公示で参加機会が広がる
従来の指名競争入札は、発注機関が独自に候補企業を選び、指名通知を受けた企業のみが入札に参加します。
これに対し希望制指名競争入札は、まず案件を公示して参加希望者を募り、所定の基準で審査したうえで入札参加者を指名します。
そのため、特定の企業だけに情報が偏りにくく、新規参入や他地域の事業者にも門戸が開かれる点が大きな違いです。
一方で、入札段階に進めるのは審査を通過した事業者に限定されるため、品質確保や事務効率の観点は従来方式と同様に維持されます。
一般競争入札との違い:一定の要件を満たした者だけが参加できる
一般競争入札は、公告された参加資格(許可・等級・過去実績など)を満たせば、広く参加可能です。
参加者が多く、競争が強く働く一方で、案件によっては過度な価格競争や、発注者側の事務負担の増加が課題になることがあります。
希望制では、公告後に応募書類の審査(技術力・体制・過去実績等)を経て参加者を絞り込みます。
結果として、一定水準以上の事業者間での競争となり、品質や履行確実性を確保しやすいのが特徴です。
随意契約との違い:複数社での競争を担保
随意契約は、競争を行わず特定の事業者と契約する方式です(やむを得ない理由や例外事由に基づくもの)。
希望制指名競争入札はあくまで入札(競争)方式であり、審査を通過し指名された複数社の間で価格や提案内容を競わせる点が決定的に異なります。
希望制指名競争入札の流れ
希望制指名競争入札の流れは、「公示 → 参加申し込み → 事前審査による事業者指名 → 入札 → 開札・落札者決定」が基本です。
各段階で求められる様式や期限、提出物が明確に定められていますので、公告・要領・様式集を事前に丁寧に確認して対応することが重要です。
公示
まず発注機関が希望制指名競争入札の実施を公示し、参加希望の受付を開始します。
公示では、業務名や履行場所、契約期間、予定価格の取扱い、参加資格、提出書類、評価(選定)基準、質疑の方法と期限、全体のスケジュールなどが示されます。
まずは自社が要件を満たしているかを確認し、満たしていない点があれば早期に代替策の可否を検討します。
参加申し込み
参加を希望する場合は、公示に従って所定の様式と添付資料を提出します。
提出が求められる資料の例として、参加申込書のほか、会社概要、直近の決算書、同種・類似業務の実績資料、体制表(配置予定の管理技術者・主任技術者など)、誓約書や各種証明書があります。
電子申請の場合は、PDF形式やファイル容量の上限、ファイル名の付け方といった細かなルールに従う必要があります。紙提出では、押印の要否、原本と写しの区別、封筒記載事項など、形式面の要件を落とさないことが求められます。
事業者指名
発注機関が指名基準に基づき審査を行い、入札に参加させる事業者を指名します。
評価の観点は、参加資格を満たしていることに加え、同種・類似業務の実績、配置予定技術者の資格や経験、履行体制、品質・安全・BCPへの取り組み、地域貢献やコンプライアンス体制などが挙げられます。
審査の結果は指名通知または非指名通知として通知されます。
入札
指名を受けた事業者のみが入札へ進みます。
方式は価格競争のみの場合と、技術提案と価格を総合的に評価する方式の場合があり、どちらも入札説明書に従って提出物を整えます。
価格競争では、仕様、数量、歩掛等に基づいて積算を行い、指定書式で入札金額を提出します。
総合評価では、評価項目に対応した技術資料(提案書、工程計画、体制、リスク対応など)を作成し、ページ数やフォント、自己採点表の有無、根拠資料の添付可否といった細則を厳密に守ります。提出方法は電子入札または書面提出が指定されますので、提出期限や時刻、差し替えの可否、封印や押印の要領まで含めて手順を確認します。
開札・落札者決定
入札締切後、予定された日時に開札され、落札者が決定します。
価格競争の場合は、有効な入札のうち最低価格(または予定価格に最も近い価格)が原則となりますが、最低制限価格や調査基準価格に関する取り扱いが設定されているときは、そのルールに従って判定されます。
総合評価の場合は、技術評価点と価格評価を合算して総合点が最も高い提案が優位となり、落札者になります。
結果は落札者名や落札額、参加者一覧、評価結果の一部などが公表され、その後は契約締結手続に移行します。
希望制指名競争入札参加時のポイント
全体を通じて、様式・期限・記載ルールの遵守が最重要です。
形式不備は即時の失格につながることがあるため、提出前のチェックリスト化やダブルチェック体制を整えておくと、短い準備期間でも安定して対応できます。
特に総合評価を想定する分野では、平時から技術資料の雛形や事例を蓄積し、案件ごとに迅速にカスタマイズできる体制を整えることが、結果に直結します。
まとめ
希望制指名競争入札は、従来の指名競争入札に「公募」を加えることで参加機会を広げつつ、事前審査で一定水準の事業者に絞り込む方式です。品質確保と事務効率を両立しやすい点が特長です。随意契約とは異なり、指名事業者間での競争が担保されるため、透明性・公平性の面でも一定の効果が期待できます。
実務では、公告の要件・様式・期限に対応し、過去の同種案件で求められた評価観点(実績、体制、技術提案など)を踏まえて準備を進めることが重要です。
一方で、こうした案件を継続的に追いかけるには、発注機関ごとに分散した公告を漏れなく収集する体制づくりが不可欠です。
公示のタイミングや掲載先、用語の表記揺れを考慮すると、手作業だけでは見逃しのリスクが高まります。そこで、横断検索と新着通知を組み合わせて、情報収集の効率化を図ることをおすすめします。
こうした入札情報のリサーチにおすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。これまでのように発注者ごとに分かれた入札システムにアクセスする手間を削減できます。
NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください
国内最大級の入札情報サイト
- 掲載機関数8,900以上
- 掲載案件数年間180万件以上
- 落札結果1,800万件以上